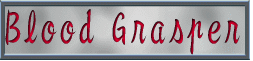
FILE1
…何故、こんな事になってしまったんだろう…?
雨に濡れたまま、呆然と立ちすくみながら、そう自問する。
舗装されたばかりの、真新しい農道のアスファルト。設置されたばかりのハロゲン灯の光が、雨に濡れたつややかな表面を
照らしている。
降りしきる冷たい雨が、濡れててかっているアスファルトの上に広がる、赤黒い液体を洗い流して行く。
そこに横たわったものが、恐怖に怯えた表情で俺の顔を見上げている。
胸に大穴が開き、そこから止めどなく溢れ出ていた血は、もう勢いがなくなっている。
食い千切られ、無残な傷が空いた喉からも、あまり出血はしていない。
…血が、もう残っていないからだ…。
それなのに、どうしてだろうか?
何故、俺が初めて目にするこの奇怪な生き物は、これだけの傷を負って、まだ生きていられるのだろう?
…こいつは、一体何なんだ?
奇怪な生物…、人の体形に、黒いつやつやした毛皮を纏う、黒猫と人の中間のような生き物…。
…何が起きた?
黒猫の化け物は、懇願するような光を両目に湛え、俺の目を見つめている…。
…俺は何をした?
黒猫の口元が動き、喉の傷口からゴボリと血が溢れ、ヒューヒューという隙間風のような音が聞こえた。
…俺は…何なんだ…?
声には成らなかったが、黒猫の言おうとした事が解った。つまり…、
「殺シテクレ」
冷たい雨に打たれているのに、俺の体は全く冷えて来ない。
なのに、体の奥、背骨の内側から来るような寒気が、俺の体を内側から冷やしている。
恐怖が、全身を貫く。
黒猫から顔を背け、足元に視線を向ける。
ハロゲン灯が照らす水溜りの中に、俺の顔が映り込んだ。…俺…?
水溜りの中には、見慣れぬ顔が映っていた。
犬…?いや、何か違う?これは…狼?
水溜りの中から、銀色の、一頭の狼が、驚いているように目を見開き、俺を見つめていた。
「な…?」
何だこいつ?
呟こうとした俺は、声を飲み込む。
水溜りの中の狼が、俺と同時に口を開いていた。
おそるおそる、俺は自分の顔に手を伸ばす。
心の中の何かが、止めろと叫んだ。だが、俺の手は止まらない。
水溜りの中で、銀の被毛に覆われた獣の指先が、その長い鼻面に触れる。
「う…、うっ…!」
心臓がデタラメに脈を刻み、肺が勝手に呼吸を乱し、喉が空気をひっかけて変な音を立てる。
「オォォォォオオオオオオオオオオオン!!!」
俺の喉から零れた絶叫は、人のモノでは在り得なかった…。
ここ、緑山町は古くから農耕で知られる広大な町だ。
人口に対して町の面積が異様に広く、田畑がやたらと多い。
なだらかで、広い山の麓に広がる田舎町で、良く言えばのどか。悪く言えば寂れている。
が、今年に入ってから少しは賑やかになった。というのも、大手製薬会社、相麻製薬の巨大な工場が移転してきて、そこで
働く従業員が、この町と付近の町に大量に転入してきたからだ。
それを見越して、半年以上前からコンビニがポコポコ経ち、自動車専用道路まで建設された。
まぁ、賑やかになるのは良い事だ。今年高校を卒業し、受験が上手く行けば上京して大学に通う俺にはあまり関係ないが。
…どうせなら、もう少し早く移転してくれば良かったのに…。
俺の名前は忌名夜彦(いみなよるひこ)。
この町の高校に通う三年生で、母と二人暮らし。
父は、俺が赤ん坊の頃に亡くなった。なので写真でしか顔は知らない。どんな人だったのかは母から話に聞くだけなので、
いまひとつ実感は無い。ただ、遺影の中の父の切れ長の目、堀の深い顔から、俺が父親似なのだという事だけは実感している。
俺、実は一昨日、大学の入試試験を終えたばかりだったりする。
合格通知は約十日後、二月初旬に届く。なので結果待ちとはいえ実に気楽だ。
おまけに明日から三連休と来れば、無駄にはしゃぎたくもなるというもの。
ホームルームが終わると同時に学校を飛び出した俺は、三年間愛用しているマウンテンバイクに跨り、商店街へと向かった。
…走り慣れたその道が、俺の人生そのものを、根底から覆す事件に繋がっているとも知らずに…。
ゲーセンで小遣いを使い、戦利品の菓子を鞄に押し込んだ俺は、チャリに跨って鞄を背負いなおした。
…いや、別に菓子なんて欲しくは無かったが、ついやってしまったのだ…。
ふと、何気なく首を巡らせた先に、スーツ姿の男が立っていた。
携帯で誰かと話をしているが、こんな時間に商店街をうろついている辺り、営業マンだろうか?
特に気にする事も無く、俺はチャリで走り出した。
男が寸前までオレを見つめていたのは、たぶん気のせいだったのだろうと考えて。
本屋やCDショップなどをぶらついて過ごすと、気が付けば時刻は五時を回り、夕暮れになっていた。
いつのまにか空は曇り、灰色に染まっている。気温はあまり低くないから、雨かみぞれになるかもしれない。
家までは自転車で30分程。夕食の少し前には家に着くはずだ。
チャリをこいで引き返し始め、そしてふとした気まぐれから、できたての新しい農道を通っていこうと考えた。
山の麓を走るそこを通ると、少し遠回りになる。が、もうじきこの町を離れる事になるんだ。少し探検しておこう。
人気も無く、車も通らない真新しいアスファルトの上を快適に飛ばし、俺は家に向かう。
まだまだ肌寒い季節だが、今日は比較的快適な気温だった。
気分良くチャリを飛ばし、農道の中間付近まで来た時だろうか?後ろから走ってきたライトバンが、俺を追い抜き、少し先
で止まった。
車の運転席から男が降り、軽く手を上げたので、俺は自転車を止める。
「やあ、済まないけれど、道を教えてくれないかな?」
男は、商店街で見たスーツの男だった。歳は30より少し行ったくらいだろうか?人の良さそうな笑みを浮かべ、道路マッ
プを片手に俺に歩み寄った。この辺りは一気に道が増えた。まだ道路マップに載っていない道も多いんだろう。
「良いですよ。何処までです?」
俺は、自転車から降り、押して男に近付く。
「ここは、この辺りだよね…」
男が地図を広げ、俺に見せる。俺は地図を覗き込みながら、
「ああ。今居るのはこの辺りで…っ!?」
俺は腕に鋭い痛みを感じ、息を飲んで一歩下った。
男の手には、ピストルのような形をした、太い針を持つ大型注射器…。…あれで刺されたのか?…まさかこいつ、人攫い…!?
そんな事を考えている間に、俺のからだから力が抜けた。自転車のハンドルが俺の手から逃げ、横倒しになる。続いて俺も、
膝から力が抜けて横倒しになった。
「…こちら06。先程見つけた対象を捕獲した。応援を頼む」
男は倒れた俺を見下ろしながら、携帯でどこかへ連絡を取った。
「さて…、念の為にしっかり麻酔をうっておこうか…」
男は倒れている俺に歩み寄り、屈み込んだ。
その時、俺の中で、強烈な恐怖が爆発した。
体中の毛穴が開き、鳥肌が立つ感覚。
汗が噴き出し、皮膚を伝う感覚。
パニックに陥りそうな恐怖の中で、俺はアスファルトに這いつくばったまま、動かない体に逃げろと命じる。
動け!逃げろ!
この二つの指令が、脳から立て続けに、繰り返し発信された。
男の手にした注射器が、俺の腕に迫ったその瞬間、俺の右手は、唐突に動いた。
いつもどおり、いや、いつにも増して素早く動いた手は、男の握る注射器を掴み、その脚へとグイッと振り下ろしていた。
「ぎゃっ!?」
男の悲鳴。太い注射器の針は、男の革靴を貫き、足の甲に深々と突き刺さっている。
もんどりうって転げた男の前で、俺はガクガクする体を叱咤し、這いずって距離を取る。
大声で誰か呼ぶ?いや、無駄だ!人が全然居ないし、さっきから車も通らない。そもそも、喉まで麻痺しているのか声が出ない!
這いずって距離を離しながら、なんとか首を捻って振り返ると、男は脚から注射器を引き抜いていた。
だが、麻酔は注射されたのだろう。立ち上がろうとして尻餅をついている。
「…くそっ!麻酔が足りなかったか!…このガキ…、大人しくしていればいい物を…」
男は憎憎しげに呟き、四つんばいになる。その顔にはもう、さっきの人の良さそうな笑みは欠片も見えない。
「…おしおきだ…、少し痛い目に遭わせてやる…。二度と歯向かう気が起きないようにな!」
男の顔の中で、両目がギリッと大きくなった。その瞳に見入ったまま、俺は息を飲む。
縦長の瞳孔…、男の両目は、まるで猫の目のように、縦に細い瞳孔になっていた。その目の周りを、顔全体を、いや、袖か
ら覗く手までが、黒い毛に覆われていく。
バリッと、何かが裂ける音がした。セミのさなぎが破れるように、男の背中でスーツが裂けた。そこから黒い毛に覆われた
背中が露出する。
靴の踵がブチンと音を立てて切れ、毛に覆われた足が姿を現す。裂けてスリッパのようになった靴は、足の一振りではがれ、
路面に落ちた。
夢でも見ているような変化は終わり、上背が伸びた男は、黄色く光る瞳で俺を見下ろす。
それは、直立した猫のような、奇怪な姿だった。
体付きは人間のようで、手も人間と同じ形、鋭い爪が生えている事を除けば…。しかし、脚は動物の後脚に近い。おまけに
尻尾も生えている。
…夢、だよな?これは…。
化け猫はゆっくり歩み寄ると、体がすくんで動けない俺の脇腹を、ボールでも蹴るように蹴り飛ばした。
衝撃、激痛、圧迫感、灼熱感、浮遊感、眩暈、嘔吐感。
蹴り飛ばされ、3メートルほど吹き飛んだ俺は、アスファルトの上に転がり、腹を押さえた。
込み上げる吐き気を堪え切れずに嘔吐すると、生暖かい血がバシャリと路面にぶちまけられた。
気が遠くなるような苦痛。内臓が破裂でもしたのか、あまりの激痛で汗が止まらない。
大粒の雨がポツポツ降り出し、瞬く間に湿ったアスファルトが光沢を帯びる。
「おっと、やりすぎたかな?まぁ、死ぬ事はないだろう」
死ぬ事は無いだって?もしかしたら内臓が潰れているかもしれない。肋骨は間違いなく折れているだろう。死んでもおかし
くないぞ!?
体は痙攣を繰り返すが、自分の意思で動かすことはできない。
逃げることも、声を上げる事もできない俺に、黒猫はゆっくりと歩み寄る。
その黄色い瞳が投げかける光に、俺は戦慄した。まるで、手頃な獲物を見つけた、猫のような…。
再び強い恐怖が俺の中で膨れ上がる。
死にたくない!
今度は、ただその一つのその意志だけが、俺の心を満たしていた。
ドクンと、心臓が脈打った。
心臓麻痺?心筋梗塞?不整脈?恐怖のあまり何か発作でも起こしたのか?そんな事を考えるほど、異常な鼓動だった。
しかし、俺の不安を無視して心臓は止まる事無く動く。
そして、その強い鼓動は一回だけでなく、何度も繰り返す。繰り返しながらどんどん速くなってゆく。
ドクン、ドクンが、どんどん速まり、ドッドッドッドッと早鐘のようになり、血管内を凄まじい速度で血液が流れ、冷たい
雨に濡れそぼった体が熱くなる。
「ルオオオォォォオオっ!!!」
どこかで、犬の遠吠えのような声が聞こえた。
全身がむず痒くなり、首が、背骨が、尻が、手足の関節が鈍く痛む。
筋肉が張り、手足がミシミシと音を立てる。
何故かコートのボタンが飛び、その下で制服のボタンも飛び、ワイシャツが破れる。
痛み。だが、それよりも強い開放感を感じていた。
快感といっても良いほどの強烈な開放感に、俺は全身を震わせる。
…気持ち良い…。なんだか、体に纏わり付いていた重しでも外したような…。
体が動く。地面にはいつくばったままだった俺は、身を起こし、膝立ちになる。
不思議に、腹の痛みは消えていた。痛みの余り、感覚が麻痺したのか?それに、この開放感は何だろう…?これまでに味わっ
たことの無い気持ち良さ…。
もしかして、俺、死ぬ寸前なんじゃないだろうか?これって天にも昇る気持ちっていうアレなのか?
にわかに怖くなってきた俺の前で、黒猫は目を見開き、こっちを凝視していた。無理も無い。動けたのは自分でもびっくり
だったしな…。
「…じ…、人狼だと…!?」
黒猫は掠れた声で呟いた。その瞳には…、え?怯え…?
黒猫はじりじりと後退する。なんだか知らないがビビッてるようだ。
もしかして…、俺、助かるのか?
僅かな期待が首をもたげたその時、胸の中で何かがざわめいた。
脳裏には、何故か炎が浮かんでいた。それも、ただの炎じゃない銀色に輝き、冷たく燃える炎…。
荒々しく、雄々しく、猛々しい。それでいていやに静かに燃えるそれが、俺の深い所で囁いた。
『そいつは敵だ。生き延びたければ狩れ』
それは決して明確な言葉なんかじゃなかったが、あえて言葉として表現するなら、そんな感じだったろう。
俺は、いや、俺の体は、即座にその声に従った。
足が濡れたアスファルトを蹴り、濡れた体から水気が霧のように後方へ飛ぶ。
カメラがズームするように、黒猫の顔が急速に近くなる。
怯えの色を浮かべる黄色い瞳が、何か異様なものを映していた。…犬の顔のような…?
「ひぃっ!?」
悲鳴と共に、猫の腕が横殴りに振るわれた。鋭い爪を備えた左手が、掴むように五指を広げて俺に迫る。が、俺の顔が張り
飛ばされる前に、猫の左腕は、肘から先が消えていた。
斜め下から、体を捻って振り上げられた俺の左手が、刃物のように長く、鋭くなった爪を広げて、猫の肘から先を切り飛ば
していた。
さらに振り上げた左手を抱え込むようにしつつ体の捻りが戻り、その勢いを乗せて右腕が突き出される。
「ぎゃぁぁぁぁあっ!?」
絶叫と鮮血が曇天へ舞い上がる。
俺は自分の腕を、信じられない気持ちで見つめていた。
右腕の…、肘のところまでが、猫の鳩尾に埋まって…?
黒猫がゴボッと何かを吐き出す。俺の胸を、突き出した腕を、黒猫が吐き出した血がバシャリと濡らした。
『まだだ。止めを刺せ』
声が、再び命じた。俺の体は即座に声に従い、首を横に寝せつつ、ビクビクと痙攣する黒猫の首筋へと口を近づける。
ブツリと、尖った牙が肉に突き刺さる嫌な歯応え。次いで生暖かい何かが口の中に溢れ出す。
素早く首を振りながら口を離すと、黒猫の喉から噴水のように血が吹き上がった。
口の中に残った、黒猫の喉から剥がれた何かを、雨の中に吐き捨てる。
俺は…何をしているんだ?
急に、意識が冷めた。
腕から力を抜き、だらりと垂らすと、猫の体は滑り落ちるように俺の腕から抜け、濡れた路面に横たわる。
周囲に撒き散らされた血が、冷たく降りしきる雨の中で湯気を上げていた。
「オォォォォオオオオオオオオオオオっ!!!」
肺が空になるまで叫び声を上げ続けた俺は、アスファルトの上に跪いた。
濡れそぼったアスファルト、浅い水溜りに映り込む、変わり果てた自分の顔…。
「…なんだよ…これ…」
と、呟いたつもりだったが、口の形が変わっていて、舌が長くなったせいなのか、発音が上手く行かなかった。口の端から
しゅうしゅうと空気が漏れてしまう。
何で、何でこんな事に…?
あ、そ、そうか…、あの注射、さっき打たれたあの注射のせいだ!
あれはきっと、麻酔だけじゃなく何か変な薬が混じっていて、それのせいで、そこの男も、俺も、こんな風に体が変形して
しまったんだな?
一種の病気みたいなものか?解毒剤とかあれば、治るんじゃないのか?
いや、もしかしたらこれは一時的なもので、放っておけば薬の効果が切れて治るのかも!?
だが、この格好じゃ家に帰れない。それに…、
俺はちらりと黒猫を見る。死んでは、いないよな?でも、傷害罪くらいにはなっちゃうかな…?
と、とりあえず、母さんに電話だ。体が治らないと帰れないし、遅くなる事を伝えておかないと…。
体が大きくなっているのか?コートを脱ぎ、ボタンが飛んで前がはだけた制服をまさぐり、俺は携帯を取り出す。
…何だよこの爪…?ボタン押し辛いな…!
指先から伸びた、鋭く長い爪に悪戦苦闘しつつ、短縮ダイヤルを操作しようとした時、後ろで、ドサッ、と音がした。
びっくりして振り向くと、10メートル程先、傘を差し、雨がっぱの上下を着た少女が、こっちを見て立っていた。
背には大きなザック。落っことしてしまったんだろう。大きなケーキ屋の袋が濡れた地面に落ちている。
「あ、あ…」
俺は頭の中が真っ白になりながら、ブンブンと首を横に振った。勢いよく振ったので、水を吸った毛からしぶきが飛び散る。
「お、俺っ、怪しい者じゃないからっ!」
いや怪しいだろう。内心自分につっこみながらも、俺はまた発音がおかしい事に気付き、言い直す。
「俺は怪しい者じゃありませんよ!?」
「鏡を見て物を言いなさいよ!無茶苦茶怪しいじゃない!」
少女はきっぱりと言う。…うわぁ、へこむぅ…。
って、つっこめるのか?この状況で?
俺は少女の姿をマジマジと見つめた。こんな状況でも、少女は逃げもせずそこに立っている。悲鳴を上げて逃げ出されても
無理は無いのに…。
「…その制服…?あんた…、うちの学校の生徒…?犬顔の生徒なんて居たかしら?」
少女はケーキ屋の袋を拾いながら、訝しげに首を傾げると、つかつかと俺に歩み寄った。
…なんていうか、キモが座ってる…。
そいつが目の前で足を止めた時、俺は相手が誰であるか気付いた。
…なんてこった…。よりにもよってそいつは、俺と同じクラスの女子だった!
川村朝日(かわむらあさひ)。今は引退しているが、以前は合唱部に所属していた、校内一の美人と評判の女子。
カワムラはつり上がり気味の目を細め、俺の胸元を見る。
「ん?三年?ますます覚えが無いわね…」
制服の左ポケットには、学年ごとに色が違う校章のバッヂがついている。カワムラはそれを見てから顔を上げ、俺の顔を見
上げた。
「あんた、名前は?」
「い、イミナ…」
カワムラは「ん?」と首を傾げる。
「イミナって、イミナヨルヒコ?」
「う、うん…」
俺が頷くと、カワムラはさらに不思議そうに、今度は逆側に首を捻った。
「昼間は、そんな顔してなかったわよね?」
「まあね…」
「その顔…、お面…じゃなさそうね…」
カワムラは「ふーん」と、俺の顔をじろじろと眺める。それから俺の後ろに視線を向け、そして息を飲んだ。
「な、なにこれ!?これもうちの生徒!?」
横たわる黒猫に気付き、少女は声を上げる。
「いや違うって。スーツ着てるじゃん…」
「じゃあ先生!?」
「いや、学校とは無関係だから…」
「なら赤の他人!?」
「そうなるかな…」
…なんだか疲れる…。
「あんたがやったの!?」
「うっ!?こ、これはその、正当防衛だっ!」
俺は発音が怪しい言葉で、たどたどしく状況を説明した。
「ふーん…。怪しい注射…。人攫い…」
カワムラは顎に手を当てて考え込むと、「あ」と声を上げた。
「そこの人…、人…?とにかくそいつ、電話してたのよね?応援呼ぶって言ってたのよね?」
「うん。…あ!」
何で思い出せなかったんだ!?
「ずらかったほうが良いわね…、とりあえず、鞄持って!」
「あ、ああっ!」
「あと自転車!邪魔になるから…」
邪魔になる?逃げるなら自転車に乗って行った方が良いと思うが…、
少女は俺の自転車を起こし。周囲を見回すと、田んぼの傍を流れる用水路に、「えいやっ!」とマウンテンバイクを突き落
とした。
「うぉおおおおおおおおい!?何してんのお前ぇええええええ!?」
慌てて駆け寄ったが、深い用水路は茶色く濁っていて、愛車の姿は見えない。ポコンと浮いた泡が、雨に叩かれて弾けた。
「後で回収すれば良いわ。とりあえず逃げるの!」
「に、逃げるって…、自転車が…」
「自転車は邪魔になるだけよ!山に登るんだから…」
カワムラは言葉を切り、首を巡らせる。その時には俺もすでに振り向き、遠くから走って来る車のライトを確認していた。
「行くわよ!…本当は誰にも話すなって言われてるけど、仕方ないわよね…」
ぼそぼそと、困ったように呟くカワムラに、俺は尋ねる。
「山になんか逃げてどうするんだ?」
俺の質問に、少女は口の端をキュッと吊り上げ、悪戯っぽく笑った。
「山の主に助けて貰うのよっ」