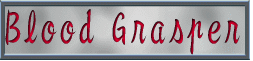
FILE11
「情けないなぁ…」
俺と04の肩を借りて辛そうに歩きながら、ビャクヤは呟いた。
「こういう時、何事も無かったように颯爽と歩ければ格好良いんだろうけれど…。やっぱり僕は三枚目だねえ…。ま、二枚目
な外見も性格もしていないけれど…」
「何を言うんだ。ビャクヤは男前だよ。俺が知っている中で最高の!」
俺の心からの賛辞に、挟まれて歩いているために左右のどちらにも顔を背けられなかったビャクヤは、ちょっと恥かしそう
に視線を上に逸らした。
思うに、ビャクヤはもっと堂々として、威張ってふんぞり返っていて良いと思う。
ビャクヤは強いし、優しいし、頭も切れるし物知りだ。
俺が知っている誰よりも優れているのに、威張った所が全然無い。むしろのほほんとしていて、ちっとも偉ぶらない。
まぁ、そういう飾らない、無駄に威を誇示しないところが魅力なのかもしれないけれど…、いつでも無駄に偉そうなカワム
ラとは本当に大違いだ。
…もっとも、思ってはいても、面と向かってアイツに「偉そうだ」なんて、俺にはとても言えないが…。
「…何と礼を言うべきか判らない…。この恩義は必ず返す。この命に代えても…」
俺と反対側でビャクヤの肩を支えている04が、少し俯きながら小声で言った。薄桃色の長い毛が俯いた顔に掛かっていて、
表情は見えない。
「せっかく助かったんだから、そんなライトに命を使わないでよ。それじゃあ僕がズタボロになった甲斐がないよ?」
ビャクヤが冗談めかして言うと、04は「済まない…」と呟いて黙り込む。
05と07の亡骸は、簡単にで悪かったけれど、きちんと埋葬してきた。
二人の爆弾はビャクヤが処分した。
「死人に鞭打つようで気がひけるね」
そう言ったビャクヤは、二人の頚骨を砕いて、爆弾が破裂しないよう慎重に摘出した。
無傷で取り出された爆弾を仔細に眺め、弄り回して、しばらく何かを確認したビャクヤは、ぼそっと何かを呟くと、おもむ
ろに爆弾を握り潰してしまった。
どういう訳か爆発は起きなかった。あれも、ビャクヤの持つ不思議な力の作用だろうか?
危ないから。とさがらされていた俺は、いつ爆発するかと気が気じゃなかったが…。
04は、並べて横たえた二人の亡骸に、自分が着ていたベストを広げて乗せ、一緒に埋めた。
意見の食い違いはあったかもしれない。衝突だってあったかもしれない。
それでも、彼女にとって、二人は自分と同じ境遇の「仲間」だったのは考えるまでもなく判る。
何も語らなかったけれど、彼女がどんな気持ちで居るかは、俺にもビャクヤにも良く判った…。
戦闘の痕跡を完全に消すことは不可能だったけれど、俺達は消気水で匂いを断って移動してきた。
最悪の場合、追撃が出されても、これで即座に急襲される事だけは避けられるはずだ…。
「ふぅ…」
小屋に着き、リビングの椅子に腰を降ろしたビャクヤは、大きく息を吐いて、大儀そうに背もたれに体重を預けた。
…かなりきつそうだ…。こんなビャクヤ、初めて見る…。
「さて…、えぇと…、ゼロヨンさん?」
入り口の所で立ち止まっていた04は、ビャクヤに声をかけられると、直立不動の姿勢をとった。
ビャクヤは前髪を撫で付けて失った目を隠しながら、04に微笑みかけた。
「はは、そう硬くならないでよ?まずはゆっくり休んで、力を戻してって言おうとしただけさ」
責められるとでも思ったのか、それとも尋問めいた事でもされると思っていたのか、ビャクヤの言葉を聞いた04は、少し
ばかり拍子抜けしたような表情を見せた。
「君はもう自由だ。動けるようになったらあとは好きにすると良いよ。もちろん、力が戻るまでは、遠慮せずここに居てくれ
て構わないからね?あぁ、ベッドは空いてるから、今日のところはまずゆっくり休むと良い。傷の修復に随分力を使っただろ
うしね」
「しかし、そこまで迷惑をかける訳には…」
「遠慮しないで。男が使ったことはないから」
男が使ってない?…ああ、カワムラが泊まる時のベッドを使わせるのか。…バレたら何て言われるかな…。
「ヨルヒコ。明日は学校休みだったよね?ケイコさんに電話して、君も今日はここに泊まって、休んでいったほうが良い」
「…そうだな。そうするよ」
俺が電話をしている間に、ビャクヤは小屋の間取りを04に教えていた。
「明日にでも、少し話を聞かせて貰えると助かる。僕らも相麻の事を知っておきたいからね」
「判った。私が知っている限りの全てを、包み隠さず話そう」
頷いた04から視線を外し、ビャクヤは俺に視線を向ける。
「ヨルヒコ、君も今日はもう休んだ方が良い。その様子じゃインパルス・ドライブを使ったね?体中ガタガタだろうし、たっ
ぷり眠って力を取り戻さないと」
ちょっと驚いた。俺の消耗の原因にも、ビャクヤは気付いてたのか?
…自分だってボロボロのくせに、なんでそう他人の事ばかり気遣うんだよビャクヤ…。
「…ああ。とりあえず、彼女を部屋に案内してくる。ビャクヤこそ先に休んでてくれよ」
言いたい事はあったけど、後だ。俺は大人しく04を部屋に案内する事にした。
ついさっきまで敵同士だったとはいえ、彼女にはもう、俺達に害を加える意志は無い。
ビャクヤくらい鼻が利けば、相手が嘘をついているかどうか察知できるらしいけれど、俺にはまだ無理。
それでも、きっと彼女は大丈夫。ビャクヤも警戒していないし、信用して良いと思う。
無駄な殺生を嫌い、自分に不利になるにも関わらず、無関係な相手を逃がそうとする。彼女はそんな心根の持ち主なんだから。
「…待ってくれ」
ドアを閉めようとした俺に、04は寝室となる部屋の中から、躊躇いがちに声をかけてきた。
俺の方が少し背が高いので、近くで顔を見合わせると、彼女が少し見上げる形になる。
「…世話をかける…。敵である私に、ここまでしてくれるとは…。もはや、何と詫び、何と礼を言えばいいのか、言葉も浮か
ばない…」
「気にしないでくれ。仕方なかったんだろう?それにもう敵じゃない。…俺も…あんたの仲間を三人も殺してしまったし…」
「それこそ正当防衛だったのだろう?互いに、生きるために命を奪い合ったのだ、誰が死んだ、生き残ったで、恨み言は言え
ないさ…」
04は目を伏せ、呟くようにそう言った。
俺達に感謝しているのは嘘じゃない。でも、憎しみや恨みも必ずあるはずだ。
それを…、彼女は不毛な感情として、きっと押し殺しているんだろう…。
桃色の猫の、愁いに満ちたその表情すらも、俺には美しいと感じられた。
…美しい…。
そう…、俺は04の事を美しいと感じている。…意識すると、トクンと、胸が鳴る…。
人ではないその姿に、凛とした立ち振る舞いに、一つ一つの何気ないその仕草に、俺は美しさを見出していた。
相麻という組織の枷に捕らわれていながらも、決して心まで飼い慣らされはしなかった、気高い獣の魂…。
自分の立場を悪化させる恐れがあっても、無関係の者を巻き込まない。
そんな、信念を曲げようとしなかった誇り高い精神に、魂に、俺は惹かれているのかもしれない…。
…異性にこんな感情を抱くのは、これまでで、初めてだ…。
「あの…さ…」
意思に反してせわしなく動こうとする尻尾を右手でギュッと掴み、押さえ込みながら、極力何でもない風を装って、俺は口
を開いた。
「あんたの名前、教えてくれないか?ゼロヨンっていうのは、本名じゃないんだろう?」
「…本名…?」
04は訝しげに眉根を寄せた後、何かに気付いたように目を少し見開き、
「…そうか、本名か…」
それから首を左右に振った。
「…済まないな。伝えるのが礼儀なのだろうが…。私達には、名が無いのだ」
「…へ?」
予想もしていなかった答えに、俺は間抜けな声を漏らした。04は微苦笑しながら続ける。
「私達は、物心がついた頃には相麻の研究所に居た。固有の名前などは無く、それに代わるものとして、アルファベッドと数
字からなる験体コードで呼ばれている。この04という識別名称も、二年ほど前に与えられた、威力捜索員としてのコードナ
ンバーに過ぎない」
…名前が…、無い…?
俺はその事がなかなか受け入れられず、馬鹿みたいに口を開けたまま、04の顔を見つめていた。
…名前が無い…。俺も、これまでは名前なんてただの呼び方のような認識しか持っていなかったが、なんだか寂しい気持ち
になった。
俺達には普通、名前がある。
親とか、親類とか、普通は名前を与えてくれる誰かが居るから、物心がついた時には自分の名前を持ってるはずだ。
なのに彼女達は、名前を与えてくれる者も居なければ、名前の必要性を問われる環境にもなかった。
なんとも寂しく、そして哀しかった…。
「もっとも、私はもう04ですらない。私が抜けた後に、新たに04のコードナンバーで呼ばれる者が、その内に補充される
だろうからな」
彼女の言葉に、俺はぼんやりとその様子を想像した。
機械の、欠けた歯車やパーツが交換されるように、彼女の後釜に別人が、また04と呼ばれる存在として補充される様子を…。
便宜上での呼び名すら失った彼女は、不思議そうに俺の顔を見つめた。
「どうかしたのか…?」
「あ…、いや…」
名前を持たないっていうのは、どんな気分だ?
名前を呼んでくれるひとが誰も居ないというのは、どんな感じだ?
まだガキの俺には、想像もつかなかった…。ただただ寂しくて、哀しかった…。
「もう、休んだ方がいいよ。お休み…ゼ…」
ゼロヨンと呼びかけそうになって、俺は口を閉ざした。
…彼女を何て呼べばいいのか、俺には、判らなかった…。
「ああ。世話になる…。お休み…」
俺は頷き、ドアを閉じた。いたたまれない気分を、胸の真ん中に抱えたまま…。
「ビャクヤ…?」
「うん?ああ、ごめん…」
ビャクヤは灰皿にタバコを押し付けて消した。
「いや、タバコは良いんだ。まだ寝ないのか?」
「眠るよ。そろそろね」
ビャクヤは普段、小屋の中ではタバコを吸わない。
少なくとも、俺やカワムラが居る時には、小屋を出てテラスでタバコをくゆらせる。
たぶん…、外に出るのもおっくうな程、消耗しているんだろう…。
爆発の衝撃で破損した臓器の修復と、傷口を塞ぐ事を優先したらしいけれど、右目は潰れ、右手も手首から先を失ったままだ。
…そこまで修復するだけの余力が、今のビャクヤには残っていないんだ…。
完全とは言えない修復だけで、力を殆ど使い切ってしまったんだから、彼がどれほど深いダメージを受けたのかは想像に難
くない…。
そもそも、目や利き手よりも優先して治さなければならなかったのだから、「軽い損傷」と言っていた体内のダメージは、
本当はかなり深刻なものだったんだろう…。
「ゆっくり休んで傷を癒してくれ。ビャクヤがこんなんなったなんて知られたら、カワムラに何されるか…」
「あはは!それは想像もしたくぅっ!?…な、ないねえ…」
笑い声を上げ、痛みに顔を顰めたビャクヤを見ながら、俺はふと気が付いた。
…さっきビャクヤは04に、男が使ってないベッドを貸すと言った。つまりカワムラのベッドだ。
てっきり、俺がベッドを使っている時は、ビャクヤはそっちで寝ているんだと思っていた。でも、違っていたらしい。
…ビャクヤは俺が泊まる時、いつも何処で寝ていたんだ?その事を尋ねてみると、
「うん?このまま椅子で寝るけど?」
ビャクヤは「何故そんな事を聞くのか?」というように、不思議そうに首を傾げた。
「駄目だ!元々ビャクヤのベッドなんだし、ビャクヤの方が重傷なんだぞ?」
「いや、慣れてるから平気だよ」
って、慣れっこになるまでベッドを譲り続けるなってば!
それに、慣れるとは言っても、ここの椅子は全て、ビャクヤ手作りの背もたれつきウッドチェアーだ。
並べて寝そべるとしても、ソファーなんかで寝るのとは訳が違うし、何よりも、人一倍でかいビャクヤがそれで伸び伸び休
めるはずなんかない。
「俺の事は良いからベッドで寝てくれ。俺が椅子で寝るから…」
「それじゃあケイコさんにも申し訳が立たない。それに僕の方が年長なんだ。君が我慢する事は…」
「年長だからこそ体を労って、ベッドで寝るべきだろう?」
「…いや…、さすがにそこまで歳じゃないんだけどな…」
問答すること約30分。
結局、俺達は一緒のベッドで寝る事で妥協した。
「ごめんね?僕、太ってるから…、狭いんじゃない…?」
ビャクヤは、自分のベッドだっていうのに、申し訳無さそうにぼそぼそっと呟いた。
「平気だよ。それに「ごめん」を言うのは俺の方だ。ベッドも小屋も、オーナーはビャクヤなんだから」
…とは言っても、やっぱりちょっと窮屈ではあったけど…。
俺とビャクヤは背中合わせでベッドに横になり、彼女を起こさないように気をつけて、ぼそぼそと言葉を交わす。
「04…。名前が無いんだってさ…」
「…うん…?」
「04も、他の連中のも、本当の名前じゃなくて、役割に応じた番号みたいなものなんだって…。任務で番号を割り振られる
だけで、個人の名前は無いんだってさ…」
「…そうなんだ…」
ビャクヤが頷いたのが、温かでふかふかな背中越しに判った。
「起きたら…、まずは彼女に、自分の名前を考えて貰おうか…」
「…ああ…」
ビャクヤの提案に、俺は頷いた。
明日から04は…、何て名乗る事になるんだろう…?
傍に居るだけで安心できる、ビャクヤの温もりを背中で感じつつ、俺はそんな事を考えながら、眠りの中へ落ちていった…。
目覚めた俺達が朝食の支度を終えた時の事だ、リビングにその女性が入ってきたのは。
「…済まない。目覚めが遅くなってしまった…」
ぶかぶかのトレーナーと綿パンを身に付けた女性は、そう言いながらぺこりと頭を下げ、俺は面食らって口をパクパクさせた。
「やあ、おはよう。良く眠れたかい?」
すっかり外傷の治癒が終わったビャクヤは、にこにこと笑いながら女性に話しかけた。
手首から欠損していた右手ももう生えているし、全身の毛もいつものように真っ白でフサフサ、右目ももちろん元通りだ。
一体何着同じ服を持っているのか、ボロボロになったオーバーオールやシャツも、別の物に替えてある。
「恥ずかしながら…、厄介になっている身の上で、一番最後に目を覚ますほどにな」
女性は笑みを返すと、口をぽかんと開けている俺に視線を移した。
「どうしたのだ?少年」
咄嗟に言葉が出なかった。
元04の正体は、以前この山の麓で会って、一緒に夕陽を眺めた、あの女性だった…。
「…失敗したかな…?」
野菜スープを担当した俺は、スープをスプーンで一口含んだきり、完全に静止した女性を見ながら頭を掻いた。
「そうかな?そんな事は無いと思うけど…」
スープを啜ったビャクヤが呟く。
「い、いや…。美味い…。…うん…。こんな味は初めてだ…」
女性は少し驚いているような表情で、何度も頷きながら、せわしなくスープを口元に運ぶ。
…何の変哲もない、普通のコンソメ野菜スープなんだけれど…。
聞いてみると、相麻の中で彼女達に与えられていた食事は、栄養剤やカロリークッキー、ミネラルスープなど、完全に制限
されていたらしい。
「それらの味は、どんな感じなんだい?」
ビャクヤの問いに、彼女は難しい表情で黙り込み、それからフォークで刺した塩茹でのジャガイモを持ち上げて見せた。
「カロリークッキーの味は、この料理から塩分を除いたものに似ている。…と、思う…」
…つまり、ただ茹でただけの味付けしないジャガイモっぽい味なのか?
「…こんな味のものを食べたのは、初めてだ…」
感動すらしているように言った彼女の顔を眺めながら、つくづく、相麻内では人間扱いされていなかったんだなと、俺は少
し寂しく感じていた…。
「さて、色々と話をしたい所だけれど…」
朝食後、ビャクヤはそう話を切り出すと、女性の顔を見つめて苦笑した。
「その前に、君の名前を決めて貰わないとね?」
「…私の…、名前?」
「ああ。もう04じゃないわけだろ?何て呼べば良いかな?」
俺も同意を示すと、女性は首を傾げた。
「名前か…」
彼女は少し俯いて眉根を寄せ、悩んでいるように腕組みをして黙り込む。
たっぷり五分ほど考え込んだ後、彼女は「うむ!」と、一つ大きく頷いた。
決まったのかな?俺とビャクヤは少し身を乗り出し、顔を上げた彼女を見つめた。
「駄目だ。全く思いつかない」
女性はそうきっぱり言って、俺とビャクヤを机につっぷさせた。
「す、好きなように名乗って良いんだよ?」
「好きなようにと言われてもな…」
少し引き攣った笑顔で言ったビャクヤに、彼女は困ったように応じた。
「…そうだ…」
女性はまた大きく頷くと、俺とビャクヤの顔を交互に見た。
「君達の好きなように呼んでくれないか?私はそれを名前にしよう」
…それこそ、好きなようにって言われてもな…。
俺とビャクヤは困惑しつつ、顔を見合わせた…。
結局、俺とビャクヤは散々首を捻った後、ゼロヨンの4を取り、とりあえずは彼女をフォウと呼ぶことにした…。
「フォウ…、フォウか…。うん。なかなか良い響きだな。気に入ったよ、ありがとう」
フォウはうんうんと頷くと、俺達に微笑を向けた。
…尻尾が勝手に、はたはたと左右に動く…。
「それでフォウ…」
何か言いかけたビャクヤの言葉は、急に開いたドアの音で中断された。
「おはようビャクヤ。…ついでにイミナ」
大きなザックを背負ったカワムラが、開いたドアの向こうに立っていた。
あ、そうか、今日は学校が休みだからカワムラも来るんだな。…って、俺はついでか…。
…それにしても、まだ朝の8時だぞ?何時に家を出て来たんだ?
小屋に足を踏み入れ、室内の様子を見回したカワムラの視線が、ピタッとフォウに止まった。
「……………」
…何だ…?この重苦しい沈黙…?
カワムラの周囲の空気が、何故か陽炎のように揺らめいて見えた。
…ライカンスロープの瞳が捉える、視覚化された危機的気配…。つまり…、これは…、闘気…?…い、いや、怒気…!?
「…ビャクヤ…」
「…う、うん?」
ビャクヤもカワムラのそれを感じ取っているんだろう。少し仰け反って体を引いている…。
「…そのひとは誰?」
「え、えぇとね…。彼女はその…、フォウといって…、えぇと、何て言うか…」
やましい事など無いのだから堂々としていれば良いものを、ビャクヤはカワムラが発散する濃密な怒りの気配に圧倒された
ように、しどろもどろになって説明する。
「…ビャクヤの…」
カワムラは拳を握り込み、俯いた後、
「浮気者ぉぉぉぉぉおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおっ!!!」
窓ガラスがビリビリ震えるほどの叫び声を上げ、身を翻して小屋から飛び出して行った。
「あっ!ちょ、ちょっとアサヒちゃん!?ま、待って!誤解だ!誤解なんだっ!」
慌てて立ち上がったビャクヤは、椅子やらテーブルやらにぶつかりながら、小屋からまろび出てカワムラの後を追っていった。
さながらその様子は、泣きながら走り去る恋人を追いかける男子学生。…ああいうの学校で何回か見たな…。
…まぁ、単純な誤解だし、二人ともしばらくしたら帰って来るだろう…。
俺は席を立ち、ビャクヤがひっくり返した椅子を立て直す。
そして、開けっ放しのドアから二人が走り去った方向を、途方に暮れたように眺めていたフォウに声をかけた。
「すぐに戻ってくるから、心配要らないよ。…そうだ、紅茶でもどうかな?」
フォウは俺を振り返り、一瞬戸惑ったような表情を浮かべた後、微笑して頷いた。
「ありがとう。いただくとしよう」
その笑みを見たとたん、また尻尾が勝手にパタパタと動き出すのを、俺は止める事ができなかった…。