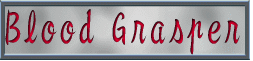
FILE2
明かりも無い山の中を、時折休みながらも、もう一時間ほども走っただろうか?
獣道としか思えない草木の間の道を、カワムラは息を切らせながら駆け上って行く。
迷いの無い足取りは、なんだかこの道を登り慣れているようにも感じられた。
奇妙な事に、明かりの一つも無い夜の山道だというのに、俺の目は驚くほど良く見えた。
しかも、前を行くカワムラはしばらく前から息が上がっているのに、俺は全く疲労を感じていない。これも、麻酔と一緒に
注射された薬のせいなんだろうか?
何度目かの休憩の後、カワムラは山の上を見上げて呟いた。
「あと…、三十分も、走れば…、着くわ…!」
息を整えながら言った後、カワムラは俺を振り返り、そして顔付きを険しくした。
「…マズったわね…!つけられた…!」
振り返ると、まだかなり下の方だが、闇の中で揺れる光が見えた。
…ライトの光?さっきのヤツの仲間か!?
まだ離れているので直接姿を照らされる事はないが、光はこちらを向いたまま、真っ直ぐに近付いて来ているように思えた。
恐らく、あっちからは俺達の姿が見えているんだ…!
「急ぐわよ!」
カワムラは俺の腕を掴み、ぐいっと引っ張った。そして上を目指してまた走り始める。
だが、カワムラはもう息が上がってかなり苦しそうだ。このままじゃ追いつかれてしまう…!
カワムラは五分ほど走った後、距離を縮めている光を振り返り、悔しげに顔を歪ませてから、すぅっと大きく息を吸い込む。
「助けてぇーっ!!!」
カワムラが叫ぶ。
落ち着いてるように見えていたけれど、本当は怖くて仕方ないんだろう。…叫んだところで、こんな山奥じゃ助けなんて来
るはずがない…。
声なんか上げたら位置がばれる。とか思ったが、向こうはとっくに俺達に気付いているんだ。今更叫び声なんて関係ないか…。
…カワムラだけでも逃がせないだろうか?
俺の体は今、物凄く力が強くなっているし、走ればスピードもかなり出る。
俺が引き返して、追いかけてくる奴らを引き付ければ、カワムラが逃げるだけの時間を稼げるかもしれない。
例え捕まったとしても、俺さえ捕まえれば満足して、カワムラには手出ししないで引き上げてくれるんじゃないだろうか?
元はといえばカワムラは巻き込まれただけで、無関係なんだ。俺がなんとかしなきゃ…。
それに、上手くすれば、カワムラを逃がす時間を稼いで、俺自身も一人だけなら逃げられるかもしれない。
…道が判らないのが不安要素だが、このまま捕まるよりはいくらかでもマシだろう?
「カワムラ!このまま真っ直ぐ走って逃げろ!俺、時間稼ぎしてみる!」
俺はカワムラにそう告げた。
「え?ちょ、ちょっとイミナ!?」
「止まるな!走れ!」
抗議するような口調で言ったカワムラの手を振り払い、彼女の背を強く押してそのまま走らせる。
そして俺は彼女に背を向けて立ち止まり、追っ手の方へ向き直った。
激しく揺れていたライトの灯りが落ち着き、相手が俺の姿をはっきりと認めた事を知る。
近付いたライトが、俺の顔に向けられた。
「…人狼…!?」
「人狼だぞ、こいつ?」
「06がやられる訳だ…」
「気を抜くなよ!」
四人か?眩しい光で姿を確認できないが、その声から警戒している事が解る。
俺は足を踏ん張り、いつでも動けるように身構える。バスケで鍛えた瞬発力には自信がある。木を盾にして動き回れば、上
手くやれば逃げられるはず…。
立ち回る方法を吟味していると、唐突にライトが消えた。…何故?俺は追っ手の意図が解らずに混乱する。
俺の目は、薬の効果なのか良く見える。でも、あっちには…、
光が消え、しだいに暗さになれて調節された俺の目が、四人の影を捉えた。ふくれ、ひしゃげ、変形する四つの影を…。
…しまった!相手も薬を持ってる。つまり、俺やさっきの黒猫みたいな姿に変身できるんだ!
四つの影は、それぞれ犬、馬、猪、熊の顔を俺に向けた。…そんな…!?この体と同じような体力の四人を相手に、俺一人
に何ができるだろう…!?
「…おい、こいつ、震えてるぞ?」
一人、猪顔が呟いて気が付いた。俺は、カタカタと震えていた。
「覚醒したてなんじゃないのか?」
「なるほど、素人だったか…」
「なら例え人狼でも、何とでもなるな…」
四頭の獣はゆっくりと間合いを詰めてくる。
体が強張る。…怖い…!怖くて仕方がない…!
歯がカチカチ鳴りそうになるのを、口を閉じて必死に堪え、俺はカワムラが無事に逃げ切る事を祈りながら、四頭につっか
かる覚悟を決めた。
「う、うわぁぁぁぁぁっ!!!」
声を上げて地面を蹴り、俺は一番小柄に見えた犬につっかかる。が、掴みかかる寸前に、横合いから猪に体当たりされ、真
横に吹き飛んだ。
濡れそぼった斜面を転がった後、なんとか身を起こそうとした俺は、脇腹に激痛を覚えて呻いた。
見れば、猪の牙が刺さったのか、脇腹に親指が入りそうな穴が二つ開いている。
立ち上がろうとしたが、上手く行かない。どうにか膝立ちになった俺の目の前で、どしっと、太い足が地面を踏み締めた。
見上げた俺と、見下ろす熊の目があう。次の瞬間、振り下ろされた太い腕が、俺の後頭部を打ち据えた。
顎から地面に叩きつけられた俺の背を、熊の足が踏み付けた。
「げうっ!」
あばらがミシミシと音をたて、内臓が圧迫されて息ができない。背中に足の爪が食い込み、皮膚を貫いて潜り込んで来る。
逃げるどころか、痛みに耐えるのが精一杯だ。
動けない俺の前に、すっと犬が立った。そして俺の頭を踏み付ける。
「さんざん逃げ回ってくれたが、結果はあっけなかったな…。てこずらせやがって…。おい08、女が居たはずだ。探して始
末してこいよ」
「ああ」
馬が頷いて応じるのが、動かせない視界の隅に見えた。
「かっ!かわっむ…ら…!逃げ…ろ…!」
叫ぼうとしたが、喉から漏れるのは掠れた声だけだった。
犬は冷ややかな目で俺を見下ろし、俺の頭を踏み付けている足に体重をかける。
「んぐぅっ…!」
「黙ってろ。せっかくの人狼なんだ、なるべく生きたまま捕獲したいのさ。お前だって死にたくはないだろう?ん?」
08と呼ばれた馬は、一瞬身を屈めると、凄まじいスピードで斜面の上へと駆け上って行く。
そ、そんなっ…!カワムラ!逃げてくれっ!
「あっ!」
遠く、斜面の上から、カワムラの声が聞こえた。
何故かその声は、嬉しそうな、そして安心したような響きを伴っているように聞こえた。
「ぎゃっ!」
間を置かずに悲鳴が聞こえた。そして、何かが斜面の上から物凄い勢いで吹き飛んで来ると、太い木の一本に叩き付けられ、
ドサッと地面に落ちた。
それは、さっき上に向かって走っていった馬だった。気絶しているのか、ピクピク痙攣しているが、起き上がる気配は無い。
何だ?何が起こってるんだ…!?
猪が斜面の上を見上げ、ブルルルッ!と唸った。犬も同じ方向を見ている。俺からは見えないけれど、恐らくオレを押さえ
込んでいる熊も、同じく斜面の上を見ているのだろう。
斜面の上から、青くて黄色くて白い何かが、のっしのっしと降りてきた。目に入った雨を瞬きして追い出した俺は、そいつ
の姿をはっきりと確認する。
オーバーオールに、黄色い半袖ティーシャツ。袖から覗く太い腕は白くて長い毛に覆われている。
そいつの顔は、俺や、四頭の獣達のように、人間の顔をしていなかった。
犬だ。ふさふさの長い髪の毛みたいな毛に覆われた、耳の垂れた犬の頭…。
顔の前に落ちかかる前髪の下から、煌く黒い瞳がこっちを見つめていた。
折って捲り上げられたオーバーオールの裾から覗く足は、今の俺と同じ、獣の足だ。踝から足の甲、つま先が長い犬の足…。
ただし、俺の足よりも太く、そして大きい。
それにしてもでかい…。丸太のように太い手足にがっしりした胴体、上背は2メートルを大きく越えているだろう。まるで
動物園で見た白熊のような巨体だ…。
俺と目が合うと、そいつは右の眉を上げ、口の左端を微かに吊り上げていた。なんだか、少し驚いているような、同時に面
白がっているような、そんな奇妙な表情だった。
「お客さんとは珍しいねぇ。それも人狼だなんて…」
「何だ、お前…?」
犬が唸り声を上げて威嚇するが、白い巨犬は涼しい顔で、軽く肩を竦めて応じる。
「ま、僕が誰なのかは大して重要じゃないさ。とりあえず、そこの彼を放してあげてくれないかな?どうも友人の知り合いら
しいんでね」
白犬は落ち着いた、穏やかなバリトンボイスでそう言うと、それから思い出したように付け足した。
「あぁそれと…、悪いけれど、君達の記憶は消させて貰うよ?僕、世捨て人なんてしてるから、なるべく居場所を知られたく
ないんだ」
獣達はぽかんとした様子で顔を見合わせた。…いや、俺も今は獣の格好だけど…。
「ふざけているのか?」
猪が低い、恫喝するような声で言うが、
「いやあ、至って大真面目なんだけどね?僕にとっては死活問題」
白犬はどこか困った様子で頬を掻いた。
「舐めおって…!」
猪が白犬めがけて突進した。ずんぐりした体の割にかなり速い!
だが、猪と白犬の距離が2メートル程度まで縮んだその時、フッと白犬の姿が消えた。そしていつの間にか、猪の目の前に、
腰を落とした状態で現れている。
「ごめんね?」
白犬の呟きに続いて、ズドン!と、物凄い音がした。何と言うか、砂袋が地面に落ちたような音、アレを何倍にもしたよう
な音だった。
猪の体が、腹を支点に「く」の字になっている。いや、下から突き上げられているので「へ」の字と言うべきか?白犬が下
から突き上げた拳が、猪の鳩尾を捉え、腕一本でその体を空中へ打ち上げた。
「なっ!?」
絶句した犬が目を見開く。その視線の先で、落下してきた猪を腕一本で軽々と受け止め、白い獣は笑みを浮かべる。
この場と状況にはそぐわない、穏やかと言って良い微笑だった。
「き、貴様何者だ!?」
「…だから身元を知られると困るんだってば…」
犬の誰何の声に、白い獣は困ったような顔をしながら猪を優しく地面に下ろす。…って、殺したわけじゃないのか?気絶さ
せただけ?
「07!行け!」
犬の声に応じ、俺を押さえ付けていた熊がのっそりと前に出た。そして身を屈めると、白犬に飛び掛る。
両者の体格は同じくらいだ。鋭い爪を備えた熊の腕が、白犬に向かって振り下ろされる。
その時、また白犬の姿が消えた。振り下ろされた熊の腕が、弾かれたように真上に跳ね上がり、その脇に白犬が出現する。
ドスッという打撃音。腹に左拳を突き込まれた熊は、水平に10メートル近くも吹き飛び、太い木に叩き付けられた。
俺は、今更になって理解した。
白犬が消えているんじゃない。俺の目が犬の動きについて行かないんだ。
あまりに動きが速過ぎて、止まったり、減速した時にしか見えない。だから動いた途端に見失い、動き終えた後の姿しか確
認できていないんだ。
「くっ…!」
仲間を全部倒された犬は、じりっと後ずさると、こちらに背を向けた。
「悪いけれど、そのまま帰られると困るんだ」
振り向いた犬の目の前に、白い獣が立っていた。一瞬前まで、俺の視線の先に居たのに…。
ガスッ、という惨い音。拳骨を頭に落とされた犬は、崩れるように地面に突っ伏した。
白犬は周囲を見回し、全員気を失ったままなのを確認すると、口元に手を当てて声を上げた。
「アサヒちゃん!もう出て来て良いよ!」
白犬の声が響き渡ると、斜面の上のほうからバシャバシャと足音が聞こえてきた。
やがて、びしょ濡れの雨がっぱを着たカワムラが姿を見せる。
カワムラは白犬に駆け寄ると、太い胴に腕を回し、ガバッと抱きついた。
「ごめん…。秘密だって言われてたけど、他に方法が思いつかなくて…」
カワムラは申し訳無さそうに、白犬に抱き付いたままその顔を見上げる。
「仕方ないよ。それより、無事で本当に良かった…」
白犬は穏やかに微笑みながらカワムラの頭を撫でると、倒れたままの俺に視線を向けた。
「そこの君も、…まあ…、無事って言っていいのかな…?まだ立てそうにないかい?」
立ち上がろうとした俺は、かくんと膝が折れて、無様に四つんばいになる。
「無理しなくて良いよ。まだ傷が開いたままだ。高速修復はできそうかい?」
「高速…、修復…?」
脇腹を押さえながら聞き返すと、白犬は不思議そうに首を傾げた。
「もしかして、まだあまり力の使い方を知らないのかな?」
「力…?何の話だ…?」
白犬は目を細めて俺を見つめた。
「君は…、覚醒したてなのかい?」
「覚醒…?」
何を言われているのか、まったくちんぷんかんぷんだった。白犬は混乱している俺に優しく微笑みかける。
「話は後にしようか。まずは彼らを何とかしないと…」
白犬は倒れている獣達を見回し、まず木の所で折り重なっている馬と熊に近付いた。そしてその手を馬の頭に乗せ、目を細
める。
数秒間そのままで静止した後、
「否定する…」
ぼそっと、そう呟いた。
同時に馬の頭ががくんと揺れ、その周囲でぱちっと、蒼い光が瞬いた。静電気か何かだろうか?
白犬は熊にも同じ事をすると、次いで猪に歩み寄って同じ事を繰り返す。
最後に犬の元に歩み寄ると、意識を取り戻したのか、やつは低く呻いて顔を上げた。
「き、貴様…、何者…!?」
「気にしなくていいよ。これから忘れる事だから」
白犬はそう言うと、なんとか身を起こそうとしている犬の前で屈み込み、その頭に手を置いた。
「ひっ…!」
怯えた声を上げる犬の前で、白犬はまた呟いた。
「否定する」
パチッと、また光が瞬き、犬はガクンと力を失い、地面に突っ伏した。
「さてと…、これで全員かな?」
白犬は立ち上がり、獣達が動かないことを確認する。
「麓にもう一人居るわ。重傷だけど、どうなったかしら?」
「重傷?」
カワムラが言い、白犬が首を傾げる。
「そこの彼がやったの。正当防衛らしいわよ」
白犬は跪いている俺に視線を向けると、小さく頷いた。
「一度麓に下りなくてはいけないね。きちんと後始末をしておかないと」
白犬はそう呟いて傍に歩みより、俺の前で背中を向けてしゃがんだ。
「おぶるよ。歩くのは辛いだろう?」
この白犬が何者なのか、まだ判らない。確かに助けてくれたし、カワムラの知り合いのようだが…、信用して良いのか?
俺が視線を向けると、カワムラは頷いた。
「大丈夫よ。彼は私達の味方」
俺は、カワムラの言葉を信用する事にした。
「迷惑をかけます…」
そう断って、白犬の背におぶさる。腹の傷が彼の服を汚してしまう事に気付いたが、後の祭りだった。
「あ!す、済みません!服が汚れて…」
「気にしなくていいよ。どうせビショビショだし、洗わなくちゃいけないからね」
白犬は笑いながらそう言い、俺を背負ったまま立ち上がる。
「アサヒちゃんは先に小屋に行っておいて。僕は彼と一緒に、一度麓に行って来るから」
「こいつらはどうするの?」
カワムラは獣達に視線を向ける。
「二、三時間は目覚めないだろうから、そのままで大丈夫。後で麓近くまで下ろしておこう」
頷いたカワムラは、白犬に手を振った。
「それじゃあ、先にお邪魔してるわね」
「うん。三十分程度で戻るよ」
カワムラが歩き去るのを見送ると、白犬は思い出したように「あ」と声を漏らした。
「そういえば、まだ名前も言っていなかったね…」
白犬は視線を巡らせ、彼の肩に顎を乗せている俺に、至近距離から微笑みかけた。
「僕はビャクヤ。字伏白夜(あざふせびゃくや)って言うんだ」
「あ、俺、忌名夜彦です…」
「それじゃあヨルヒコ君、少し揺れるから、しっかり捕まっていてね?」
「え?」
俺が聞き返すが早いか、アザフセビャクヤと名乗った白犬は、物凄いスピードで走り出した。
「わ、わ、わ、わああぁぁぁぁぁぁぁっ!?」
辺りの木々が高速で後ろへ流れて行く中、悲鳴を上げる俺を背負ったまま、白犬はクスリと笑いつつ、猛スピードで山を駆
け下りて行った。
アザフセビャクヤは、オレをおぶったまま物凄いスピードで斜面を駆け下った。
生い茂る常緑樹を避け、飛ぶようにぐんぐん下っていく。
俺達に当たった雨粒が霧になって弾け、耳元で風がビョウビョウと唸る。まるで絶叫マシーンさながら…、いやそれ以上。
「はい到着〜!」
白犬の言葉に顔を上げると、少し先で木々が途切れ、雨に濡れたアスファルトが見えた。白犬は最後に一度大きく跳ね、ア
スファルトの上に太い足を踏ん張って着地する。
数メートル滑って静止すると、ため息をついて脱力した俺の顔を横目で一瞥し、面白そうに眉を上げる。
…無茶苦茶スリルがあった…。これからは並の絶叫マシーンに乗ったくらいではビクともしないな…。
カワムラと一緒に一時間以上もかけて登った山道を、結局、白犬は十分足らずで麓まで駆け下りて見せたのだ…。
男達が乗ってきた車だろう。ライトバンの中に、寝袋のようなチャックつきの袋に包まれ、黒猫が横たわっていた。
匂いで彼を見つけた白犬は、袋ごと車から引っ張り出し、ジッパーを大きく開け放って、その顔を見下ろした。
恐怖に見開かれた目が、俺と白犬の顔を交互に見る。
俺は、この時点で異常に気付いた。冷静さを失っていたからだろう、普通ならもっと早く気付くはずだった。
…この黒猫は、息をしていない…。
それなのに、目は動いているし、声は出ないけれど、口元は微かに動く。
生きているのか?死んでいるのか?黒猫の異様な状態に、俺は恐怖を覚えた。
「…カース・オブ・ウルブス…」
白犬がポツリと呟き、俺は傍らの彼の顔を見上げる。
「人狼だけが持つ縛鎖の呪いの事さ。力の流れを阻害し、魂ですらも縛り付ける…。彼はそれに縛られ、死ぬことができない
でいるんだ」
言っている事の一部しか理解できなかった。
白犬は黒猫の脇に屈み込み、その瞳を覗き込む。
「死にたいかい…?」
黒猫は、目で頷いた。懇願するようなその目の光が、憐れでならなかった…。
「いくつか質問に答えてくれれば、苦しまないように逝かせてあげるよ。…君達は何者だい?同族にしては希薄な匂いだ…。
普通のライカンスロープではないね?」
白犬の問いに、黒猫は目で頷いた。
「…因子の人為的な移植…、強制的な覚醒…、なるほど…、いわゆる人造の…、という事は…、そうか、君達、元々は…、…
そう…、相麻…、やっぱり…」
白犬はボソボソと、黒猫と言葉を交わす。いや、喋っているのは白犬だけだ。黒猫は口を動かすだけで、白犬がそこから彼
の言いたい事を読み取っているらしい。
「解った。もう良いよ…」
二、三分も経っただろうか、白犬は「会話」を打ち切り、黒猫の傍で屈んだまま、俺の顔を見上げた。
「僕が呪いを否定してもいいけど、ここは君がやるべきだね。彼を、自由にしてあげて」
「え?…自由って…?」
白犬は俺の手を掴むと、黒猫の頭側に屈ませた。
「彼に触れて、魂を縛っている力を解除するんだ」
「意味が…、解らないんだが…」
戸惑う俺に、白犬は優しく微笑んだ。
「難しく考えなくて良いんだ。君が彼を赦してあげる。それだけで良い」
俺は戸惑いながら、黒猫の肩にそっと触れた。赦しを請うような、怯えたその目が、憐れだった…。
襲われた事も、傷つけられた事も、今は赦せる。もう憎しみは感じなかった。
「あ…」
俺は、小さく声を漏らした。黒猫の体から、今、目では見えない何かが、スッと抜けていったような気がしたから。
黒猫はほっとしたような顔をして、目を半眼にすると、そのまま、二度と動かなくなった。
「お疲れ様。さあ、後の始末は…、あ、ちょっと?ヨルヒコ君?」
力が抜けてべしゃっと横に倒れた俺は、白犬の声をどこか遠くで聞きながら、意識が遠のいてゆくのを感じていた。