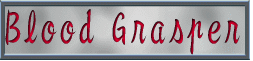
FILE20
忠告を無視して襲いかかってきた二体、猫と蜥蜴のライカンスロープは、ビャクヤが無造作に左右に打ち払った拳で、同時
に頭を粉々に破砕された。
頭部が爆ぜるように砕け、二頭の体は、飛びかかった勢いそのままにビャクヤの両脇をすり抜け、後ろを歩む俺とフォウの
両脇に倒れ込んだ。
力を使い果たしてろくに動けない俺は、足を引きずり、フォウの肩を借りて歩きながら、俺達の前に道を切り開いてゆくビャ
クヤの背を見つめる。
今夜、自分に架した不殺の誓いを解いているビャクヤは、その圧倒的な力を遺憾なく見せつけた。
振るう拳や繰り出す蹴りの一撃で、確実に敵対者に死を贈り、すでに十四頭の傭兵を排除している。
俺の義兄は、俺が思っていたよりもずっと強かった。
いや、正直に言えば、俺達とは次元が違い過ぎて、本当はどれだけ強いのか全く解らない。
結構強くなった気になって、ビャクヤの力もある程度は把握したつもりになっていたんだけど…、自信を無くすなぁ…。
それだけの力を持ちながら、普段のビャクヤは優しく、穏やかだ。
…きっと、心が強いからこそ、力に溺れる事がないんだろう…。
「ようやく着いたね…」
ビャクヤは足を止め、俺達が侵入に利用したエレベーターの前で呟いた。
「さて、上に着いたら正面突破だ。ヨルヒコ、具合はどうだい?」
体中が痛くてガタガタだったけど、俺はフォウに礼を言って離れ、自分の足で床を踏み締めた。
下らない痩せ我慢だけど、この偉大な義兄に、これ以上無様な格好は見せたくなかったんだ。
「右腕はまだ生えてこないし、ちょっとばかりガタも来てるけど、もう少し行けるさ」
俺が張った虚勢は、きっと見透かされていただろう。
それでもビャクヤは、俺を見つめて微笑み、ゆっくりと頷いた。
少し嬉しそうに、そして満足そうに…。
「なら行こう。03達が待ってるし、爆破まで時間もない」
そう言ったビャクヤは、エレベーターに向き直って、ボタンを押しながら続けた。
「この戦いは、僕達から相麻への宣戦布告でもある。だから最後は威風堂々、正面目指して一気駆け、敵を蹴散らして脱出す
る。逃げる者は追わない。そいつらが、僕らの事を上に報告してくれるからね」
猛るでもなく、意気込むでもなく、何でもない事のように、普段と変わらない様子で言ったビャクヤの背を、俺とフォウは
誇らしい気持ちで見つめる。
「…今夜ばかりは、道は僕が切り開こう…。離れて進む餞に…」
独り言のように呟いたビャクヤの声は、少しだけ、寂しそうだった…。
「これで全員かい?」
「はい!揃ってますよ!犠牲はゼロ、重傷を負ってる者は居ません!」
自由になった被害者や仲間達を率いて、俺達と合流を果たした03は、ビャクヤの問いに鼻息も荒く頷いた。
ビャクヤはエレベーター前の通路にひしめく全員の顔を、ゆっくりと見回した。
「さて…、皆疲れていると思うけれど、一息入れる前にもう一踏ん張り、最後の仕事が残ってるよ」
ビャクヤは口の端を吊り上げ、前髪の奥の目を細めて、ニヤリと笑った。
「相麻の鼻をあかしてやろう!堂々と胸を張って、正面突破だ!」
拳を振り上げた白い巨犬に応じ、俺達は大きく鬨の声を上げた。
この夜、この町の相麻製薬の工場で起こった爆発は、新聞の記事では化学薬品類の反応が原因で出火し、施設内の燃料貯蔵
庫に引火、爆発した「事故」であると報じられた。
これは相麻側がマスコミに伝えた公式発表だ。
実際にはビャクヤが動力室に細工して、小麦粉を使った粉塵爆発と、撒いた燃料の気化爆発で、地下から地上まで完全に破
壊してのけたんだけど、相麻側も事が明るみに出る事を恐れて、自ら隠蔽工作を行ったらしい。
もっとも、俺がこの事件の報道を携帯でチェックしたのは、夜が明けて昼近くになってから。
仙台港発の真新しいフェリーに乗り、お台場に向かう途中の事だったけどな…。
「それじゃあ、乾杯と行きたいところだけれど…」
脱落者なく山に帰りつき、小屋の前に集まった、相麻脱出組17名の顔ぶれを見回し、ビャクヤは困ったように眉を顰めた。
庭の中央には薪を組んで、キャンプファイヤーのような火が炊かれ、それをほとんど全員が囲んでいる。
「…ええと…。何に乾杯すればいいかな…?」
皆の手には、俺の母がビャクヤに渡した缶ビールやら、途中の自販機で手に入れたワンカップやらが握られている。
テラスの手すりにもたれ掛かり、オレンジジュースのビンを弄んでいた俺の横で、フォウが苦笑混じりに口を開いた。
「新たな仲間達と、手に入れた自由にでも乾杯するか?」
ビャクヤは首を巡らせ、こっちを見てニッと笑った。
「それが良いね。それじゃあ、仲間と、自由に、…乾杯!」
『乾杯!』
全員が唱和し、缶やビンが触れ合う音が庭に響き、次いで笑声と拍手が弾けた。
01と02、犬と豹のライカンスロープであるフォウの仲間達は、首に埋め込まれていた爆弾をビャクヤに取り除かれ、真
の自由を手に入れた。
投薬途中だった大半の皆も、投薬さえ中断してしまえば、副作用で命を落とすことは無いだろうとの話だ。
もっとも、半端なライカンスロープになってしまうのは、もう防ぎようが無いらしいけれど…。
とりあえず全員、命についてはひとまず安心だ。
「何のことはない。相麻が私達に投薬していた獣化因子活性剤とは、ライカンスロープの血液を元に造られた物だったそうだ。
ビャクヤが回収した資料に、製法も中和剤の製法も載っていたよ」
フォウは鮮やかな赤紫のカクテルが入ったビンを傾け、俺にそう説明してくれた。
「それじゃあ、中和剤が手に入れば、フォウも人間に戻れるのか?」
期待を込めて尋ねた俺に、フォウは肩を竦めて苦笑した。
「残念ながら無理だ。資料を確認したビャクヤから説明を受けた。私もまだ完全には理解していないし、少し専門的な話にな
るが、それで良ければ聞くか?」
ずっと山奥で暮らしてるくせに、何でビャクヤはそんな事に詳しいんだろう?
考えてもみれば、今夜使った爆弾もビャクヤお手製だ。…今更ながら、底が知れない…。
少し興味もあったし、俺は話を聞いてみる事にして、フォウに頷いた。
薄桃色の猫は、カクテルを少し含み、飲み込んでから口を開く。
「彼の話では、獣化因子活性剤は、人間の体内に入ると人間の因子と反応を起こし、毒性の強い酵素を発生するそうだ。この
酵素が人間の因子を侵食し、擬似獣化因子へと変質させ、人間の肉体に本来は無いはずのトランス機能を付加する訳だが…、
大丈夫か?」
「たぶん…」
心配そうにこっちを見たフォウに、俺はこめかみを押さえながら頷く。
「それで…、相麻が製法を確立した中和剤とはつまり、体内に残留するその酵素を中和するだけのものだ。拒絶反応を起こし
た被験者に投与すれば、活性剤の効果を打ち消し、発作によるショック症状を和らげる事ができるが、すでに生じた変化につ
いてはどうしようもない」
「…そうか…」
項垂れた俺を見て、フォウは優しく微笑んだ。
「そんな顔をしないでくれ。ライカンスロープの身体自体は、それほど嫌いではない。普通の人間より遙かに丈夫だし、何か
と便利だしな。…それに…」
フォウは恥ずかしげに目を伏せ、消え入りそうな声で囁いた。
「…この体のおかげで…、君と出会え…、共に…歩めるのだから…」
…俺は…。自分の耳を疑った。
フォウはそれきり黙ってしまい、俺は顔が熱くなるのを感じながら、激しく脈打つ心臓の音を数え、ジュースのビンを手で
弄んだ。
「…あ…」
傍らのフォウが空を見上げ、小さく声を漏らした。
つられて見上げると、澄んだ空気の中、満点の星空を、続けざまにいくつかの流れ星が横切って行った。
細く、速い、銀色の流星…。
ぼんやりと、天駆ける狼を連想していると、フォウの手が、俺の手をそっと握った。
その能力とは裏腹に、柔らかく、暖かいその手を、俺は少しばかり照れながら握り返す。
「危険を顧みずに助けに来てくれた事…、申し訳なかったが…、とても嬉しかった…。…ありがとう…。ヨルヒコ…」
「…う、うん…」
俺達は空を見上げながら、いつまでも、手を握っていた…。
それからしばらくすると、飲み物が足りなくなって、フォウが同僚の01と一緒に、コンビニへ行くために山を降りた。
同行を希望した俺は、
「ボロボロなのだから、休んでおけ」
と、やんわりと居残りを命じられた…。
…あ、あれぇ?さっきは結構良い雰囲気になってたはずなのに…。
手持ち無沙汰になって、小屋の横で壁によりかかってジュースを啜っていると、缶ビール片手に、ビャクヤが近付いてきた。
「やれやれ、やっと開放されたよ…。お疲れさんヨルヒコ」
「ビャクヤも」
俺が持ち上げたジュースのビンと、ビャクヤが突き出したビールの缶が、軽い音を立ててぶつかる。
「楽しそうだな、皆…」
キャンプファイヤーでもやってるように、大いに盛り上がってる皆の様子を眺めて、俺は呟く。
「自由を手に入れたんだからね…。大変なのはこれから先もしばらく続くけれど、今は楽しんでおかなくちゃ」
目を細めて応じたビャクヤは、じっと、俺の目を見つめた。
「ヨルヒコ。フォウから、少し聞いたよ…」
「ん?」
何の事か判らずに首を傾げた俺の手を、ビャクヤが掴む。
「ちょっとごめん…」
ビャクヤは右手の人差し指の爪を硬化させると、素早く俺の手の平をなぞる。
痛みは無かったけれど、肉球の表面に、数珠のように連なった血の球が浮いた。
「その血を、…そうだね、これにつけて」
白犬は足元から細い枯れ枝を拾い上げると、俺に差し出した。
…あ…。
「ビャクヤ!言い忘れてた!俺…」
血を見て思い出した。ミストの体を焦がした、黒い炎の事を…。
「試してみよう。この木の枝に…」
頷いた俺は、ビャクヤが差し出している枝を軽く握り、血をこすりつける。
ビャクヤはそれを、土がむき出しになっている箇所に置いた。
「たぶん…、体の中の血をコントロールするのと同じ要領で、意識を集中させれば良いはずだ…」
ビャクヤの言葉を聞きながら、俺は地面に置かれた枝を見つめ、念じる。
また、あの炎が現れた。
枯れ枝は音も無く燃える黒い炎に包まれ、パキパキと乾いた音を立てながら、細かく割れて行く…。
「…初めて…見た…」
呟いたビャクヤは、かなり驚いているようだった。
「君は、ブラッドグラスパーだったんだね…」
そういえば、ミストもそんな言葉を口にしていた?
「二ヶ月足らずで、ここまで肉体操作に熟達できた…。生粋の人狼の血と、才能のおかげだとばかり思っていたけれど…、納
得できた…。君は、何度も僕を驚かせてくれる…」
訳が分からず首を傾げている俺に、ビャクヤは微笑んだ。
「君はブラッドグラスパー。類稀な資質を持った、本当に希少なライカンスロープだったのさ」
「ブラッド…グラスパー…?」
「「血を掌握する者」。自分の体を離れた一部…、流れ出た血液を媒介にして、能力を発動させる事が出来るライカンスロー
プの事さ。君の場合はこの黒い炎、血を燃料にして燃える呪いの炎、という事らしい」
「…微妙だよな…?怪我をしないと使わない能力なんて…」
「そこが重要さ。下手に君を傷つければ、返り血を浴びて呪いに焼かれる…。一度経験すれば、ほとんどの相手は君を傷つけ
ようとはしないだろう」
ビャクヤは笑みを浮かべたまま目を閉じると、深く息を吐いた。
「この力はきっと助けになる…。離れる間際になって、君はまた少し強くなった。…なんだか、ちょっと安心したよ…」
目を開けると、周囲は静まりかえっていた。
盛り上がる宴会の喧噪から離れ、太い木に寄り掛かって身体を休めていたら、いつの間にか眠ってしまったらしい。
疲労が溜まっていたんだろう。身体には嘘はつけないな…。
小屋の前には地面にごろごろ転がって、寝息をたてているライカンスロープ達。
焚き火は消えていた。その横では、おそらく消火したんだろう03が、傍にバケツを転がしたまま、ひっくり返って豪快な
いびきをかいている。
周囲には空になったビールの缶や酒瓶が散乱し、まさに兵共が夢の跡と言った感じだ。
もうじき日の出なんだろう。空は薄明るく、山の空気は張り詰めてひやりとしている。
俺の銀の被毛も、傍らに置いていたザックも、朝露に濡れ始めていた。
「起きたのかい?」
突然の声に驚いて耳を立て、首を巡らせると、俺の左手側、同じ木に寄り掛かり、ビャクヤがウーロン茶の2リットルボト
ルをラッパ飲みしていた。
「はは。こんなの久しぶりだったから、ついつい飲み過ぎちゃった…」
白犬は、少し赤くなっている目を細めて苦笑いした。
「ビャクヤは酒も強いんだな?みんな潰れてるのに」
「お酒は弱い方が得だよ?少しで酔える方が良いし、飲めないならそれに越したことはないよ。タダじゃないんだから…」
頭が重いのか、眉間を指で揉みほぐしながら、ビャクヤはため息をついた。
なんだかケチ臭い事を言っているビャクヤを横目に、俺は苦笑を浮かべる。
「…そろそろ、お別れだね…ヨルヒコ…」
「…ああ…」
寂しさを押し殺したような、低いビャクヤの声に、俺は小さく頷いた。
「…何て礼を言ったらいいのか、判らない…。どうすればこの大きな借りが返せるのか…」
「気にしなくて良いんだよ…。弟の面倒を見るのは兄の義務で、同時に特権だ。…それに、こう言ったらなんだけれど、君の
世話をやくのは結構楽しかった」
そう、軽い調子で言ってくれたビャクヤに、俺はただ、項垂れて礼を言うことしかできなかった。
「…ありがとう…。ビャクヤ…」
「ははは。今生の別れって訳じゃないんだ。そんなしんみりしないでよ?また会えるんだからさ」
ビャクヤは笑いながら立ち上がる。俺も立ち上がろうとして…、
「いぎっ!?」
凄まじい筋肉痛に呻き、堪らず尻餅をつく。
踏ん張りすぎた後遺症は、なかなかしつこかった…。
ビャクヤは片方の眉と片方の口の端を上げ、驚いているような面白がっているような、あのお馴染みの表情を浮かべて、俺
に手を差し伸べた。
「最後もしまらないな…」
バツが悪い思いをしながら呟き、大きな手を掴んだ俺を、ビャクヤは軽々と引っ張り起こした。
俺はビャクヤの顔を見上げ、ビャクヤは俺の顔を見下ろす。
ビャクヤは穏やかに、でも少し寂しそうに微笑んでいた。
「…夜が明けるよヨルヒコ…。もう、行かないと…」
「…うん…」
ビャクヤに頷き、俺は木の根元に置いていたザックを担ぐ。
「…じゃあ…」
踵を返しかけた俺は…、
「…ビャクヤっ…!」
結局、想いを堪えきれず、義兄と仰ぐ男の胸に飛び込んでいた。
「楽しかった…!」
「僕もだよ…」
「ありがとう…!」
「僕こそ、ありがとうヨルヒコ…」
「元気で…!」
「君もね…」
流れる涙を拭いもせず、込み上げる嗚咽を押し殺し、震える声を漏らした俺を、ビャクヤは逞しい両手で優しく抱き締め返
してくれた。
今になってはっきり判った。
俺はきっと、ビャクヤを父と兄の中間のような存在として見ていたんだ。
強く優しいビャクヤの庇護を受け、深い安心を得ることができていたんだ。
心細さはもちろんある。
それでもここから先は、ビャクヤから離れて歩いて行かなきゃならない。
俺がいつまでも頼りないままじゃ、ビャクヤが安心できないんだ…。
柔らかくて温かいビャクヤから体を離し、俺は精一杯の空元気で、笑って見せた。
無理してるのは、きっとお見通しだったろう。
でもビャクヤは、ニッと笑い返してくれた。
疲れ果て、今は小屋のリビングで眠っているはずのフォウには、起きている内に別れを告げた。
03にも夜明け前に山を降りる事を告げている。
これで、ここに居る全員との別れが済んだ…。あとは…。
「それじゃあな。ビャクヤ」
「うん。気をつけてね、ヨルヒコ」
片手を上げて最後の挨拶をかわし、俺は踵を返した。
見送ってくれているビャクヤの視線を背中に感じながら、俺は一度も振り返らず、胸を張り、通い慣れた山道を降りてゆく。
ありがとう。
…そして、さようなら。ビャクヤ…。
人間の姿になり、山を降りた俺は、一箇所だけ寄り道してから、母の待つホテルへ向かった。
「おかえり、ヨルヒコ…」
「ただいま、母さん…!」
短い挨拶の後に軽く抱き合って再会を喜び、俺と母は駅まで歩いた。
長く暮らしたこの町に、お別れをしながら。
俺の愛車であるマウンテンバイクは、受け取って欲しいと記した手紙と一緒に、カワムラの家に置いてきた。
全然足りないだろうけど、ささやかなお礼のつもりだ。
遠ざかる山を、電車の窓から眺めながら、俺は心の中でもう一度、ビャクヤにさようならを告げた…。
「出航まであと40分ね」
母が時刻表を見ながら呟いた。
俺と母は今、仙台港で出航を待つ、真新しいピカピカのフェリーに乗り込み、船体後部のデッキから太平洋を眺めている。
久しぶりに穏やかな時間が流れてく。慌ただしかったこの二ヶ月弱が嘘のように…。
「あっちに着いたら、待ち合わせ場所になってる水族館を見物しよう。色々と忙しくなるし、今日くらいはゆっくりさ…」
「それも良いわね。親子でどこか出かけるなんて、しばらく無かったものねぇ。…でも、残念だったわね?」
「ん?何が?」
尋ねた俺に、母は苦笑した。
「どうせなら、友達か恋人と一緒に行きたかったでしょう?せっかくのお台場なんだから」
「…痛いところを突くなぁ…」
苦笑いで応じた俺は、これ以上つつかれる前に話を変えようと考え、話題を探しながら何気なく視線を巡らせた。
「…あれ…?」
首を巡らせたままの格好で動きを止めた俺に、母が訝しげな視線を向ける。
「どうしたの?ヨルヒコ」
母の問いに答えるのも忘れ、俺はその、信じ難いものを見つめていた。
濃いベージュ色のロングコートの裾を潮風ではためかせ、デッキを横切って颯爽と歩いてくる、整った顔立ちの女性…。
目の前で足を止めた女性に、母はとりあえず会釈し、俺は目を見開いて硬直する。
「初めまして、忌名圭子さんですね?」
丁寧に一礼し、女性は微笑んだ。
「字伏白夜の指示により、現地まで同行し、身辺警護に当たらせて頂く、フォウと申します」
「あらあら、それはご丁寧にどうも…。ご迷惑をおかけしますね?」
フォウの事も、詳しい事情も知らない母は、呑気にお辞儀を返している。
「…な、な、な…!?」
フォウは上手く言葉が出てこない俺に視線を向けると、
「そういう訳だ。同行させて貰うぞ?ヨルヒコ」
と、口の端をゆるやかに吊り上げ、魅力的な笑みを浮かべた。
「どうやって追いついたんだ?電車じゃ無理だろう?」
フェリー内に設置された自販機でザクロココアを買いながら尋ねると、母のお茶と自分のミルクティーを抱えたフォウは、
可笑しそうに笑った。
「実はな、深夜の内に、君が眠ってから出発し、先に訪れて港とフェリーを監視していたのだ。安心して良い。相麻の手の者
も、他のライカンスロープも、このフェリーには乗っていない」
…全然気付かなかったな。てっきり小屋で眠ってるとばかり思っていた…。
「そうか。一安心だな。…って、護衛に同行するって事、俺は聞いてなかったんだけど?」
「ああ。急な事で迷惑をかけたが、私からビャクヤに頼み込んでな。戦力は一人減るのだが、快く承諾してくれたよ」
「へぇ、ビャクヤに…」
…ん…?フォウが、ビャクヤに頼んだ…?
俺の視線を受けたフォウは、「しまった!」というように口元を手で覆った。
「いや、その…、つけられて、洋上で襲われたら逃げ場がないだろう?ましてや母君も一緒なのだ。誰かが護衛につくべきだ
と…思ってだな…」
慌てた様子で、少し頬を染めて早口で言ったフォウに、俺は笑みを返した。
「ありがとう。嬉しいよ、フォウ…!」
「…ん…うむ…」
礼を言った俺から、フォウは照れたように視線を逸らした。
…嬉しかった。フォウも、俺の事を憎からず思ってくれていると、実感できたから…。
「待ち合わせ場所、水族館なんだ。着いたら三人で見物しよう」
「ああ。まぁ、気を緩め過ぎない程度ならだが…、それも良いかな…。私も水族館など、行った事は無かったし…」
フォウは頬を赤らめたまま、ぼそぼそと言った。
泣きたくなるほど辛い別れもあったけど、こうして、一緒に居られる仲間も居る…。
ビャクヤ、俺は大丈夫だよ。
…だから…、ビャクヤも…。
俺は、これから行く先の街で、タマモさんという元締めに頼むべき事に思いを巡らせながら、フォウと並んで母の待つデッ
キへと向かった。