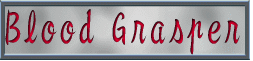
FILE21
「お〜。可愛いなぁ北極熊!」
悠々と水中を泳いでいる白く大きな熊を、分厚いガラス越しに見つめる俺の横で、
「む…?可愛いか…?大き過ぎるせいか、私は軽く警戒心が…」
と、フォウは首を傾げた。
言っている意味が理解できた訳じゃないだろうけど、北極熊はフォウ目掛けて真っ直ぐに泳いで来た。
まん前にやって来た北極熊を見て、フォウは軽く仰け反る。
「なんとなくビャクヤに似てないか?のんびりしてるトコとか、白くてデカいトコとかさ」
ガラスの向こうで水面へと浮上して行く白い巨体を眺めつつ、俺は笑いながらフォウに話しかけた。
「…言われて見れば、少し似ているような気も…。それはそうと、お母様はどうした?今までここに…」
尋ねるフォウに、俺は少し離れた所にある小さな水槽を指し示して見せた。
その水槽の底に居るコロッとした奇妙な魚を、母はさっきからずっと食い入るように見つめている。
「あそこ。ダンゴウオって名前の妙な魚に見入ってる。可愛いんだってさ」
「…可愛い…のか…?」
フォウは理解に苦しむように眉根を寄せ、首を傾げた。
「ところで、約束の時間まであと一時間あるが…、ずっとここに留まるか?」
「う〜ん、そうだな…。下の売店とか見とく?」
リーフレットタイプの案内図を取り出し、売店の位置を確認しようとした俺は、素早く顔を上げ、嗅覚を鋭敏化した。
「…どうした?」
問い掛けながらも、俺の様子から事態を察したんだろう、フォウは声を潜めつつ、油断無く周囲を見回す。
俺達の周囲には客がごった返してる。全員が普通の人間の客だ。…けれど…。
「…ライカンスロープの匂いだ…!」
俺は確信しながらも、周囲をはばかって小声でフォウに告げた。
「会うはずの相手は、人間、それも女性と言っていたな…?」
声を潜めたフォウに、俺は小さく頷く。
「ああ。待ち合わせ相手じゃあない…!」
「数と位置は?」
鋭い視線を周囲に向け、俺達と母の位置関係と移動経路を確認しながら、フォウが小声で尋ねる。
屋内で見通しが利かないここじゃあ、俺の鼻が頼りなんだが…。
「…駄目だ…!館内の空調で、空気の流れが読み辛い…!順路の後方からの気がするけど、位置までは…!」
「判った。ならば移動しよう。ただ偶然居合わせた相手かもしれんし、接触を避けるに越した事はない」
俺とフォウは目立たないよう、小さく頷き合い、母に歩み寄って部屋を移動した。
相麻の連中…?だが、フェリー内には俺達を追ってきたライカンスロープは居なかった。
フォウも確認してくれていたし、俺だって何も感じなかった。尾行されてはいないはずだけど…。
この匂いの主は、一体何者だろう?無関係な相手なら良いんだが…。
夕暮れに染まる空の下、水族館の裏手、オープンテラスのカフェで四人がけの席につき、俺とフォウは母を挟む形で、周囲
に視線を配っていた。
待ち合わせ場所の変更は、先程携帯でタマモさんに告げた。じきに迎えが来るはずなんだけど…。
「…現れないな…」
フォウは腕時計を確認し、僅かに焦りを滲ませた声で呟いた。
刻々と向きを変え続ける潮風に混じって、時折ライカンスロープの匂いが運ばれてくる。
俺の鼻がかろうじて捉えられる程度で、フォウが感知できない事から、近くに居ない事だけは確かなんだが…。
海側から強い風が吹いた途端、俺は鋭敏化させている嗅覚で、また新たな匂いを捉えた。
…また、新手か…!?
匂いはこの近辺、結構広い範囲に散っている。
それも、刻々と新たな匂いが加わり、すでに二十近い匂いを確認している。
俺達は消気水で匂い誤魔化しているから、そうそう気付かれはしないだろうけど、勘の鋭いヤツと面と向かえば、あっさり
バレる可能性もある。
じりじりと焦燥感を募らせていた俺達は、
「済みません。遅れてしまいました」
突然かかったその声に、文字通り飛び上がるほど驚いた。
そのひとは、突然現れた。
ライカンスロープの匂いと気配に集中していたせいか、俺もフォウも、すぐ傍に接近されるまで、危険では無いその気配を
無視してしまっていたらしい。
そう、そのひとは人間…、それも女性だった。
この女性…、歳は二十代半ばから後半といったところか?
薄く口紅を引いただけの、化粧気がない顔には分厚い丸眼鏡。
動きやすそうなジャケットを羽織り、下は色褪せたジーンズを穿いている。
女性はニッコリと微笑むと、
「シルバーフォックスの使いです」
と、打ち合わせ通りの言葉を口にし、俺達に会釈した。
「あらあら、ご足労をおかけしまして済みませんねぇ」
「いえいえ、こちらこそ大変お待たせしちゃって、本当にごめんなさい」
母と女性はやけにほのぼのと笑いあう。
…結構、油断できない状況なんだけどな、今…。
それから女性は小さく首を傾げ、フォウの顔を見つめた。
「…変わった気配ですけど…。猫さん…でしょうか?」
「…はい、そうですが…。…何故それを?」
フォウは少し警戒しているように、女性の仕草を観察しつつ頷いた。
疑問はもっともだ。俺達は消気水でライカンスロープの匂いを消している。
なのにこの女性は、あっさりとフォウの正体を言い当てて見せた。
「私自身は普通の人間ですけれど、皆さんの本来の姿を感じ取れるんです。希少な能力らしいですね?」
「では貴女は、パシーバー…ですか?」
フォウが少し驚いている様子で、俺には聞き覚えの無い言葉を口にした。
「一部の組織などでは、そういう風に呼ばれてるらしいですね?」
女性は微笑みながらそう言うと、俺に視線を向けた。
そして物珍しそうに俺の目を覗き込む。
「あら珍しい…!貴方は人狼ですね?」
「はい。…人狼って、珍しいんですか?」
首を捻った俺に、女性は微笑を絶やさずに頷いた。
「ええ。私が直接会うのは貴方で三人目です。…あ、いけない!」
女性は口元を押さえると、
「済みません。長旅でお疲れなのに話し込んでしまって…。早く移動しちゃいましょうか」
そう言って、何気ない感じで周囲に視線を走らせた。
「…25…、いえ、27人…。何者かしら…?少なくとも、私達の同志じゃない…」
小さく呟かれた女性の言葉に、俺とフォウは舌を巻く。
この女性、生粋の人間らしいが、ライカンスロープを感知する能力は俺より遙かに高い。
同族の中でも飛び抜けて鋭いはずの人狼の嗅覚でも、人数を捉えるまでには至ってないのに…。
「車を待たせています。ついてきて下さい」
歩き出した女性は、後ろに連なった俺達を振り返り、苦笑を浮かべて見せた。
「あぁ済みません…。まだ自己紹介していませんでしたね?私は字伏洋子(あざふせようこ)といいます」
…は…!?
俺とフォウは足を止め、
『アザフセ!?』
と、同時に声を上げていた。
アザフセと名乗った女性は、突然声を上げた俺達を、少し驚いた様子で見つめていた。
「はい。…どうかしましたか?」
「あ、そ、その…!アザフセって、貴女はもしかして…!?」
ビャクヤの知り合い!?いや、親類!?…いや…、もしかしてもしかすると、ビャクヤの弟の関係者!?
訊きたいことが一気に頭の中を駆け巡り、どこから尋ねようか迷っていると、
「…あ…」
突然、アザフセさんが小さく声を上げた。
俺達の後方を見つめるその顔には、警戒の色。
が、彼女は特に何も言わずに前に向き直り、歩き出す。
「…落ち着いて、何事も無いように私についてきて下さい」
歩きながら、アザフセさんは小さな声で続けた。
「…気付かれました…。でも、知らんぷりしていて下さい。なんとかまいてみます」
アザフセさんから警告を受けた俺とフォウは、互いに素早く目配せし、それとなく母を挟んでガードする。
風向きが変わり、追い風になると、俺の鼻ははっきりとライカンスロープの匂いを嗅ぎつけた。
…かなり近い…!四人か!?
アザフセさんに先導され、俺達はとあるビルに入り、土産物屋のスペースを歩き抜け、反対側の出口から外に出た。
ビル内で、気配はいつのまにか二つ減った。疑問に思っていると、
「見張りに回っていた同志達が援護を始めてくれました。このまま車へ向かいます」
と、アザフセさんが小声で説明してくれた。
どうやら彼女の仲間達が、俺達をサポートしてくれているらしい。
…だが、しかし…。
「フォウ…。アザフセさんと母さんを頼む」
母とアザフセさんに聞こえないように小声でそう告げると、フォウは訝しげに、横目で俺を見た。
「また増えた。追って来るのは8人…、このままじゃ囲まれる…」
「待てヨルヒコ…!君は何を…?」
慌てたように口を挟んだフォウを制し、俺は彼女の肩を叩いた。
「俺のスピードは知ってるだろ?囲みを突破して引き付けて、攪乱して来る」
既に日は沈みかけてる。闇に紛れて人狼になれば、攪乱して逃げるくらいは何とでもなる。俺一人ならの話だけど…。
「駄目だ。地理にも不案内なここで…」
「行き先は知ってる。大丈夫。任せてくれ」
「しかし…!」
「頼むフォウ…!この中でたった一人だけ男の俺が、他の誰かにしんがりを任せる事はできない。…ビャクヤの義弟として、
恥ずかしい振る舞いはしたくないんだ」
「え!?」
小声で話していたんだが、アザフセさんの耳にも話が届いたらしい。
彼女は足を止め、驚いたように俺達を振り返った。
「い…、今、何て!?」
「済みません。今はゆっくり話をしてる余裕が無いんで、先に行って下さい」
俺はアザフセさんに頭を下げ、
「母さん、ちょっと行ってくる」
母には笑みを投げかけた。
「ヨルヒコ…。…ええ、気を付けて、いってらっしゃい」
一瞬心配そうな顔をした後、俺の心を察してくれたんだろう。母さんは笑みを浮かべて見せた。
親指を立てて笑顔で頷き、それからフォウに視線を向ける。
「それじゃあ頼んだ。また後で、フォウ…」
フォウは悔しげに俺の顔を見つめた後、諦めたように小さくため息を零した。
「…判った…。無事に帰らねば承知しないぞ?…後でな、ヨルヒコ…」
俺はその場で踵を返し、三人とは逆方向、ライカンスロープの気配に向かって歩き出した。
ポケットに両手を突っ込み、堂々と胸を張り、不敵な笑みを浮かべて。
片側三車線の太い道路をまたぐ歩道橋へ足を向け、素早く敵の数を確認する。
…近くに居るだけで十三か…。これは、よほど上手く立ち回らないとな…。
間違いなくライカンスロープであろう三人の男が、俺の前方から歩いてくる。
外人だな…。たぶん、相麻の傭兵だ。
考えてみれば、この国の何処に行っても相麻の支部やら工場やらがある。
俺の顔はミストとカグラを通して、工場壊滅前には相麻に知られていたはずだ。
それに、フォウが離反した事も、既に知れ渡っているだろう。
先回りはされなくとも、現地のヤツらが俺達に気付く事は予想しておくべきだった。
…水族館なんかを待ち合わせ場所にするんじゃなかったな…。
後悔しても仕方がない。俺は警戒心をあらわにしている男達を遠くに眺めつつ…、歩道橋へ走り込んだ。
突然の行動にも動揺を見せずに、男達は俺の後を追って歩道橋を駆け上って来た。
そうだ、良いぞ…、ついてこい!
なるべく目立つように派手に走り回り、追っ手を引き付けながら、俺は月に照らされたお台場を、倉庫の建ち並ぶ区画目指
して駆け抜けた。
十数人にも膨れ上がった追っ手を引っ張りまわして、倉庫群の中に引き込んだ俺は、闇の帳が降りた倉庫の隙間に駆け込んだ。
軽く目を閉じて、乱れた息を整える。
汗で濡れた体は、三月の海風を受けて冷えて行く。
心臓がバクバク鳴り、足が震え、ふくらはぎが痙攣する。
…三人から引き離すのには成功したけど、すっかり囲まれたっぽい。
ゆるりと流れる潮風の中に、殺気立った獣の匂いと気配が漂っている。
…逃げ続けるのは、もう限界だな…。
立ち並ぶ倉庫に反響する、何人もの足音…。この近辺に潜んでいる事には、やっぱり勘付いてるか…。
…覚悟を決めろ、ヨルヒコ…!戦って、生き延びて、母とフォウの元に向かうんだ…!
俺は倉庫の隙間から覗く、細く切り取られた夜空を見上げた。
…ビャクヤ…。
薄い雲がかかった半月が、俺に黄色い光を投げ落として来る。
月は、あの山で見上げたのと同じ、静かで、穏やかで、そしてそっけない顔をしてる。
…俺に、力を…。
弾ける鎖をイメージすると同時に、夜空に浮かぶ月が鮮明さを増し、その表面の筋や穴までがはっきりと瞳に飛び込んで来る。
皮膚を銀の毛が覆い、骨格がメキメキと変形する。
月を見上げる俺の目前で、顔の下半分が前に向かってせり出していく。
筋肉が膨れ上がり、細胞の一つ一つが息を吹き返す。
ダルさと震えは完全に消え、疲労に代わり、全身に力が漲った。
銀の人狼の姿を取り戻した俺は、ふさふさした毛に覆われた銀の尾を一振りし、頭頂の耳を素早く動かした。
匂いが、音が、これまでよりもずっと鮮明に捉えられる。
いつも胸の中に灯っていた銀の炎は、今ではもうそのイメージを感じられない。
ミストとの闘争の最中、弾けたイメージを残して消えて以来、感じる事ができなくなってしまった。
人狼の本能、誇り、そういった物は今でもこ胸の中にある。ただ炎だけが消えている。
思うに、あの炎は、俺が思っていたような、人狼の魂なんかじゃない。
人狼の魂を包み、燻っていたあの炎は、俺の中に眠っていた力の兆し…。
つまり、ブラッドグラスパーとしての力のイメージだったんじゃないだろうか?
だから力が覚醒すると同時に、消えてしまったんだろう。
胸の中で揺らめいていた銀の炎は、今では俺の血を媒介にして燃え盛る、黒い炎に変わったわけだ…。
僅かな時間、物思いに耽っていた俺は、クリアになった感覚で周囲の気配を探った。
…捉えた…!
気配をキャッチし、全身をたわめ、倉庫の屋根の上へと一気に跳躍する。
僅かな風切り音で気付いたか、屋根の上に居た焦げ茶色の虎猫が振り返った。
声を上げようと口を開いた猫の顔が、俺の視界の中で急激に拡大する。
声を出される前に左手で口を覆い、爪を揃えて硬化させた右手を、突進の勢いを乗せて鳩尾に潜り込ませる。
口を塞いだ手の平が、ごぼりと吐き出された血で濡れる。
背中まで突き抜けた右手を引き抜き、地面に押し付けるように猫を引き倒す。
致命傷を負った猫が、最期の痙攣を繰り返しながら、カース・オブ・ウルブスに蝕まれて行く…。
血臭が周囲に立ち込め、風に溶けて行く。…余裕は無い、さっさと済ませないと…。
「…死にたいか…?」
死んだ身体に魂を縛り付けられた猫に、俺は低い声で問いかける。
うつ伏せに倒れ、顔を横に向けた猫の、瞳孔の開いた瞳が俺に向けられた。
最初は何が起こったか解っていない様子だった。が、自分が人狼に殺されたのだと悟ったのか、猫の目が少しだけ見開かれた。
人狼に破壊されて死んだ者は、呪いに蝕まれて、魂が死体に縛り付けられる。
死に至った痛みを、苦しみを、体が完全に朽ち果て、魂が解放されるまで、ずっと味わい続ける事になる。
これまで、俺にとってのこの力は、相手を殺めてしまった時に勝手に発動してしまうだけの物だった。
つまり、この力を自分の意思で利用するのは、今回が初めてという事になる…。
正直に言えば気は進まないけど、今は四の五の言っていられない…!
「正直に質問に答えれば、開放してやる。良いな?俺の質問に答えるんだ」
俺は猫の顔を引き起こし、その死人の目を真っ直ぐに見つめた。
強烈な嫌悪感と罪悪感が湧き上がる…。でも、目を逸らしちゃダメだ。これは、俺が俺の意思でやった事なんだから…。
「お前達は相麻の傭兵だな?違うなら一回、あってるなら二回瞬きしろ」
俺の問いに応じて、猫の目は、二回しばたいた。
間違いないと確信はしていたけど、人違いで殺したわけじゃないと確認が取れて、俺は少しだけほっとした…。
「どれぐらいで来ている?20人以上か?」
猫の目が二回瞬きした。
「30人以上か?40人以上?50人以上か?」
50人以上かとの問いかけに、猫の目は一度の瞬きで応じた。
40人以上、50人以下…?くそっ!予想以上だ!俺だけじゃどうしようもない数…!
「…そうだ…。どこを集中的に守っている?この辺りに皆居るのか?」
猫の目が、二回瞬きした。
…なら、なんとかなるかもしれない…!
この辺りに集まっているなら、どうにかして突破さえしてしまえば、逃げ切れるかもしれない!
この大きな街で、消気水で気配を絶ったライカンスロープ一匹を見つけ出すなんて、そう簡単な事じゃない。
この包囲を突破できれば、あとは…!
希望を見い出し、安堵の息を漏らしかけた俺は、風切り音を耳にして、その場を飛びのいた。
後ろ向きに跳躍した俺の目の前で、工場の屋根にガガガガガッと音を立てて、細かな穴がいくつも開く。
何だ?何か小さな物が何個も飛んで来て…?銃弾じゃあないようだが…。
飛び退って着地した俺は、屋根に穿たれた穴を、そして猫を見遣る。
離れる寸前に呪いを解除した猫は、その瞳から意識の光を失くし、ピクリとも動かなくなっていた。
屋根の穴の方は…、六つ確認できる。どれも指がスポッと入るくらいの大きさだ。
火薬の匂いなんかは全くしない。やっぱり銃じゃないみたいだな…。
猫から視線を外し、俺は気配の元を見据える。
闇に浮かぶ灰色と黒の体。…犬?それも、結構でかい…。
確か、シベリアンハスキーっていう犬だな。隈取のある顔の犬が、蒼い瞳で俺を見つめてる。
ゆっくりと踏み出した犬の後ろに、ワニと…ヤギ?いや、ガゼルってヤツか?見慣れない草食獣のライカンスロープが居る。
…相麻の傭兵はバリエーションが豊富だな…。
こんな状況なのに、俺の頭の中には、そんな呑気な感想が浮かんでいた。