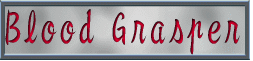
FILE3
柔らかく、温かい毛布の感触。
カーテンの隙間から注ぐ光が、瞼越しに眩しく感じられる。
スズメだろうか?時々鳥の声も聞こえてくる。
俺はベッドの中で寝返りを打ち、落ちかけた掛け布団を肩に引っ張り上げた。
あ〜…、幸せ…。もうちょっとだけこのままで…。
コンコンッ
ノックの音が響いた。
…今日は休みだよ母さん…。疲れてるんだから、もう少し寝かせてくれって…。
ところが、返事をしていないにも関わらず、ドアは勝手に開いた。
…あれ…?いつから俺の部屋、襖からドアにバージョンアップしたんだっけ…?
「お〜い。朝だよ〜」
いいじゃないか朝でも…。休みなんだから…。
…ん?母さん風邪でも引いたのかな?声が変だぞ?
「…ん〜…あとごふん…」
俺がモゾモゾと布団の中に頭を引っ込めながら言うと、
「ふふ、さっきもそう言ったじゃないか?もう十五分以上経ったよ?ねぼすけ君っ」
可笑しそうな含み笑いが聞こえた。
…あれ?違う。母さんじゃないぞこの声?誰だ?
俺は布団から顔を出し、薄目を開けて首を巡らせ、声の主に視線を向けた。
「おはようヨルヒコ君。良く眠れた?って、聞くまでもないかな?あははは」
鼻がくっつきそうなほど、俺の顔のすぐ傍で、白いムクムクの毛に覆われた犬の顔が、…笑っ…た…?
「や。おはよう」
白犬が笑顔のまま、すちゃっと手を上げた。
「ぎゃぁぁぁあああっ!!!化け物ぉぉぉおおおっ!!!」
悲鳴を上げて身を離そうとした俺は、ベッドから落ちて木の床に腰をぶつけた。
「いって!」
腰を抑えて呻いた俺を見下ろし、オーバーオールに身を包み、直立した白犬が可笑しそうに笑う。
「あはははは。化け物は酷いなぁ」
笑う犬の顔、見慣れないもののはずなのに、改めて見れば不思議にも怖いとは思わなかった。穏やかな、人の良さそうな笑
み…。…あ…?
その時やっと、俺は昨夜の事を思い出した。
目の前の白い巨漢の事。カワムラと一緒に山の中を走った事。獣に変身する妙な連中の事。そして、俺の体…。
おそるおそる、まず、自分の手を見た。
俺の手は、鋭い爪を備え、銀色の毛に包まれていた。
「あ」
頭に触ると、三角に尖った耳がついていた。
「あ…」
顔をさすると、鼻から下、下顎までが、前に突き出していて…、
「あああ…」
今気付いたが上着は着ていない。トランクス一丁だった。見下ろすと、銀の毛に覆われた筋肉質な胸板が見えた。
「ああああああ…」
ふと思い立って振り向くと、半ケツ状態のトランクスの上、尾てい骨の辺りから生える尻尾…。意識したらピコッと動い…、
「ぎゃぁぁぁぁあああああああああああっ!?」
獣型の口から、俺は絶叫を上げていた…。
「落ち着いたかい?」
「は、はい…。なんとか…」
床に手を付き、項垂れながら応じた俺に、白犬は苦笑いしながら頷いた。
「まぁ無理も無いよ。アサヒちゃんと同級生って事は、17歳か18歳でしょ?これまで人間として生きてきて、急に覚醒し
たんじゃねぇ…」
…そうだ…。覚醒って、昨日も何度か言ってたな?
俺は顔を上げ、白犬の目を見つめる。
彼が何者なのかはまだ良く解らないが、俺の体に起きたこの異常な現象について詳しいらしいことは、なんとなく察しがついた。
彼自身も俺と同じ、獣と人を足して二で割ったような姿をしているし…。
「あ、あの…!」
ぎゅるるぅぅぅう〜っ…
質問を発しようとしたその時、俺の腹の虫が鳴いた。
…決まり悪っ…!俺が再び項垂れると、白犬は可笑しそうに笑い声を上げた。
「あはははは!元気がいいねぇ。君ぐらい若いならそうでなくちゃ。言い忘れてたけれど、朝食の仕度が出来たから呼びに来
たんだ。まずは腹ごしらえしようか」
俺は頭を掻きながら、ニコニコ笑っている白犬に頷いた…。
さすがにトランクス一丁はまずい。
だが、昨日着ていた制服は白犬が洗濯してくれたらしく、まだ乾いていないそうで、着るものが無い。
白犬は俺に、ティーシャツと膝上までの厚い生地のハーフパンツを貸してくれた。
上着はぶかぶかだが、まぁあまり気にならない。ハーフパンツはウェストがかなりあまって、ベルトできっちり絞めなくて
はずり落ちてしまう。
色はどちらも濃いグレーで、銀の毛に覆われた俺の体に合わせてチョイスしてくれたことが察せられた。
白犬はハーフパンツの尻の部分を少し裂き、尻尾を出す穴を作ってくれた。
ふと見れば、彼自身には尻尾が無い。…申し訳ないなぁ、壊させてしまった…。
普通ならこの季節では寒すぎる程の薄着だが、全身が毛皮に覆われているせいか、寒さは全く感じなかった。
白犬に連れられて、恐らくは居間兼台所なのだろう、なんだかいい匂いのする広めの部屋に入ると、テーブルについていた
カワムラがオレに視線を向けた。
「おはよ。やっとお目覚め?ねぼすけねぇ」
「う…。お、おはよう…」
白犬はテーブルにつくよう俺に勧め、自分はかまどのところに行く。
オブジェとか、かまどのデザインのコンロとか、そういうものじゃない。薪を使う本物のかまどだ。ナマでは初めて見たな…。
椅子を引いて腰掛けながら、かまどと白犬に視線を向けてみる。
かまどの上には大きな鍋。白犬は手馴れた様子で鍋の中身をシチュー皿によそうと、向かい合って座っている俺とカワムラ
の前に、湯気の立つシチュー皿を置いた。
ビーフシチューだ…。凄くいい匂いがする…。
白犬は自分の分のシチューと、大皿に載せたぶつ切りのフランスパンをテーブルに置くと、椅子を引いて腰掛けた。
「冷めないうちにどうぞ」
「いただきまーす」
白犬が促し、カワムラがシチューをスプーンで掬い、口元に運び始める。俺は少し躊躇した後、
「頂きます…」
シチューをスプーンで掬った。凄く美味かった。
「あの…」
食事が済み、白犬が立ち上がったのを見計らい、俺は声をかけた。
白犬は空になったシチュー皿を手にしたまま、俺に視線を向ける。
「えぇと、助けてくれて、ありがとうございました…。その…聞きたい事が、いろいろあるんですけど…」
「あ、ビャクヤ。あたしが片付けるわ」
カワムラはそう言って立ち上がると、白犬から食器を預かり、かまどの傍のたらいに食器を運んでいった。
カワムラが片付けを始めると、白犬はその背に声をかけた。
「それじゃお願いするよ。僕らはテラスに出ているからね」
白犬に促され、俺はドアを潜って外に出た。
外に出てから初めて聞かされたが、俺が運び込まれたのは白犬の家…、丸太で作られた小屋、ログハウスだった。
子供の絵本に出てくるような丸太の小屋は、煉瓦の煙突がついていて、周りにはウッドテラスが巡らされている。
俺は白犬に連れられて、テラスにおいてある木製の長椅子に、彼と並んで腰掛ける。
白犬はポケットからタバコを取り出し、火をつけて美味そうに吸った。
吐き出された煙は、ハッカの香りがした。
「あの、アザフセさん…」
おずおずと口を開くと、白犬は横目で俺を見て、微かに笑った。
「ビャクヤで良いよ。アサヒちゃんもそう呼んでる」
「は、はい。ビャクヤさん…」
「「さん」もいらないよ。僕からすれば呼び捨てにして貰った方が気楽だから、そうしてくれないかな?敬語も使わなくてい
いからね」
「あ、はい…。えぇと、ビャクヤ…」
戸惑いながら頷くと、ビャクヤは笑みを浮かべたまま頷く。
俺は、今になってやっと、ずっと気になっていた事を口にした。
「貴方は…、いや、俺は…、何なんだ…?やっぱり、変なクスリとかのせいでこういう姿になってしまってるのか?」
本来なら、真っ先に聞くべき事だろう。…でも俺は、この事を聞くのが怖かったのだ…。
「クスリ?どういう事だい?」
「昨日、手足が痺れる麻酔みたいなものを注射されてから、俺はこの姿になった。あのクスリの効果かと思ったんだけど…」
「それはたぶん、ただの麻酔だろうね。僕や君が今の姿で居るのは、薬なんかの外的な要因の効果じゃない」
ビャクヤは前を向いたまま目を細める。俺はその横顔をじっと見つめながら、彼の答えを待った。
「ライカンスロープ。それが、君や僕のような存在を指す言葉として、古くから使われている名だ」
「ライカン…スロープ…?」
呟いた俺に頷くと、ビャクヤは続ける。
「狼男、リカント、ネコマタ、虎人、ジャガーマン…。世界中には様々な、多数の獣人伝承がある」
いくらかは聞いた事のある名前があった。ゲームや漫画にも出てきたりするから。
「その中のいくらかは事実に基づいた伝承なのさ…。…信じられないみたいだね?」
ビャクヤは横目で俺をちらりと見ると、ニッと笑って親指を立て、自分を指し示した。
「でもこの通り、君の目の前に実物が居るわけでね」
…そう。彼も、そして俺も、明らかに人の姿をしていない…。
「ショック、だろうねぇ…」
項垂れた俺の頭に、ビャクヤはポンと大きな手を乗せた。
「俺…、もう、元には戻れないんですか…?」
一晩経っても、俺の体は狼と人の中間みたいな姿のままだ。もしかして、俺はもう一生、この格好のまま生きなくてはいけ
ないんだろうか…?
「戻れるよ」
あっさりと口にされたビャクヤの言葉に、俺は弾かれたように顔を上げていた。
ビャクヤは右の眉を上げ、笑みを浮かべて見せる。
「戻る、というのは正確じゃないかな。君の本来の姿は、今の姿の方なんだから。でも、また人間の姿になる事も勿論できるよ」
ビャクヤはそう言うと、俺の頭を軽く撫でた。
…温かくて、大きくて、彼の手で頭を撫でられたら、少しほっとした。
「方法を教えてあげる。だから安心していいよ。まぁ、練習に丸一日かかるかも知れないけれど…」
戻れる…!それを聞いて安心したら、体から一気に力が抜けた…。
「呼吸を落ち着けて…、自分の鼓動を把握して…、全身を巡る血を、それが運ぶ力を感じ取る…」
俺は地面にあぐらをかき、ビャクヤの言葉に従って意識を集中する。
ビャクヤは俺と向かい合わせであぐらをかき、じっと俺の様子を見ながらアドバイスをしてくれている。
「一箇所に意識を集中しちゃだめだよ?しっかり感じ取るんだ。血の流れを、力をね。その全身を巡る血を支配すれば、変身
は自在にできるようになる」
すでに日は傾き始めている。こうやってもう四時間以上もの間、元の姿に戻る練習を続けてる。
そして、ある瞬間、それは唐突に訪れた。
「良いよ…。その調子だ…」
ビャクヤの声が、僅かに緊張を帯びた。俺は戸惑いながら頷く。
奇妙な感覚だった。全身を巡る血液が、その道筋が、血流の強弱や速度までが、ある瞬間、手に取るように把握できるよう
になった。
いや、ずっと把握していたんだ。ただ、見過ごしていたような感じ…。
一度見破った隠し絵が、次からははっきりと見えるように、一度意識を逸らしても、注意を戻せばすぐに捉えられる。
この瞬間だった。俺が初めて自分の血の流れを、力の道筋を、完全に捉えたのは。
「次は血の道筋に沿って、自分の意識を全身に流すんだ」
血の流れを捉えた後は、ビャクヤの言葉に従って、俺はスムーズに体の隅々まで意識を向けることができるようになっていた。
内臓の蠕動や、毛細血管の脈動、神経を走る電気信号までも全て把握できる。
「五体に満遍なく、意識の糸を張り巡らせて、そして、意思の力で獣の力を束縛する…」
ビャクヤの声を聞きながら、俺はその言葉に従い、隅々まで把握した自分の体に…、
「命じるんだ。鎮まれ、と」
ビャクヤに言われるまま、鎮まれと、命令を下した。
「…うっ…!」
全身を襲うむず痒い感覚に、俺は思わず呻き声を上げた。
体が締め付けられるような、窮屈な感覚。
そうとは自覚しないままに全身に漲っていた力が圧縮され、体の深いところ、細胞一つ一つの奥深くへ収納されてゆく。
骨格が音を立てて変形し、人の形に戻ってゆく。
筋肉が収縮し、熱になったエネルギーが周囲に放出され、陽炎を作る。
鼻の辺りがむず痒い!視界の中で鼻がみるみる低くなり、近付いてくる。
体が縮み切った後、全身から銀の被毛が抜け、体から放射される熱に舞い上げられ、ブワッと散った
銀の被毛は空中で細かい光になり、煌きながら、空気に溶けるようにして消えてゆく。
俺は手を顔の前に翳してみた。
毛の無い、つるんとした、見慣れたはずの手の平は、何故か頼りなく感じられた…。
「おめでとう。これで一安心だね」
呆然と手を見つめる俺の前で、ビャクヤは微笑んでいた。
「ありがとう。良かった…、戻れ…て…、へ…、へっくし!」
俺は盛大にくしゃみをした。
ビャクヤから借りたティーシャツとハーパンだけでは、二月の夕暮れの空気は、この体には堪えた…。
洗ってもらい、乾いた制服を身に付けた俺は、破れ目が修繕されている事に気付いた。
「感謝しなさい」
カワムラが胸を張ったので、俺はペコリと頭を下げる。
「ビャクヤが繕ってくれたんだから」
…ってお前じゃないのかよカワムラ?何でエラそーなんだ?
「ありがとう。ビャクヤ…」
「どういたしまして」
白犬は眉を上げて笑みを浮かべる。
…料理はするし、裁縫はするし、何ていうか、家庭的だな…。ビーフシチューは母さんのよりも美味かったし…。
「あ!!!」
俺は母に何の連絡もしていなかった事に、今更気付いた。
慌てて携帯を取り出すと、
「あ、あんたのお母さんには連絡しておいたわよ?あたしがゴーストライターでメール送っておいたから」
見れば、「友人の家に泊まります」という俺(実際にはカワムラ)が送ったメールに、母から了承した旨のメールが返信さ
れていた。…ほっ…。
「そろそろ出ないと遅くなるよ?」
そう言ったビャクヤに深々と頭を下げ、俺はもう一つ、聞いておかなくてはならない事を思い出した。
「あの…、昨日の連中は、どうなったんだ?」
「夜の内に山の麓に運んでおいたよ。朝方に引き上げて行ったのを確認した。丸一日分の記憶は消してあるから、君の事も、
僕らの事も覚えてはいないから安心して。自分達に何が起こったかも分かってないし、匂いも痕跡も全部消してあるしね。…
ああ、でも念の為に昨日とは違う側から道路に出てくれるかな?」
記憶を消した?…そういえば、ビャクヤはあいつらの頭に手を当てて何かしていたっけ…。催眠術か何かだったんだろうか?
「それと、これを持っていって」
ビャクヤは俺の手に、透明な液体の入った小瓶を握らせた。
「香水みたいなものでね。それを体にふりかけておいてほしい。昨夜は無断で使わせてもらったけれど、毎朝忘れずにね?」
「香水?何でそんなものを?」
「理由はまた今度話すよ。明日にでもまたここへ来て欲しい。まだまだ話さなきゃならない事があるからね」
俺はビャクヤに頷いた。それはオレからも頼みたい事だ。知りたい事はまだまだたくさん、それこそ山ほどある。
「…ああ、それと、ここの事や僕らの事は、他じゃ話してはいけないよ?」
それももちろんだ。俺達みたいな変り種のことが知られたら、世間は大パニックだろう。
それに、恩人であるビャクヤにも、きっと迷惑をかける事になってしまう。
「それと、次は何かお土産を持ってきなさいよね?」
これはカワムラだ。だから何でお前そんなに偉そうなんだよ?
それでも俺は頷く。ベタだけど、お礼に菓子折りか何か持ってくるべきだろう。…あ、そうだ…。
「ゲーセンでとった物だけど、良ければ…」
俺は鞄の中に詰め込んでいた、昨日とった飴玉やチョコなどの菓子類を机の上に出す。
何とも安上がりだけれど、一応せめてものお礼…、にはならないかなやっぱり。
と、思ったのだが…、
「え?貰っても良いの!?」
と、ビャクヤは垂れた耳をピクピク動かしながら、嬉しそうな笑みを浮かべた。
あれ?意外に喜んで貰えた?
「それじゃあ、明日また来るよ。お邪魔しました」
深く頭を下げてお辞儀した俺は、ふと気になって尋ねてみた。
「カワムラは、まだ帰らなくていいのか?」
「まだっていうか、今日は帰らないわよ。連休中はずっと泊まって行くから」
そうなのか。途中まで送って行こうかとも思っ…、…ん?連休中ずっと泊まり…?
俺は首を傾げ、ビャクヤを見る。
彼は困ったような顔をして、太い人差し指でポリポリと頬を掻いていた。
また明日来たら、この二人がどういう知り合いなのか、聞いてみようか…。