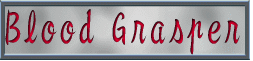
FILE4
登り始めは不安だったけど、どういう訳か、俺は一昨日の夜にカワムラと駆け上り、そして昨日の夕方に降りたルートを、
完全に見分けることができていた。
翌日の早朝、まだ空気が冷たい時間帯から山を登り始めた。もう二時間半以上歩いてる。
奇妙な事に、あの夜闇の中で見た枯れ木の位置や木立の並び、一本一本に至るまでがはっきりと記憶に残っていたし、視覚
の記憶だけじゃなく、足が、体が、感覚が道筋を覚えてる感じだ。
…感じ…だったんだけど…。
「あれ?」
俺は昨日通り抜けたはずの、二股に分かれた木の前で立ち止まった。
…おかしい…。この木の向こうに丸太小屋があったはずなのに、辺りを見回してみても、影も形も無い。
…似てるけれど、違う木なのかこれ?
「あぁ、ごめんごめん!」
周囲をうろうろしていたら、背後から声がかけられた。
振り向くと、二股の木の間に立ち、身を乗り出している白犬の姿があった。
「ビャクヤ?いつからそこに?」
今まで居たっけ?この巨体を見逃すはずもないんだけど、木の陰にでも居たんだろうか?
「うっかりしてたねえ、昨日の内に説明し忘れていたよ…」
ビャクヤは頬をポリポリ掻きながら言うと、俺を手招きした。
「普通には見つけられないように、昔少し齧った認識迷彩型結界を張ってあるんだ。改めて、家に来るための手順を教えるね」
意味が解らなかったけど、俺は大人しくビャクヤの言葉に従った。
俺はビャクヤに言われるままに二股の木を回り込み、斜面の上側から間を抜け、そして振り返ってみた。
「あれ…!?」
俺は思わず声を上げる。二股の木の間から、さっきまでは無かったはずの、煙突つきのログハウスが見えた。
「この手順を踏まないと、小屋と庭の存在を認識できないようにしてあるんだ。効果は見ての通り、この「マヨヒザクラ」を
媒体にした結界のおかげで、ここ十三年以上の間に、偶然に迷い込んだ人間はアサヒちゃんただ一人だけ…、っと、いきなり
そんな説明をしても判らないよね?あはは」
ビャクヤは苦笑いしながら、驚いている俺にそう告げると、ログハウスに向かって歩き出す。
…つくづく、不思議な事だらけだ…。
ドアを開けて小屋の中に入ると、キッチン兼リビングのテーブルでは、少女がマグカップを手にくつろいでいた。
「おはようカワムラ」
「おはよ、イミナ」
軽く手を上げて挨拶するカワムラのマグカップには、かわいくウィンクしているフクロウの絵が描いてある。
…そういえば、首から下げている木彫りのペンダントといい、携帯ストラップや鞄につけた小さなぬいぐるみといい、フク
ロウの小物ばかり持ち歩いているな…。こいつ、フクロウが好きなんだろうか?
「朝ごはんは食べたのかい?」
「あ、うん。家で食ってきた。…それと…」
尋ねたビャクヤに答え、俺はコンビニで買って来た菓子の詰め合わせを鞄から引っ張り出す。
「お礼って言うか…、つまらないものだけど…、一応土産を…」
そう言って差し出すと、ビャクヤは目をまん丸に、大きく見開いて笑みを浮かべた。
「え!?おみやげ!?僕に!?」
子供みたいにキラキラした目で菓子の箱を見つめるビャクヤ。
…いや、かたどおりのもので申し訳ないなぁと思ってたんだけど、もしかして、本気で喜んでくれてる?…そういえば、ゲ
ーセンの景品の菓子類でも喜んでたっけ?
「甘いものが好きなのよ、ビャクヤは」
受け取った菓子箱を嬉しそうに抱き締め、満面の笑みを浮かべているビャクヤを見ながら首を捻っていると、カワムラがそ
う説明してくれた。
…山の中に住んでいるから、菓子は貴重なのか?
いそいそと、本当に嬉しそうに紅茶を淹れるビャクヤに、俺は昨夜からずっと気になって仕方がなかった事をさっそく尋ね
てみた。
「あの、ビャクヤ?」
「うん?」
「ビャクヤは、いつもその格好で過ごしてるのか?」
山の中の生活だと、獣の格好の方が便利なんだろうか?そう思って尋ねてみたのだが…、
「僕はね、人の姿を否定したんだ…」
ビャクヤは、少しだけ寂しそうな微笑を浮かべ、そう呟いたが、この時の俺にはまだ、その言葉の意味は良く判らなかった。
「だからもう、人の姿になる事はできないんだよ」
「…ごめん…。辛い事、聞いたのかな…?」
会って以来、ずっと笑みを絶やさなかった白犬が初めて見せた表情に、俺は動揺した。
「気にしない気にしない。僕も大して気にしてないんだし」
気楽な口調で言ったビャクヤの顔からは、さっきの寂しそうな表情は消えていた。
三人で茶を楽しみながら、ビャクヤが話して聞かせてくれたところによると、俺とビャクヤはライカンスロープという存在
で、厳密には人間とは違う種族らしい。
ショックが無かった訳じゃないが、理解はすんなりできた。自分の身にあんな事が起きた後だったから…。
一昨日の夜にでくわした獣達もライカンスロープらしい。
どうやったのかは良く判らないが、ビャクヤは彼らの記憶を消したそうだ。
それと、ビャクヤがくれた小瓶に入った水は、ライカンスロープ特有の匂い…、一種の波長と言うか、気配のようなものを
薄め、消してくれる効果があるそうだ。
つまり、この「消気水」を忘れずにふっておけば、もしもまたあいつらと出会ってもライカンスロープと気付かれないのだ。
ついでに言うと、俺にもライカンスロープと人間を嗅ぎ分ける能力があるらしい。
ただ、ビャクヤも俺と同じで匂いを消しているらしく、今はまだその効果を確かめる事はできなかった。
…どういう風に感じるんだろう?一昨日の夜は夢中で、どんな風に感じていたのかは思い出せないな…。
その辺りまで説明を聞いた後、俺はビャクヤに質問した。
「あいつらは、何で俺を捕まえようとしたんだろう?」
ビャクヤは一口紅茶を啜り、少し考えてから口を開いた。
「目的までは判らないけれど、ろくな事じゃないだろうね。関わらないに越した事はないよ」
「あいつらも俺やビャクヤと同じなんだろう?なんで仲間なのに狙うんだ?」
ビャクヤは片方の眉を上げ、反対側の口元を吊り上げる。
少し驚いてるような、そしてどこか面白がってるような、あの奇妙な表情だ。
「念の為に言っておくよ?彼らと僕らは、なるほど確かに同族だろうね。けれども仲間じゃあない。そこはしっかりと理解し
ておいて欲しい」
眉根を寄せて首を傾げた俺に、ビャクヤは微笑んだ。
「同種だからといって、仲間だとは限らないよ。人間と同じさ」
…そうか。同じ種族でも、仲間…、味方とは限らない。それどころか、奴らは俺達にとって危険な相手なのか…?
「一度に話しても混乱するだろう?そのうち少しずつ説明していくけれど、ライカンスロープ同士の関係は、敵対か協力か、
人間よりも極端にはっきりと分かれるんだ。共同体を構築して人間社会に溶け込む者も居れば、単独で人に紛れて過ごす者も
居る。もちろん、僕のように極力他者との接触を避けて暮らしている者もいるしね」
俺はハッとしてビャクヤを見た。ビャクヤは「ん?」と首を傾げ、オレを見つめ返す。
「ごめん!俺…、一昨日はビャクヤを巻き込んだのか…!」
今更になって気が付いた!本当は、彼は静かにここで暮らしていたんだ…。
「済んだ事だよ。痕跡も記憶も消したし、もう心配は要らないんだから、気にしない気にしない」
ビャクヤは気楽な様子で笑ったが、俺はとにかく頭を下げて詫びるしかなかった。
「そういえば…」
こいつなりに気を遣っていたのか、これまで口を挟まず、黙って話を聞いていたカワムラが、ビャクヤに向かって首を傾げた。
「なんでイミナの記憶は消さなかったの?ここの事、知られたくなかったんでしょ?」
そういえばそうだ。俺も気になって視線を向けると、ビャクヤは困ったような顔で頬を掻いていた。
「僕にできるのは一定期間の記憶を纏めて消去する事だけで…、部分的にだけ記憶を消すのは不可能なんだ。だから、ヨルヒ
コ君から僕らに関する記憶を消そうと思ったら、一昨日からの記憶を全部消さなきゃならない。つまり、自分がライカンスロ
ープだという事も忘れて、彼らから正体を隠さなければいけない事も忘れてしまう」
「なるほど。イミナの身を守る為には仕方ないって事ね…」
カワムラが納得したように頷き、俺はますます小さくなった。
…助けて貰ったうえに、迷惑かけてばかりだな俺…。
「ところで、私が最初に迷い込んだ時はなんで記憶を消さなかったの?」
カワムラがなおも尋ねると、
「あの頃はまだ、この使い方は身につけていなかったからね。できるようになったのは四、五年前かな?あの時は君を信用す
るしか無かった」
ビャクヤはそう応じてから、微かに微笑んだ。
「でも、当時は使えなかったおかげで、僕はこうして週末毎に楽しい時間を過ごせてるのかな」
ビャクヤの言葉を聞いたカワムラは、なんだか顔を真っ赤にしてそっぽを向いた。…照れてるカワムラは…、初めて見たかも…。
「さて…、大まかな説明は以上だけれど、何か聞きたい事はある?」
「え?う、う〜ん…、いきなり言われても…」
正直、聞いた情報を整理するだけで精一杯だ…。困って頬を掻いた俺に、ビャクヤは微笑みながら言う。
「だろうねぇ。まぁ、焦る事はないさ。気になる事ができたら、その都度聞いてくれれば良い」
「うん。迷惑かける…」
また頭を下げた俺は、聞きたかった事を一つ思い出した。
「あ、そうだ。あのさ、カワムラとビャクヤは、どういう知り合いなんだ?」
「婚約者よ」
俺の質問にビャクヤが答えるよりも早く、カワムラが横からそう答えた。早押しクイズでもしてるような即答だ…。
「こん…?」
あまりにも意外な答えに、俺は口をパクパクさせながらビャクヤに視線を向ける。
「アサヒちゃん。婚約って…」
「ビャクヤ、私を予約してくれたわよね?」
「え?い、いや、それはまぁ…」
「私もビャクヤを予約したわ」
「そ…そう…だけど…」
しどろもどろに応じながら、恥かしげに俯き、大きな体を縮め、両手の指を胸の前でからませるビャクヤ。なんだか少し可愛い。
対して、恥かしがるでもなく堂々と、むしろ誇らしげにすら見える笑みを浮かべているカワムラ。なんだか少し格好良い。
「これを婚約と言わずに何て言うの?」
「……………」
ビャクヤはすっかり小さくなって、完全に下を向いている。
…婚約者って、どうやら冗談ではないらしい。
少なくとも、カワムラは本気に見えるし、ビャクヤの反応を見れば、彼もカワムラを嫌ってはいない事が解る。
「…と、とりあえず…。教えておきたい事があるから、僕とヨルヒコ君はひとまず外へ…」
ビャクヤは俯いたままボソボソと言うと、足早に部屋を横切り、ドアから出て行った。
ふと見ると、カワムラは、これまでに俺が見た事の無い、優しい笑みを浮かべていた。
「…あらあら照れちゃって…、可愛いんだから…!」
俺は彼女の呟きに思わず苦笑しつつ、ビャクヤの後を追って外に出た。
「…本気らしいんだよね…、アサヒちゃん…」
テラスの長椅子に座ったビャクヤは、タバコをくゆらせながら、困ったように呟いた。
俺は手すりにもたれかかり、そんなビャクヤを見つめる。
「何も僕なんかでなくとも、学校で恋人を見つければいいのに…。可愛いんだから、モテると思うんだけどなぁ…」
「可愛いとは思ってるんだな?カワムラの事」
俺がニヤッとしながら言うと、ビャクヤは「しまった!」とでも言うように口を引き結び、俺を見た。
「確かにモテるよ。カワムラは学校一の美人だ」
俺はそう言いつつ、ビャクヤの隣に腰を降ろす。
「でも、プロポーズした男はことごとくふられた。理想が高いのか、それとも恋愛に興味が無いのか、ずっと謎だったけど…、
やっと解ったよ」
俺はビャクヤに笑みを向けた。
「心に決めた相手が居るから、誰とも付き合わなかったんだな、あいつは」
「…もしも、恋人ができなかったら付き合おう…。アサヒちゃんにそう言った事がある…。そう言ったのに…。恋人を作ろう
ともしなかっただなんて…」
ビャクヤはため息をついた。
「何処が良いんだろうねぇ…。太ってて、毛深くて、人間ですらない、おまけに歳も離れてる僕なんかの何処が…」
「歳なんて、少々離れてても、案外気にしないものだぞ?」
「35と18でも?」
「それぐらい…、さんじゅうご!?」
俺は驚いてビャクヤを見る。姿は獣だから外見での年齢は判らないが、声の感じや喋り方から、もっと若いものと思ってい
たのだが…。
「そうは思えなかったな…。声の感じとかから、それよりも若く思えてた…。てっきり二十代前半だと…」
「ははは。ありがとう。まあ、僕らの寿命は人間の1.5倍くらいだから、人間で言えば大体それぐらいになるかな」
ビャクヤはそう言うと、懐かしむように目を細めた。
「初めてアサヒちゃんと出会ったのは、彼女が幼稚園児だった頃…、11年と少し前の事だ。今でも、ついこの間の事のよう
に思い出せるよ…」
そして目を閉じると、小さな声で呟いた。
「…この山に住み着いて、もう13年か…。元気にしているかな…、ヤチ…」
…寂しそうな…、声だった…。
ビャクヤは、望んでこんな山奥で暮らしている訳じゃないんだと、何となく解った。
彼はさっき、人の姿を否定したと、人の姿になる事はできないと言っていた。
きっとそのせいで、こうして身を隠して生きているんだろう…。
ビャクヤの指示通り、俺は昨日借りたのと同じ服に身を包んだ。
ぶかぶかのティーシャツにハーフパンツ、ビャクヤのものだ。
はっきり言って寒いが、これからおこなうトレーニングは、ゆったりした服でないといけないらしい。
着替えを終えた俺が表に出ると、
「それじゃあ、まずは基礎的な所から覚えて貰おうかな」
ドアの脇に立ってタバコをふかしていたビャクヤは、木のステップを下り、小屋の前のならされた地面に立った。
俺もその後に続き、ビャクヤの背に問い掛ける。
「基礎的な事って?」
「形態変化のコントロールさ」
向き直ったビャクヤは、意味が解らず首を傾げた俺を見て、一つ頷いた。
「獣としての形態と、人間としての形態間の変化…、つまりは変身だね。まずはこれを覚えて貰うよ」
なるほど、それで昨日と同じ服装にしたのか…。
確かに俺が着てきたトレーナーとジャケット、特にジーパンは、制服と同じように、間違いなく破れてしまうだろう。
ビャクヤの話では、ライカンスロープというものは、半人半獣の姿こそが本来の姿らしい。
人間の姿をとり続ける事はエネルギーの消耗を加速させ、身体や精神に負担をかけてしまうとの事だった。
生まれてこの方18年、ライカンスロープとして覚醒しなかった俺は非常に希なそうだが、一度変身を経験した以上、これ
までのようにずっと人間の姿を維持するのは難しくなって来るらしい。
「圧迫感とか感じないかい?少しきつめの服を着ているような、そういった感じ」
ビャクヤの言葉に、少し考えた後、俺は頷いていた。
言われてみればそんな感じもする。一昨日、狼男のようになった時の開放感を思えば、確かになんとなく窮屈な感じが…。
「今はまだ我慢できない程じゃないだろうし、それほど気にもならないと思うけれど、長く人間の姿で居れば圧迫感は徐々に
増して来る。限界が来れば意識が緩んだ途端に勝手に獣の本性が現れてしまう。人間の姿を維持するのは、あくまでも意志の
力による束縛だからね。例えば、あまり我慢していると寝ている間に体が勝手に変身してしまう事もある」
「夢精みたいなものかな…?」
俺の言葉にビャクヤは苦笑混じりに頷いた。
「まぁ、確かに似ているね…。それと同じで、防ぐためには体にも息抜きをさせてあげなければいけないんだ」
なるほど。それは納得できる。
「これからは、その変身の練習をして貰う事になる。自分自身の体をしっかり把握しておけば、人間社会での生活も続けられ
るからね」
…そうだった!これからの生活では、ライカンスロープである事がばれないように、気を付けていかなければいけないんだ…!
「納得できたなら、さっそく始めようか?もっとも、変身は一昨日一度やっているんだから、それほど難しくはないと思うよ」
ビャクヤは微笑み、俺への変身指導を開始した。
「鼓動を把握して、体を流れる血の道筋を捉え、力の巡りに神経を集中させて…」
座禅を組んでいた俺は、ビャクヤの声に従い、鼓動を、血液の流れを、それに乗って体の隅々まで行き渡る力の動きを把握する。
「昨日全身を縛るのをイメージした時とは逆に、束縛を解く事をイメージするんだ」
血流や力の流れを捉える事までは上手く行った。がしかし、俺は束縛を解くという事に手こずっていた。
「焦らなくて良いよ。君は18年人間の姿のままだったんだ。体そのものが変化に対して慣れていないからね」
励まされながらも、俺は意地になって集中する。額に汗が滲み、頬を伝う。
しばらくすると、ビャクヤは見かねたように口を開いた。
「一度休憩しよう。根を詰め過ぎても上手く行かないものだからね」
目を開け、ため息をつきながら、額の汗を腕で拭う。
どうにも上手く行かない…。束縛を解くというイメージが、なかなか掴めないんだ…。
ビャクヤは「う〜ん…」と唸り、困ったように頬を掻く。
「僕が変身できる体だったら、例を見せて誘導してあげる事も出来るんだけど…、こればかりは手助けのしようが無いなあ…。
一度自分の意志で変身してしまえば、あとは楽にできるようになるはずだけれど…」
「一昨日は気付いた時にはもう変身していたから…、どうなっていたのかさっぱり判らないんだ…」
「だろうねえ…」
ビャクヤは腕組みしてしばらく考えた後、
「参考になるかどうかは判らないけれど…」
と、口を開いた。
「束縛を解き放つ際に、明確なヴィジョンをイメージするという方法を使う者も居る」
「明確な…、ヴィジョン?」
「うん。例えば、自分を縛り付けるロープが解ける様子なんかをね」
俺はビャクヤの言葉を反芻し、頷いた。
「やってみる」
俺は姿勢を正し、目を閉じて深呼吸した。
慣れてきているのだろう。血と力の掌握はすぐにできた。…問題はこの後だ。
俺は目を閉じたまま、体にまとわりつくある物をイメージした。
それは、冷たく、重く、ジャラジャラと音を立て、全身に絡み、四肢を縛り付ける、大きな南京錠のついた鎖だ。
何かの映画で見た、鎖に縛られた獣、そのワンシーン…。
一度目で見たものだから、明確なヴィジョンとしてイメージするのは難しくは無かった。
俺は全身を縛るその鎖が、映画の中でそうだったように、獣によって引き千切られる様子をイメージする。
歪んで弾け飛ぶ南京錠。千切れて散らばる鎖。それらの立てる騒々しい音までも想像した途端、ドクンと、体が震えた。
体中が心臓そのものになり、脈動したような強い鼓動。
実際には心臓が、普段では有り得ない程に強く脈動したんだろう。
体の隅々まで力が行き渡り、体が火照って熱くなる。まるでかじかんでいた手足がほぐれるような感覚…。
俺の身体が、手足が、細胞の一つ一つが、束縛からの解放に歓喜を叫ぶ。快感すら伴った強烈な開放感…。
全身がむず痒くなり、成功を悟った俺は目を開けた。
手足から銀の被毛が生え出し、瞬く間に肌が見えなくなる。
全身の筋肉が膨張し、骨格はメキメキと音を立てて変形する。
手足が変形し、それぞれの指から鋭い爪が伸びる。
鼻と顎が前にせり出し、伸びた尾てい骨が尻尾を形作る。
頭の上に移動した耳は即座に周囲の細かな音まで捉え始め、湿った鼻は大気の中を漂う微細な粒子までを拾い集める。
より鮮明な視覚情報を脳に送り込むようになった両目が、笑みを浮かべて拍手するビャクヤの顔にピントを合わせた。
「おめでとう。初の自意識下での変身だね」
「…どうも…」
一昨日この姿になった時は、戸惑いと焦りしか感じなかったけど、人間の姿に戻れる事を知ったせいか、今回はただただこ
ちらの姿での感覚に驚いていた。
…とにかく、全てが鮮明だ…。
視覚、聴覚、嗅覚…。人間の姿で感じていた時の数倍、いや、数十倍鮮明に、細かく感じ取れる。
両目が映す景色は、連なる木々の葉の一枚一枚、影の中の葉脈に至るまでが鮮明に見えている。
ピンと三角に立った両耳は、葉ずれの音や風の音を一つ一つバラバラに拾い上げ、集中すれば遙か彼方から風が運ぶ、車の
エンジン音まで捉える事ができる。
驚きなのは鼻だ。息吹始めた春の命、新芽の香りや針のような杉の葉の匂い、空気に漂い出る土や風の中の微細な粒子の存
在まで、舌で味わうように感じられる。
触覚も鋭敏化している。全身を覆う銀の毛皮が、木々の中をすり抜けてゆく風の動きまでを、細やかに捉えて伝えて来る。
驚くべきは、それらの膨大かつ精密な情報を、必要な物と不必要な物とに細かく分けて感じ取れる事だ。
周囲の物事を細やかに捉えながらも、決して過剰な情報で騒々しくはならない。
「感覚の鋭敏化に加えて、脳の情報処理能力も格段に向上しているんだ。人狼の姿を取り戻した今の君は、普通の人間が捉え
ることのできない世界を感じる事ができる」
ビャクヤの言うことももっともだ。ついさっきまで人間の姿で捉えていた周囲の情報が、まるでもやがかかった、漠然とし
た感覚のように感じられていた。
「さて、そこから先はまた今度にするとして、二つだけ注意しておきたい」
ビャクヤは口調を改め、俺の顔を見つめた。
「一つ目は、人間の血肉を口にしないこと」
「へ?」
俺は首を傾げた。だってそうだろう?人間の血や肉なんて、何だって食べなきゃ…、あ。
「怪我したからって、傷を舐めたりするなって事か?」
「いいや」
思いついたことを尋ねたら、ビャクヤは首を横に振った。
「君自身は酷なようだけど人間じゃない。傷を舐めたっていいさ」
ますます解らない…。なら人間の血や肉を口に入れる機会なんて…。
困惑している俺に、ビャクヤは真面目な口調で、その衝撃的な言葉を続けた。
「もしもこれから先、君がそんな衝動に襲われたとしても…。決して、人間を食べてはいけない」
ビャクヤの言葉の意味が頭の中に入るまで、少しかかった。
「…ビャクヤ…」
俺は、恐る恐る訊いてみた。
「俺は…、人間を襲うように、なるのか…?」
恐怖。そう、この時、俺の心に満ちていたのは、強い恐怖と嫌悪だった。
俺は、人狼はつまり、映画で見た狼男みたいに、人を…、襲う…!?
「その可能性もゼロじゃないって事さ。君の場合は確率は低いけれどね」
恐怖で凍りついた俺に、ビャクヤは優しい口調で言った。
「ライカンスロープは、本能的に人間の血肉を求める。人間の血肉にはね、僕らライカンスロープの力を何倍にも引き上げる
効果があるんだ」
そう言った白犬は、少し俯いた。
「ただ、人間の血肉には強力な依存性がある。力を求めて、あげく「人中毒」になって、本物の獣になってしまったライカン
スロープを、僕は何人も知ってる…」
長い前髪で隠れ、その目がどんな感情を映しているのかは判らない。
「でも、たぶん君は大丈夫だ」
ビャクヤは顔を上げ、少し微笑んで俺の顔を見つめた。
「君は長い事、人間社会の中で生きてきた。人のモラルが、その禁忌を忌避してくれる」
「…でも…、舐めたりしても、危ないんだろう?」
俺の問いに、しかしビャクヤは小さくかぶりを振った。
「舐める程度じゃどうって事はないよ。…そうだね、コップ一杯もの血を飲めば、一掴みほどの肉を口にすれば、たぶん酒に
酔ったような感覚と、全能感を覚える」
判りにくい例えに、俺は顔を顰めた。
「酒なんて飲んだ事ないから判らないぞ?」
「っと、そうだったね…。まぁ、目安として、一口食べたらアウト。そう考えて欲しい」
ビャクヤは苦笑いし、俺は何とは無く理解して頷いた。
決して人間の血や肉を口にしてはいけない。守るのは簡単だ。誰が好きこのんで食うか…!
「そしてもう一つ…」
ビャクヤは表情を引き締め、じっと俺の目を見つめた。
「やむを得ない場合を除いて、その姿で生物を殺してはいけない」
「殺すって…、普通はそんな事は…」
「ないだろうね。でも、肝に銘じておいて欲しい。君がその姿で何かに致命傷を与えたとする。その場合相手は…」
ビャクヤは一度言葉を切り、重々しい口調で、囁くように言った。
「死ぬ事ができなくなってしまう」
ゆっくりとビャクヤが言ったその言葉が、じわりと、胸の奥へ染みこんで来た。
「それは、どういう…?」
聞き返そうとした瞬間、俺は思い出した。
黒猫…。一昨日の夜、俺が傷つけ、重傷を負いながらも、しばらく生き続けていた黒猫のライカンスロープ。
喉を食い千切られ、胸に風穴をあけられ、それでも生きていたあの黒猫…。
背骨に氷柱でも差し込まれたような寒気を覚え、総毛立った。
…生きていたんじゃない…。あいつは、その…、…死ねなかった…?
「…カース・オブ・ウルブス…」
ビャクヤが呟いた。
「人狼というのは、多種多様なライカンスロープの中でも、特に恐れられている存在だ。その理由の一つがカース・オブ・ウ
ルブス…、「人狼の呪い」と呼ばれる特殊な力を持つ事」
「人狼の…、呪い…?」
呟いた俺に、ビャクヤは頷いた。
「人狼の呪いを受けて破壊された者は、魂を肉体に縛り付けられ、その身が完全に朽ち果てるか、呪いを解除されるその時ま
で、死ぬ事は許されない。死に至った傷の痛みにさいなまれながら、真の消滅を迎えるその時まで、意識を失う事も無く、ひ
たすら苦しみ続ける事になる」
…呪い…?
あいつは、俺の呪いによって死ねなくなっていた?
そして、ビャクヤがあの時に俺にやらせた事は、その呪いの解除だった…?
「…うっ…!」
俺は吐き気を覚え、口元に手を当てた。
…俺は、…俺は…、やっぱり、人を殺してたのか…!?
地面に跪き、背を丸めてえづく。
ビャクヤは屈み込み、そんな俺の肩に手を当て、静かに言った。
「…気に病むな…、というのは難しいかもしれないけれど、君にすれば正当防衛、彼にすれば自業自得だ。…殺すも止む無き
状況だった…。君が責任に感じる事は無いよ…」
ビャクヤの優しい声が、手の温もりが、今は何故か…、痛かった…。