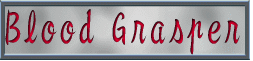
FILE6
小屋についた後、ビャクヤはオレに傷の修復の仕方を教えてくれた。
ただでさえ傷の治りが速いライカンスロープだが、力を消耗するものの、意図的に傷を高速修復する能力も備えているらしい。
実際にビャクヤの指示通りに意識を集中させる事で、俺の左腕はメキメキと音を立てて飛び出した骨を収納し、瞬く間に繋
いで、傷口を閉じてしまった。
驚いた事に、完全に傷が消えるまで、わずか一分ほどの出来事だった。
傷の修復を終えた俺をリビングの椅子に座らせ、向かいに座ったビャクヤは小さく息を吐き出した。
テーブルには、ビャクヤがいれてくれた、熱いココアが入ったマグカップが置いてある。
俺は黙ったまま、カップから立ち上る湯気越しに、何かを思い悩んでいるようなビャクヤを見つめた。
「…明日からは…、君に生き残るための力の使い方を教えよう…」
しばらく沈黙した後にそう言ったビャクヤは、少し哀しそうだった。
「…本当はね…、その体の性能の引き出し方を教えるだけに留めて、闘争の手段までは教えたくはなかったんだ…。人間の中
に混じって、静かに暮らしていけるなら、必要の無い事だと思っていたから…」
ビャクヤはそう言うと、俺に向かって手を広げ、三本の指を立てた。
「明日からは、身体能力の制御、人狼固有の能力の使い方、そして闘い方…、この三つを覚えて貰う事にするよ」
戸惑いながら頷くと、ビャクヤは「ふうっ…」と息を吐き出した。
「闘争が起こらないに越した事はないけれど、もしも今日のような事態に陥った時、また僕の助けが間に合わない事もあるか
もしれない…。その時の為に、あくまでも念の為だけれど、闘い方を覚えておいて欲しい…」
「…判った…。…ごめん…、ビャクヤ…」
俺は何と謝っていいのか判らず、ただただ申し訳ない気持ちで一杯になり、項垂れた…。
「それともう一つ、相手の事も話しておくよ」
俺は顔を上げ、ビャクヤを見つめた。
「相麻製薬…、知っているよね?」
俺はもちろん頷く。この田舎町に進出してきた巨大企業、あそこのおかげで町は活性化し、賑やかになりつつある。
「あのライカンスロープのような連中は、相麻製薬の者だよ」
「何だって!?」
俺は驚きのあまり、反射的に立ち上がっていた。
脚に当たった木の椅子がひっくりかえり、騒々しく床に転がる。
「驚くのも無理はないよね。アサヒちゃんから聞いたけれど、ここ三年くらいで一気に成長した新進の製薬会社なんだってね?
あそこ…。僕は全然知らなかったけれど」
そう。いまや薬局に行けば「ソーマ」のロゴの入った薬はどの棚でも見かけるし、テレビを付ければしょっちゅうCMが流れ
ている。
そんな大企業と、ライカンスロープなんていうオカルトめいた存在に繋がりがあるなどとは、イメージとしてどうにも結び
つかなかった。
「なんで…、製薬会社なんかが…」
やっとの事でかすれた声を絞り出した俺に、ビャクヤは肩を竦めた。
「製薬会社だからこそ、だよ…。実は以前、13年以上も前の事だけれど、ライカンスロープの存在を知ったある製薬会社が、
極秘に僕らの同種を狩っていた事があるんだ…」
ビャクヤに座るように促され、俺は椅子を直して再び腰掛ける。
「ライカンスロープというのは、人間から見れば驚異的な存在だ。身体能力、生命力、僅かながらも人間を超える寿命…。こ
れらを研究すれば、人間を本質から変える事ができるかもしれない…。もしかしたら不老不死の存在になれるかもしれない…」
「そんな…夢みたいな事…」
言いながらも、俺は納得しかけていた。
不老長寿の薬の話や、それを追い求めた中国の皇帝の話、そんな事は結構色々な所で読んだり聞いたりする。
…永遠…。多くの者が憧れる言葉だ…。
「現在の製薬会社だけじゃなく、遥か昔から様々な人物が取り組んできた課題だよ。医者、学者、錬金術師、宗教家…、ライ
カンスロープは恐れられる存在であると同時に、一部の者にとっては、危険ながらも魅力的な研究材料だった」
「研究材料…?」
「うん。事実、13年前に消滅したその会社は、僕らの同種を使って色々な実験をしていた。解剖、投薬実験は当り前、器官
を摘出して人間に移植するなんていう事までやっていたらしい」
「いしょ…く…!?」
吐き気が込み上げ、俺は口元を覆った。
人間があさましい生き物だということは知っている。知っているつもりだ。
だが、ビャクヤが語る、ライカンスロープから見た異種としての人間の行いは…、自分が人間だと信じて18年生きてきて、
今もなお、どちらかといえばライカンスロープの自覚に乏しく、人間としての意識が強い俺にとって、耐え難いほどにおぞま
しい物に思えた。
捕らえられた自分が、ついこの間まで自分もその一員だと思っていた人間の手によって、監禁され、研究され、実験動物並
みの扱いを受ける様子を想像すると、おぞましさと恐怖に胃が痙攣しそうになる。
「大丈夫かい?」
「う、うん…。続けてくれ…」
気遣うような視線を向けたビャクヤに、俺は頷いた。
「それじゃあ…話を戻すよ?相麻は僕や君のようなライカンスロープを捕らえ、何かをしようとしている。…いや、すでに何
かを始め、いくばくかの成果を上げている。最終的な目的までは判らないけれど、おそらくは君をそうしようとしたように、
ライカンスロープを狩り集めるのが当面の目的らしい」
「狩って、実験に使うのか?一体どんな事を研究してるんだ…?」
「少なくとも、毛生え薬なんかの平和的な研究の為じゃあないだろうねぇ」
ビャクヤはつまらなそうに肩を竦める。…こんな状況で冗談を飛ばせる図太い神経が羨ましい…。
「やっぱり、不老不死とか、そういう…?」
「だとは思うけれど…、成果の一部を見るに、それだけでもなさそうだね」
…ん…?俺はビャクヤの言葉に引っかかるものを感じた。
…成果の一部を見るに…?…そういえばさっきも、いくばくかの成果を上げているとか言っていたような…?
「成果って何だ?あいつらの研究の成果って、ビャクヤは何か知ってるのか?」
尋ねる俺に、ビャクヤは目を伏せながら頷き、静かな声で言う。
「君がこれまでに出会った、五人の、相麻のライカンスロープ…。覚えているね?」
「…ああ…」
顔を思い出しながら頷くと、白犬は深く息を吐き出した。
「…彼らが、相麻の研究の成果さ…」
「あいつらが、成果…?」
意味が判らず問いかけようとした俺は、ふと思いついた事を口にした。
「ドーピングしてたとか?」
ビャクヤは目を丸くする。…やっぱり違うか。
「近いかもね。人為的な強化という意味では…」
「…え…?」
首を傾げた俺に、ビャクヤは沈黙した。
言うべきかどうか迷っている…、そんな感じだったけれど、結局、ビャクヤは意を決したように小さく頷いて、口を開いた。
「彼らは、人造のライカンスロープだよ」
俺は言葉も無く、ただただ目を見開き、ビャクヤの顔を見つめていた。
窓を揺する風の音が、急に強くなった気がした…。
「人造の…、ライカンスロープ…?」
オウム返しに聞き返した俺に、ビャクヤは静かに頷いた。
「彼らは、君や僕のような、生まれつきのライカンスロープじゃない。何らかの人為的な手段で、後天的にライカンスロープ
としての能力を獲得した存在だ。だから普通のライカンスロープとは違う奇妙な匂いがしていたよ。…何か異質なもので割っ
たような…、奇妙な気配がね…」
俺には普通のライカンスロープの匂いというものが判らない。
ビャクヤはあの香水で常にライカンスロープの匂いを消しているので、俺はあいつらからしか嗅ぎ取った事ないんだ。だか
ら普通とはどう違うのかは良く判らないんだが…。
考えて見れば、ビャクヤはさっきあいつらの事を「ライカンスロープのような連中」と言った。つまり、ライカンスロープ
と似た、でもライカンスロープそのものではない存在…。
考え込んでいた俺は、ある事に気付いた。
生まれつきのライカンスロープではない、人為的にライカンスロープの能力を得た存在…。…元々はライカンスロープじゃ
ない…、それなら元は?あいつらの元は何だ?
「…ビャクヤ。あいつら、元々は…?」
俺が全て言わなくとも、ビャクヤは質問の内容を察してくれた。
「生粋の人間だろうね」
予想したとはいえ、驚きは大きかった。
好きこのんでライカンスロープになる?何のために?
もしも俺が、普通の人間に戻れる方法があるとすれば、間違いなくその方法に縋る。
なのに、人間である事をやめ、ライカンスロープになりたがる連中が居る…。信じ難かった…。
「なんで、そんな真似を…」
「さぁてね…。生まれた時からライカンスロープとして生きてきた僕には判らないけれど…、あるいは先人達のように、人間
を越えた生命力に憧れたのかもね…」
ビャクヤはそう言うと、席を立った。
「さて、話はひとまずここまでにして、夕食にしようか。一度に話すには情報が複雑で多過ぎるからね」
かまどに歩み寄って、暖めていたシチューをよそい分けるビャクヤに、俺も立ち上がって声をかけた。
「手伝うよ。何をすればいい?」
戦いと傷の修復で体力が失われたせいか、正直なところへとへとだったけれど、じっとしていたくなかった。
動いていないと、なんだかそこらじゅうから伸びてくる見えない手に絡め取られて、動けなくなってしまうような気がして…。
銀狼の姿のまま風呂を借りて、浴室の窓から、普段よりもはっきり見える月を見上げたら、ふと、以前授業で習った山月記
という作品の事を思い出した。
確か中国の話で、ある男が虎になってしまう話…。
虎になった男が、再会したかつての知り合いに内心を吐露する物語…。
なんとも現実離れした話だと思って、なんで教科書に載せられていたのか理解に苦しんだが、今ならば少し理解できるかも
しれない。
…獣に変わってしまった我が身を忌む。変わってしまって戻れなくて、以前を振り返る。その気持ちは何となく解る…。
ビャクヤに出会い、こうして色々な事を教えて貰えなければ、俺も人を避け、山野を彷徨うしかなかっただろう…。
…いや、そもそも逃げ切れずにあいつらに捕らえられて、実験生物になっていたか…。
あるいはあの物語…、ひょっとして、ライカンスロープとして目覚めてしまった男を題材にした、実際にあった事を元にし
た物語なんじゃないんだろうか…?
そんな事を考えたら、これまでに見聞きした様々な物語、人が獣に変ずる話や、その逆の話が、今までとは違った印象で捉
えられた。
俺は借りたベッドに横たわり、天井を見上げてまどろんでいた。
変身はしたままだ。ここに居る間は、ビャクヤに合わせてなるべくライカンスロープとしての姿で居ようと思うから。
それと、人間の姿のままで居るのと違い、体や精神がリラックスできると聞いたからというのもある。
色々な話をした。あまりにもたくさんの事を話したせいか、頭の中でそれらがグルグルと巡っていた。
それでも俺はやっぱり疲れていたんだろう、程無く、眠りに落ちていった…。
樹上から馬が飛び掛り、俺は身を伏せてそれをかわす。
地面に伏せた俺に、枯れ草の中を這うようにして近づいた黒猫が飛びかかる。
転がって避け、必死に逃げる俺に、容赦なく二頭が迫る。
胸に大穴をあけ、喉をごっそりと食い千切られた黒猫が…。
左腕を根本から失い、胴体を半ばまで切り裂かれた馬が…。
こけつまろびつ森の中を逃げ惑う俺を、容赦なく、恨みの声を上げながら追い立てる。
痛かったと…、苦しかったと…、…よくも俺達を殺したな…と…。
「うわぁぁぁぁぁああああっ!?」
跳ね起きた俺は、人狼の本能がそうさせたのか、ベッドから飛び降り、床に四つんばいになっていた。
「はっ…!はぁっ…!はっ…!はっ…!」
自分の荒い呼吸を聞きながら、周囲を見回す。
夢だったと実感するまで、数秒かかった。
ベッドの下から、あるいは窓から、今にもあいつらの顔が覗くような気がした。
不意にドアがノックされ、俺はビクリと身を竦ませてドアを振り返る。
「…大丈夫かい?うなされていたみたいだけど…」
荒い息をついている俺を見て、開いたドアの向こう、逆光の中のビャクヤは目を細めた。
廊下はうっすらと明るい。リビングのランプはまだ落とされていないんだろう。まだ起きていたビャクヤは、俺の声を聞い
て確認しに来たのか…。
「大丈夫…、ちょっと、嫌な夢を見ただけで…」
俺がなんとかそう答えると、ビャクヤは静かに部屋に入ってきた。そして俺の前で立ち止まり、すっと手を上げ、俺の目尻
を指で拭う。
泣いていた事に、俺は初めて気がついた…。
恐怖。後悔。罪悪感…。
胸を締め付けられるような気分で項垂れた俺を、ビャクヤはそっと、優しく抱き締めてくれた。
「ごめんね…。ボクがもうちょっと早く着いていれば、君にあんな真似をさせないで済んだのに…」
ビャクヤはそう謝った。…謝ることなんて何も無い、ビャクヤは何も、悪くないのに…。
「…ビャクヤ…」
俺はビャクヤの胸に顔を押し付け、声を押し殺して泣いた。
「っく…う…!ふ、うふぅうっ…!」
不安と恐怖で押し潰されそうになっている情けない俺の背を、ビャクヤは優しく撫でてくれた。
フカフカの毛に被われた、思いの外柔らかい、少し太り気味の体…。
ビャクヤの体は、温かくて、柔らかくて、優しくて、抱き締められると柔らかい羽毛に包み込まれるようで、安心できた…。
「一つ、昔話をしようか…」
眠れない俺と並び、ベッドに腰掛けたビャクヤは、そう切り出した。
今から二十年以上も前、ある町に、一人のライカンスロープの少年が居た。
父を知らず、母を知らず、決して治安の良いとは言えない町で育ったその少年は、俺と同じ銀色の人狼だった。
その銀の人狼と出会ったビャクヤは、彼を当時の自分の仲間達の元へと連れ帰った。
抜き身の刃物のようなギラギラしたその少年は、他者を警戒し、近付けないようにしていたが、仲間と触れ合ってゆく中で、
少しずつ変わってゆく。
そしていつしか、仲間達を護る狩人として信頼され、その信頼に応えようとするように、仲間を大切にする青年へと成長し
て行ったそうだ。
「少々無鉄砲で無愛想だった彼はね、敵に対して一切の容赦をしない、一見冷徹に見えるほどの鋼のような意思と、仲間のた
めに我が身を投げ出す、無謀とも言えるほどの献身さを併せ持っていた」
その人狼の事を話すビャクヤの横顔は、慈愛に満ちていて、そしてどこか誇らしげでもあった。
「きっと君の中にも、苛烈さと、情の深さが同居しているんだろう。君の場合は人間として生きてきた時間が長いせいで、苛
烈さが押さえ込まれているようだけれどね…」
ビャクヤはそう言うと、俺の目を見つめ、微笑んだ。
「…辛いと思うよ…。でも、命を奪う事に抵抗を感じるのは、決して悪い事じゃない。ただ、僕個人の考えで言わせて貰うな
ら、自分の身を滅ぼしかねないような優しさは、持たないで欲しい」
ビャクヤの大きな手が、俺の頭を優しく撫でた。
「僕は、君に死んで欲しくはないからね」
「ビャクヤ…」
「だからこそ、闘い方を教えてあげるんだ。いざという時には、苦しくても、辛くても、躊躇わずに敵を仕留められる方法と
心構えをね…。さあ、もうお休み。明日は少しきつめのトレーニングになるからね」
立ち上がり、俺の頭をくしゃくしゃと撫でると、ビャクヤはベッドから離れてドアに向かった。
「ビャクヤ!」
「うん?」
振り返ったビャクヤに、俺は尋ねてみた。
「その人狼、今はどうしてるんだ?」
「…さてね…。もう13年も会っていないから…。でもきっと、幸せに暮らしていると思う。…そう、願ってる…」
少し寂しげに微笑んだビャクヤに、俺はもう一つ尋ねてみた。
「その人狼、俺と似ていたのか?」
「雰囲気はだいぶ違うけれど、外見は良く似ているね。別れた時の彼は、今の君と同じ18歳だった」
…そうか…。俺と同じ歳の時には、もう戦う力を持っていたのか…。
俺の考えている事を見透かしたように、ビャクヤは口を開いた。
「一緒に考える必要は無いよ?彼には幼い頃からライカンスロープだという自覚があった。生殺に関する観念自体が、普通よ
りも一歩も二歩も突き抜けた所にあったからね」
ビャクヤはそう言って笑うと、ドアを開け、廊下に出た。
「それじゃあ、お休みヨルヒコ君」
「あ、待って!ビャクヤ!」
ビャクヤは閉じかけたドアを止め、俺を見つめた。
「あの…、俺の事も、呼び捨てにしてくれないか?」
ビャクヤは少し黙った後、ふっと優しい笑みを浮かべた。
「解ったよ。お休み、ヨルヒコ」
「ああ。お休みビャクヤ…」
ゆっくりとドアが閉じられ、部屋が暗くなると、俺はベッドの上に身を投げ出した。
今の俺と同じ歳で、戦いに日々を費やしていた人狼…。
俺も、彼のような誇り高く、強い人狼になれるだろうか?
仲間を護るために自分の手を汚すことも厭わない、そんな風になれるだろうか?
ビャクヤが誇らしげに他人に語って聞かせるような、そんな男になれるだろうか…?
…しまった…。…その人狼の名前…、まだ聞いてなかったな…。
そんな事を考えている内に、ビャクヤと話して落ち着いたせいか、俺は再びまどろみ、今度こそ深い眠りへと落ちていった…。
「おはようビャクヤ」
リビングに入った俺を振り返り、朝食の支度をしていたんだろうビャクヤは、いつものように穏やかな笑みを浮かべた。
「おはよう、ヨルヒコ。ちょうど朝食が出来上がったところだから、そこに座って」
…昨夜の事、覚えてくれていたんだ…。呼び捨てで呼んでもらえた俺は、少し嬉しくなってビャクヤに歩み寄った。なんだ
か、少し距離が縮んだような気がして…。
「運ぶの手伝うよ」
俺はビャクヤと並び、かまどの中につっこんであった鳥肉と野菜の串焼きや、鍋からよそった味噌汁をテーブルに運び始める。
『頂きます』
声を揃えて食事にとりかかると、俺とビャクヤは、時折笑いすら交え、他愛の無い会話を楽しんだ。
一晩眠って落ち着いた。
俺は、自分がやった事を受け止める。
自分が生き延びるために、二人も殺めてしまった事、生涯、決して忘れはしない。
あるいはこれから先も、生きる為に誰かの命を奪わなければいけない時が来るのかもしれない。
だとしても…、最悪の場合、この両手をまた血で染め上げる事になっても…、それを受け入れて、俺は生き延びなくちゃな
らない…。
ビャクヤが死んで欲しくないと言ってくれた。
それに、こんな俺でも、何かあれば母さんが悲しむ。
なにより、俺自身も、まだまだやりたい事がある。
…だから…、俺は生きたい…。
朝食後、ビャクヤは一度麓近くまで降り、カワムラを連れて帰って来た。
昨日の後の様子を確認したいのもあったので、念には念を入れて彼女を迎えに行ったのだ。
ビャクヤは、俺が二人目を殺めた事を、カワムラには話さなかった。
「昨日埋めた遺体は、掘り返されて、持ち去られていた…。恐らく、彼の仲間の仕業だろうね…」
カワムラが傍を離れた隙に、ビャクヤは声を潜めてそう教えてくれた。
ビャクヤは心配するなと言ってくれているけれど、きっと、このままでは済まないだろう。非人道的な実験を繰り返して、
不老不死なんかの研究をする連中が、不確定な敵対存在を放ったらかしにしておくとは思えない…。
俺は、強くならなければならない。
闘う力を手に入れなければならない。
これ以上ビャクヤに迷惑をかけない為にも、自力で生き延びられる力を付けなければならない…。
ビャクヤがまず教えてくれたのは、肉体の操作に関しての事だった。
昨日08と闘った際、俺も無意識に使っていた技術らしいが、ライカンスロープは肉体を局所的に強化したり、変形させた
りする事ができるそうだ。
爪を伸ばして鋭くし、それを硬化させたり、脚の筋肉を瞬間的に強化し、跳躍力を高めたり、細胞を活性化させて、傷を短
時間で修復したり…、実に多様な使い方ができる。
慣れてくれば、体内の鉄分やカルシウム等を集中させ、爪に金属と同等の硬度を持たせる事もできるようになるらしい。
にわかには信じられなかったが、
「ちょっと見ててくれるかな?」
と言ったビャクヤは、風呂用の薪に使う、太い木の幹を持ってきて地面に立てた。
直径20センチ、長さ30センチ程の木だ。
普段はマサカリで叩き割っているが、ビャクヤは何も持たずに木の前に立ち、右手を眼前に翳す。
ジャッと音がして、ビャクヤの白くて太い指の先で、爪が20センチほど伸びた。
そのパールホワイトの光沢を帯びた綺麗な爪が、じわりと根本から黒ずみ、ミキミキと音を立てて薄く、鋭く形を変える。
黒い、鋼鉄のような色に変わった五本の爪は、内側がまるでナイフのように鋭くなっていた。
ビャクヤは屈み込み、木の上に左手を置いて押さえると、右手を手首のスナップをきかせ、スッと動かした。
さほど力を込めたようには見えなかったが、ポン、と音がして、五箇所で切断され、輪切りになった木が地面に転がった。
「凄い…!」
転がった木の輪切りを手にとってみると、まるでバームクーヘン…。スポンジケーキを包丁で切ったような、綺麗な切り口
をしていた。
「僕や君のように、近接肉弾戦闘を得意とするライカンスロープは、まずは牙と爪の使い方から覚えるのが良いだろうね」
「俺は肉弾戦が得意なのか?」
そう問うと、ビャクヤは何故か少し面白そうに、口の端に笑みを浮かべて俺を見つめた。
「自覚が無いようだけれど、人狼はライカンスロープの中でも特に基礎身体能力が高く、数少ない「無音の領域」に達する事
ができる種なんだよ。ライカンスロープの中でも特に恐れられる理由の一つがそれ」
「無音の領域?」
俺が首を傾げると、ビャクヤはニッと笑って答えた。
「その気になった人狼は、弾丸並に速いのさ」