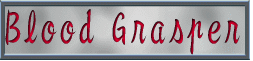
FILE7
「いつまでやってんのよ〜!?夕飯できたわよ〜!?」
突如響いたカワムラの声に、俺とビャクヤは揃って振り返る。
「ごめんごめん!すぐ行くよ〜」
腰に手を当てて頬を膨らませている少女に、ビャクヤは笑いながら応じると、俺を促して小屋へと歩き出す。
すっかり日が落ちているにも関わらず、人狼の目は夜目が利くせいか、暗くなったのも気にせずにトレーニングを続けてし
まった。
爪の伸縮や、折れた際の修復は何とかできるようになった。
硬質化はなかなか難しく、あまり強度を上げる事はできなかったが、初めてにしては上出来だとビャクヤが誉めてくれた。
今日はカレーらしい。小屋の中から良い香りが漂い出ている。
言ったら怒られるだろうから黙っているが、実はカワムラより、ビャクヤの作る飯のほうが美味い。
一人暮らしが長いせいか、ビャクヤは本当に何でもできるんだよな…。
「君のお母さんは、いつも家に居るのかい?」
ビャクヤの唐突な問いに、俺はカレーを頬張ったまま首を傾げた。カワムラも「ん?」と首を傾げている。
母は地元のスーパーでパートをしている。毎週決まった日が休みという訳じゃない。いつ休みになるかは毎月の予定表を参
考にするしかないけど…。
「いや、いつもっていう訳じゃないけれど…。何でだ?」
理由が解らずに聞き返した俺に、ビャクヤは小さく顎を引いて頷いた。
「一度会っておきたいんだ」
俺の手から落ちたスプーンが、皿の上で音を立てた。二人の視線が硬直した俺に注がれる。
ビャクヤが俺の母に会いたい?
彼が信頼できる男だという事は確かだ。普通なら喜んで母に紹介する。
だが、ビャクヤは人間の姿になれない。会わせようものなら、母がどんな反応をすることか…。
俺が困惑している事に気付いたんだろう。ビャクヤは小さく頷き、口を開いた。
「これまで黙っていたけれど、お母さんは、君が人間では無い事を知っているはずだ」
「…は?」
馬鹿みたいに口をぽかんと開けた俺に、ビャクヤは続けた。
「ライカンスロープはね、本来の姿で産まれて来る。つまりお母さんは、君を産み落とした時、人狼の赤子の姿を見ているんだ」
ビャクヤの言葉の意味を理解するまで、少しかかった。
「母さんは…、俺が人間じゃないと、知っていた…?」
掠れた声で聞き返した俺に、ビャクヤはまた頷く。
「ライカンスロープという種の名称や、存在の本質まで知っているとは限らないけれどね。…ついでに言えば、人狼は出生か
ら数時間で人間の4、5歳児程度の自我を持つ。…たぶん、君の場合は人間としての生活が長過ぎて、赤ん坊の頃の事が思い
出せなくなっているんだろうけれど…」
「何で…?何で母さんは俺に黙っていたんだ!?」
思わず立ち上がった俺を、ビャクヤは座るように手で促しつつ、何か思案するように目を細めた。
「そこは聞いてみるしかないけれど、恐らくは、話すべきじゃないと判断したんじゃないかな?…考えてごらん?ある日突然、
自分の親が「お前は人間じゃないんだよ」って言い出したら、どうだい?」
「冗談は顔だけにしろって笑い飛ばすわ」
俺が口を開く前にカワムラがそう応じた。
…頼むから大事なところで話の腰を折らないで欲しい…。
「まぁ、カワムラじゃないけれど、やっぱり信じないかな…」
やや憮然としながら俺が応じると、
「だろうね。逆に言えば、黙っていれば解らない事だと思っているのかもしれない…」
と言って、ビャクヤはまた小さく頷く。
「お母さんにも、君が置かれている状況を話しておくべきだろう…」
その夜、家に帰った後、俺は母の休日の予定を確認した。
ビャクヤには、まだ話を切り出すなと言われたので、それに従い、俺は今まで通りに母と接した。
だが、胸の内では、母が俺の事をどう考えているのかが、気になって気になって仕方がなかった…。
そして月曜がやって来た。
週末がやってくるまで、また悶々と過ごすのか…。
もはや卒業は目前で、授業の殆どは自習のような感じになっている。
俺はライカンスロープや相麻製薬の事ばかり、あれこれ考えて過ごした。
…進学か…。こんな状況になると、大学に通うために上京するのも少々考えさせられる…。
土日の内に、ビャクヤに相談しておくべきだったな…。
水曜日の昼休み、俺はいつものように混み合う学食を避け、体育館脇の自販機に飲み物を買いに行った。
ついでに近くのベンチで昼食を取るべく、弁当も持って来ている。
渡り廊下に設置されているこの自販機、実は品揃えがあまり良く無い。
なので部活の休憩など以外では、わざわざここを訪れる生徒は居ないのだ。
もっとも、俺が好きなザクロココア(友人内では見た目がグロい上にマズいと不評)はこの自販機にも置いてあるので、学
食の自販機で順番を待つよりは、ここに来た方が早い。
が、いつも誰も居ないこの自販機前に、今日は珍しく先客が居た。
「カワムラ?」
クラスメートであり、俺の窮地を救ってくれた恩人でもあり、同時に秘密を知る女子は、自販機の前で屈んで飲み物の缶を
取り出しながら、俺の顔を見上げた。
「珍しいな。ここで会うなんて」
「それはそうよ。入学してから三年間、ここに飲み物を買いに来た事なんて、数えるくらいしかないもの。イマイチなものし
か置いてないしね」
確かに。カワムラが今手にしているものも、そのイマイチな品の一つだ。
「飲んだ事ある?ドクダミオレ」
「…いや…」
「ドクダミは体に良い。…ってビャクヤが言っていたわ」
「あぁ、便秘に効くんだっけ」
素直に納得した俺を、何故かカワムラは顔を真っ赤にして睨んだ。…あれ?何かまずい事言ったか?
「…で、あんたは何しにここに来たのよ?」
「同じだ。飲み物を買いにだよ」
財布から硬貨を取り出し、ボタンを押すと、取り出し口にデフォルメされた鬼子母神が描かれた缶が転がり出る。
「…ネタ?何に使う気?」
俺が手にした缶を見て、カワムラが首を傾げる。
「飲むんだよ。決まってるだろ?」
「罰ゲーム用以外にそれを買う生徒…、初めて見たわ…」
眉を顰めて見つめてくるカワムラに、俺は「ふん!」と鼻を鳴らす。
「悪かったな。好きなんだよ」
俺達は何を話すでもなく、並んでベンチに腰掛け、缶を開けた。
他に人は居ない。今なら何を話しても大丈夫だろう。
「…なぁ。カワムラは、ビャクヤのどういうトコが好きなんだ?」
俺の問いに、カワムラはピタリと動きを止めた。
慌てたり、恥かしがったり、あるいは怒ったりするかとも思ったが、
「全部よ」
どうやら少し考えていただけらしい。いつもと変らない口調でそう答えた。
「初めて出会った時から今日この日まで、ビャクヤ以外のヒトと恋仲になる事なんて、考えた事もないわ。何があっても、ど
んなに困難でも、私はビャクヤと一緒になる。例え…」
カワムラは言葉を切り、そしてそれっきり後を続けようとはしなかった。
皆まで言わなくても判った。
ビャクヤを親に紹介し、結婚を認めて貰うのは難しい。…いや、おそらく無理だろう…。
そもそも、ビャクヤの存在を他の人間に知られるような事を、カワムラがするはずもない。
ビャクヤと一緒に生きるなら、あるいは家を捨て、人間社会から完全に離れなければならないのかもしれない。
…けれど…、果たしてビャクヤは、カワムラがそうなる事を望むだろうか…?
俺が考えたところで、仕方のない事なのかもしれないけれど…。
とにかく、今は一刻も早く力を付けることだ。
カワムラは何も言わないが、ビャクヤが俺の指導にかかっているせいで、寂しい思いをしてるのは間違いない。
まずは俺が、少しでも早く一人前になる事こそが、当面の二人の為になる事だろう…。
「何よ?静かになって?」
沈黙を破ったのは、自分が話を途中で切った事を棚に上げたカワムラだった。
「え?あ、いや…」
俺は少し口ごもった後、
「カワムラは、強いな…」
ぽつりと、そんな事を呟いていた。
「…は…?」
当のカワムラは、心底不思議そうに目を丸くし、俺の顔を見つめた。
午後の授業中も、カワムラと話した時に思った事をずっと考えていた。
そうしたら、居ても立ってもいられなくなった…。
ビャクヤとカワムラに迷惑をかけない為にも、一刻も早く力をつけたくて仕方がなかった。
それに、いつまた、相麻の連中と戦わなければならなくなるかもしれない。早く独り立ちしなければならない。
だから俺は、遅くなる事を母にメールで伝え、学校が終わり次第ビャクヤに会いに行く事にした。
愛用のマウンテンバイクを駆って農道を駆け抜けた俺は、またあの場所で車を見かけた。
だが、あのライトバンじゃない。赤い車体の普通車だ。
車の横には一人の若い女。…二十歳過ぎくらいだろうか?
濃いベージュのロングコートを羽織った女性は、寒々しい風の中、山に背を向け、田園を照らす夕陽を眺めていた。
鋭さと凛々しさを感じさせる切れ長の目。
細く、しかしくっきりした真っ直ぐな眉。
すっと通った鼻筋と、ふっくらした唇。
そして、夕陽で朱に染まった物憂げな表情…。
細められた目はどこか寂しげだが、憂いの表情すらも、その整った顔を魅力的に見せていた。
女は、ゆっくりと俺に視線を向けた。
「どうかしたのか?少年」
落ち着いた、涼やかな声でそう問われ、俺は自分が自転車を停め、女性に見入っていた事に今更ながら気付く。
「あ…、いえ…。何を見ているのかなと思って…」
しどろもどろに応じた俺から視線を逸らし、女性は再び夕焼けに目を細めた。
「夕陽を眺めていただけだ。あまり見る機会が無いのでね…」
女性は呟くようにそう言うと、再び俺に視線を向けた。
「少年は、この近くに住んでいるのか?」
「え?えぇ。割と近く…、かな?」
その女性があまりにも美人だったので、俺は少しドギマギしながら答えた。
「そうか…。私は、この町に来てからまだ日が浅くてな。この美しい景色を見るのも、実は今日が初めての事だ」
…美しい…?
幼い頃から見慣れていたせいか、こうして改めて言われるまで、俺はこの風景を美しいと思ったことは無かった。
…考えてもみれば、都会や、ある程度開発が進んだ所から見れば、こののどかな田舎町の風景は、自然が豊かな美しい景色
に見えるのかもしれない。
あるいは俺もこの町をしばらく離れて、それから戻って来たなら、この景色を美しいと感じるようになるんだろうか…。
「もしかして、相麻製薬の人なんですか?」
俺の問いに、女性は頷く。
「そうだが、何故そう思った?」
「この田舎に新しく来る人は、相麻の社員さんくらいですよ」
「田舎か…。そうかもしれないが、私には良い町に思える。騒がしい都会よりも、よほど環境が良い」
女性は深く息を吸い込みながら、微かに笑った。
きっとこの人は普通の社員なんだろう。相麻が影で何をしているかなんて知らない、普通の…。
日がもうじき落ちるが、女性には立ち去る気配は無い。
今日の所はビャクヤに会いに行くのは見合わせ、帰ることにした。
「それじゃあ、俺はそろそろ行きます。邪魔して済みませんでした」
「気を付けて帰りなさい。夜道は何かと物騒だからな」
軽く手を上げて女性に応じ、俺は自転車を走らせ始めた。
口調がなんとなく男っぽい。男っぽいっていうか、女軍人?なんだかそんな風に感じた。
凛々しくて、綺麗で、まるで…、人間に飼い慣らされていない、気高い野生の獣のような…。
そこまで考えた俺は、ふと可笑しくなって、小さく吹き出す。
ライカンスロープの俺が、人間の女の人に対して「獣のような」も無いだろう…。
ゆるく、大きくカーブする農道を回り、快調に自転車を飛ばして家に向かっていた俺は、一台の車とすれ違い、少し走った
後にマウンテンバイクを止めた。
…あのライトバンだ…!
やっぱりこの辺りを調べて回っているんだろう。08の遺体を発見した周辺を捜索するのは当然だ…!
ビャクヤは気付いているのか?警告に行くべきだろうか?
…いや、ビャクヤならこのくらいは想定しているだろう。下手につついてまたヘマをするよりは、大人しくこの場を離れて
おくべきか?
しばらく迷った後、俺は自転車を隠し、木立の中を移動し始めた。
変身はしない。見つかっても言い訳できるように、人間の姿のままだ。
馬鹿げているかもしれないが、ヤツらの動きに気付きながらも、恩のあるビャクヤに警戒を呼びかけないのは、あまりにも
礼を欠いた行為に思えたんだ。
周囲に気を配りながら慎重に山を登り、08を埋めた地点を大きく迂回してビャクヤの家を目指す。
もう三十分も登っただろうか?入念に周囲を確認した俺は、微かな物音に気付いた。
動きを止め、茂みに身を隠して息を潜める。
少しすると、俺が登ってきた後ろから、草をかき分けるがさがさという音が聞こえ始めた。
「何だ?何も居ないじゃないか…」
…男の声…。聞き覚えのある声だ。
これは、俺が初めて変身した晩、山中まで追ってきた犬のライカンスロープの声だ!
「おかしいな…、確かに見たと思ったのだが…」
犬の声に、別の声が応じる。
俺は茂みに身を潜めたまま、目を細めて声のする方向を覗った。
木々の間から降り注ぐ月明かりの下、熊と犬のライカンスロープの姿が見えた。
「匂いもしない。気のせいだったんだろうよ。大体この日没間際に、灯りも持たずに山を登る人間など居るはずもない」
犬はそう言いながら、確認するように風の匂いを嗅ぐ。
体だけでなく、衣類や荷物にまでふりかけている香水のおかげで、俺の匂いは嗅ぎ取れないだろう。…危ない所だった…。
「何をしている」
俺がひとまず安堵していると、また別の声が聞こえた。
犬と熊の向こう、下の方から、白い影が登ってきた。
いや、白というよりも薄い桃色というべきだろうか?ほんのり桜色の長い被毛に覆われた新たなライカンスロープは、どう
やら長毛の猫のようだった。
女か?胸を覆うふさふさした長い毛が、ふっくらとせり出して、豊かな丸みを帯びている。
「さっさと探索に戻れ。遊んでいる暇など無いのだぞ」
初めて見るはずの桃色の猫の声に、なんとなく聞き覚えがあるような気がした。
「ふん。お前に言われなくとも解っている!」
犬は猫に向かい、不機嫌そうにそう吐き捨てた。どうやらあまり仲は良くないらしい。
「解っているのならばさっさと…」
桃色の猫は言葉を切った。俺は慌てて顔を伏せ、茂みに姿を隠したが…、
…またしても遅かった…。猫の金色の目が、俺の目と一瞬あっていた!
どうする!?こうなったら変身して、戦って切り抜けるか!?いや、三体も相手にそれは無理だ!ならば逃げの一手しか…。
「どうした04?」
猫に問い掛ける熊の声が聞こえた。
まずい!とにかく早いところ変身しなければ!人間の姿のままではどうしようもない!
焦りのせいか、集中が上手く行かず、焦燥感を募らせるだけの俺の耳に、猫の言葉が聞こえた。
「いや、何でもない。さっさと下りるぞ」
…え?
俺は、信じられない気持ちで猫の言葉を聞いていた。
…何故だ?あっちは確かに俺の存在に気付いたはずだ。それなのに…?
俺はそっと顔を上げ、三人の様子を覗う。
三人ともこちらに背を向け、この場から離れて行く所だった。
安堵しつつも疑問が残った。
何故かは解らないが、あの初めて見る猫のライカンスロープは、俺の姿を確認しながらも、見逃してくれたらしい。
三人の姿が見えなくなって、それでもしばらく身を隠していた俺は、十分に時間が経った事を確認し、再び山を登り始めた。
「…と、そういう事があった…」
俺は耳を伏せ、尻尾をだらんと垂らし、上目遣いにビャクヤの顔を見上げた。
ビャクヤは、…すっかり呆れていた…。
俺はあの後、十分に離れた場所で変身し、大急ぎで小屋まで駆けてきた。
突然の来訪に驚きながらも、快く迎え入れてくれたビャクヤは、俺の話を聞き終えると、目を閉じて「ふぅ〜…」と、大き
なため息をついた。
「事情は良く判ったよ。…でも今回の件は、君が軽率だったと言う他に無いね…」
う…。やっぱり怒らせたかな…。
そう思ったが、目を開け、静かに俺を見つめるビャクヤの目は、とても悲しそうだった。
「僕の事を案じてくれるのは嬉しい。けれど、極端な話、僕は自分の身だけならどうとでも守れる」
ビャクヤは俺の目をじっと見つめながら言った。
「でも、君の身となればそうは行かない。最初の夜のような幸運は、そうそう無いんだよ?」
「…ごめん…」
俺は項垂れ、ビャクヤに詫びる。
困らせたくないのに、迷惑なんてかけたくないのに、俺の行動は毎度ながら裏目に出る…。
ビャクヤはしばらく黙った後、席を立った。
「家まで送ろう。そして、君のお母さんに会う」
「え?」
唐突な物言いに、俺は面食らって何度も瞬きする。
「幸か不幸か、君が遭遇したおかげで、連中がこの山を嗅ぎまわり始めている確証は得られた。もうあまり猶予は無い」
ビャクヤはそう言うと、ランプに歩み寄り、灯を消す。そして、俺を驚愕させる言葉を口にした。
「もしも君の正体が連中にバレた場合、危険が及ぶのはお母さんも同じだ」
俺は、勢い良く立ち上がっていた。全身の銀毛が逆立ち、嫌な汗が吹き出す。
なんて間抜けだ!母の身にも手が回るのは当り前のことじゃないか!
俺は、自分の軽はずみな行動で、ビャクヤだけでなく、母の身にまで危険を招く所だったのだ。
「事情を話して、警戒を促すよ。これから先、君に集中的な訓練を受けてもらう為にも、お母さんに知っておいて貰わなけれ
ばいけない。毎回遅くなったり、唐突に泊まりになったりする度に、嘘をつくのも罪悪感があるだろう?」
ビャクヤはそう言うと、リビングの壁にかけてあった、フードつきのロングコートを手に取った。
「…ところで、お母さんはもう家に居るかい?」
「え?あ、ああ。遅くてもそろそろ帰ってくる頃だと思うけれど…」
「そう…。なら、急いで行こうか」
急ぐ?何故?もしや、俺が考えている事の他に、母に迫っている危険があるのだろうか?
急に不安を覚えた俺に、ビャクヤは今日、初めて笑みを浮かべた。
「別に危険が迫っている訳じゃないよ。明日も仕事なら、夜遅くまでお邪魔したら迷惑になるからね」
安堵のため息をついた俺を促し、ビャクヤは月が照る庭へと足を踏み出した。
「アサヒちゃん以外の人間に会うなんて、13年振りかな…」
感慨深そうな呟き声が、白犬の口から漏れた。
街灯が照らす狭い夜道。スクールゾーンにもなっているその細い道路沿いに、母と俺が暮らす安アパートは建っている。
道路から見上げた二階の窓、母と俺の住まいからは、カーテン越しに灯りが漏れていた。
時刻は午後七時半を回ったところ、母は仕事を終え、すでに帰っているようだ。
「このアパートに、二人で住んでいるのかい?」
傍らのビャクヤに問われ、俺は頷きつつ彼の姿を見る。
俺はもちろん人間の姿になっているが、変身できないビャクヤは、いつものオーバーオールの上にフード付きのロングコー
トを羽織り、正体を隠している。
かなり大きなサイズのコートだが、太い胴回りと突き出た腹で前が閉まらないらしく、手袋をはめた両手をポケットに突っ
込んで、前に引っ張って押さえている。
フードを目深に被った下で目を光らせ、窓を見上げるビャクヤは、どうひいき目に見ても不審者だ。
道ばたで会った通行人に遠巻きに迂回されるどころか、くるりと背を向けて来た道を引き返されても仕方がないほどに。
…今更ながら母に会わせる事に不安を覚える…。
若干不安を感じている恋人を親に紹介する人間は、もしかしたらこんな気分になるのだろうか?
…っておぉい!違うぞ違うぞ!?俺は別にビャクヤを恋人のように母に紹介しようだなどとは思っていない!
…と、何でこんな言い訳めいた事を考えているんだろうか、俺は…?
「どうかしたのかい?」
「え?あ、いや…、何でもない…」
俺が内心でおこなった一人ボケ、一人ツッコミには気付かぬまま、ビャクヤは不思議そうに首を傾げていた。
「なら早く行こう?自分で言うのもなんだけれど、僕の格好はまるっきり不審者だからね。お巡りさんにでも見咎められたら
事だ…」
…自覚はあったんだなビャクヤ…。
おれは不安を抱きつつも、ビャクヤを促してアパートの階段を登りはじめた…。