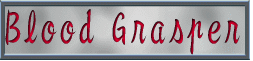
FILE8
「ただいま…」
「あら、おかえりなさい。遅かったわね?」
玄関のドアを開け、控えめに声をかけた俺に、台所に居るらしい母さんの声が応じた。
「晩ご飯は食べたの?」
「いや…、まだ…」
俺は靴を脱ぎ、うちで一番広い9畳の和室…、居間へと足を踏み入れた。
仕切りの引き戸が開けられていて、隣接する台所からは水道の音が聞こえ、味噌汁の匂いが漂って来る。
その台所に、流し台に向かった母の後ろ姿があった。
肩まで届く髪は、仕事中いつもそうしてあるように、ヘアバンドで纏めてある。
女手一つで俺をここまで育て上げてくれた、線の細い、痩せ形の、39歳の未亡人…。それが俺の母だ。
「母さん…。会わせたい人が居るんだ…」
「あら?もしかして、ガールフレンドでもできたの?」
母は振り向かないまま、微かな笑い混じりに言う。
「違うんだ。その…、危ないところを助けて貰った恩人で…」
俺は言葉を切り、それからはっきりと言った。
「俺と…、同じ種族のひとなんだ」
母の肩がピクンと震えた。
水道から落ちてゆく水の音が、途切れた会話の間を埋める。
母は肩を震わせたきり、動きを止めている。
その反応が、母はやはり、俺の正体を知っていたのだと…、はっきりと教えてくれた…。
何と言葉を続ければ良いのか解らなくなり、黙り込んだ俺を、母はゆっくりと振り返った。
驚きと、そして哀しさが同居するその顔の中で、哀しげな光を湛えた瞳が、じっと俺を見つめていた。
その瞳が俺と、その後ろに立つ、ロングコートを纏った異様な風体の大男の姿を映す。
ビャクヤはフードを被ったまま、胸に広げた右手を当てて、深々とお辞儀した。
「字伏白夜と申します。初めまして、忌名圭子(いみなけいこ)さん…」
顔を上げたビャクヤは、自分に視線を向ける母を真っ直ぐに見つめた。
「夜分遅くの訪問、まことに不躾で心苦しいのですが、危急の要件につき、お邪魔させて頂きました」
手袋をはめた右手が持ち上がり、フードを掴む。
フードがゆっくりと後ろに下ろされ、その下から現れたビャクヤの顔を見た母は、小さく息を呑んだ。
白くて長い、フサフサした毛に覆われた、耳の垂れた犬の顔…。
母はビャクヤの顔をじっと見つめながら呟いた。
「貴方は…、そう…、ツキヒコさんと同じなのね?」
忌名月彦(いみなつきひこ)…、俺の父の名だ…。
母の呟きに、ビャクヤはコクリと頷いて、口を開いた。
「ええ。…ライカンスロープ…。我々は古来からそう呼ばれています」
丸いちゃぶ台を囲み、俺とビャクヤの向かいに座った母は、全員の湯飲みに熱い茶を注ぎ終えると、居住まいを正した。
「ライカンスロープという言葉は、初めて聞いたのですね?」
「ええ。あの人は自分の事を、ただ人狼とだけ言っておりましたので…」
ビャクヤの問いに母が頷く。
「いつか、その血が目覚める時が来るまでは、ヨルヒコ自身にも黙っておくようにと、そう言われておりました…」
「ですが、人狼は産まれた時からある程度の自我を持っているものです。それなのに、ヨルヒコ君には全く自覚が無かった…。
それは何故か、心当たりはお有りでしょうか?」
ビャクヤのこの問いには、母は小首を傾げながら応じた。
「私にも詳しくは判りませんが…、この子の父は、産まれたばかりのこの子に目隠しをし、人の姿になるまでの一週間ほど、
周囲の様子も、自分の姿も、一切見せようとしなかったのです。その間はなるべく意味のある言葉もかけるなと言われたので
すが…、その事と何か関係が?」
「…なるほど…、外部からの刺激情報を遮断して、自他の違いを認識させず、おぼろげな記憶しか残させなかったのか…。そ
の上で自分を回りの人間だと思い込ませて生活させれば…。確かに…、人間社会に溶け込ませるには、何よりの予防策かもし
れない…。パラケルスス博士の仮説は正しかったかもしれないね…」
ビャクヤは感心したように何度も頷き、ぶつぶつと俺には判らない事を呟いた。
「…もうお察しの事とは思いますが…、彼は、すでにライカンスロープとして覚醒しています」
ちらりと俺を横目にしたビャクヤの言葉に、母は少し息を吸い込んでから頷いた。
「事の発端は、二週間程前…」
ビャクヤは、俺が初めて人狼になったあの夜の出来事から、順を追って話し始めた…。
「…お話は、よく解りました…」
ビャクヤが全て語り終えると、母はそう呟いた。その顔には、疲労の色が濃い…。
「相麻製薬…。身近すぎてまだ実感が沸きませんが、この町を離れた方が良いのでしょうか…」
「可能ならばですが、それをお勧めします」
頷いたビャクヤに、母は微かな笑みを浮かべた。
「この子の進学も決まった事ですし…、春には、母子揃って引っ越した方が良いのでしょうね」
これを聞いたビャクヤが「ん?」と、眉を上げて目をまん丸にした。
…そう言えば、まだ大学への進学の事は話していなかったかも…?
「知らなかった…。進学おめでとう、ヨルヒコ!」
嬉しそうな笑みを浮かべて言ったビャクヤに、俺は少し照れながら、そして言い忘れていた事が申し訳なくて、乱暴に頭を
ガリガリ掻いた。
「どうも…。でも、正直なところ、大学に行くべきかどうか迷っているんだ。…こんな状況だし…」
「迷う事はないよ。正体さえ知られなければ、これまで通りに生活して行けるんだから」
ビャクヤは微笑みながらそう言った。
…でも、進学してこの町を離れれば、相麻から距離を取ると同時に、ビャクヤとも離れる事になる。
頼れる者が居ない町で、正体を隠して上手くやっていかなくちゃいけないわけだ。
一人前になりたいという気持ちは日に日に大きくなっていくのに、現実の俺は半人前のまま、匍匐前進のようなスピードで
しか成長できていない…。
「せめて、卒業式まではこの町で過ごさせてあげたいのですが…」
母の言葉にビャクヤが頷く。
「解りました。ではそれまでに、僕はヨルヒコ君が覚るべき事を全て教えます。これからしばしば遅くまで、あるいは泊まり
がけで鍛錬に励んで貰う事もあると思いますが、許可を頂けますか?」
母は俺とビャクヤの顔を交互に見て、それから頷いた。
「お手数をおかけしますが、それがこの子に必要な事なら…、ぜひ、お願い致します…」
深々と頭を下げた母に、ビャクヤは笑みを浮かべた。
「お礼を言われるには及びませんよ。僕も、ヨルヒコ君が訪ねて来てくれるようになってから、暇を持て余す事がなくなりました」
そう言ってから湯飲みを掴んでグイッと煽り、すっかりぬるくなった茶を一気に飲み干すと、ビャクヤはペコリと頭を下げた。
「では、長々とお邪魔してしまいましたが、そろそろおいとまさせて頂きます」
「あ、待って下さい」
立ち上がりかけたビャクヤは、母に声をかけられ、中腰の姿勢で止まる。
「宜しければ、夕食を一緒にいかがですか?大した物ではありませんが…」
「いえ、そこまでは…」
遠慮するビャクヤを、俺も母と一緒になって引き留めた。
「遠慮しないでくれビャクヤ。俺だっていつもご馳走になってるんだし、たまには良いじゃないか?」
しばらく迷っていたビャクヤだったが、俺と母のしつこい誘いに、結局はしぶしぶ頷いた。
「…美味しい…!」
ナメコ汁を啜ったビャクヤは、幸せそうに微笑んだ。
焼き鮭にだし巻き卵、ナメコ汁にひじきの煮物、漬け物が少々といった、実にありきたりな夕食だったのだが、ビャクヤは
とても嬉しそうだった。
…考えてみれば、ビャクヤはほとんど自給自足の生活をしている。鮭やひじきなどの山の中では手に入らない物を食べられ
る機会は滅多に無いのだろう。
「遠慮しないでお代わりして下さいね?」
母は機嫌が良さそうに笑みを浮かべている。
それはそうだ。ビャクヤは瞬く間に丼に大盛りにされたご飯を平らげ、鮭に至っては骨までバリバリと食べてしまっている。
惚れ惚れするような食いっぷりだ。
自分が作った料理をこれだけ美味そうに食べられれば、作った母さんだって悪い気がするはずもない。
ちなみに、俺も変身するようになってからは以前より食が太くなった。
変身そのものと、変身後の修練でエネルギーを使うのもあるが、人間の姿を維持する事で肉体がストレスを感じ、消耗しや
すくなっているからだそうだ。
母とビャクヤは、会ったばかりだというのに、何故かすぐに意気投合した。
ビャクヤが穏やかで取っつきやすい性格をしているというのもあるんだろう。
それに、母にすれば、我が子の事を包み隠さず全て話せる初めての相手なんだ。
これまで18年、ずっと隠し続けていた秘密を打ち明けられる相手…。きっと、母さんはもっと早くにビャクヤと会いたかっ
ただろうな…。
ビャクヤの方は、恐らく人との会話が楽しいんだと思う。
俺やカワムラのようなガキじゃなく、きちんとした大人と話をする事など、十何年間もの間無かったはずだから。
考えてみれば、親類とも疎遠な我が家では、食卓に三人並ぶ事なんかこれまで無かった。
そのせいなんだろうか?電球を替えた訳でもないのに、居間がいつにも増して明るく感じられる。
そしてふと気付いた。
俺が…、出会って間もないビャクヤの事を、今では家族のように…、兄のように感じていた事に…。
同族だからなのか…。それとも人柄からそんな印象を抱いたのか…。
優しく、強く、穏やかに自分を見守ってくれる兄…。
俺はビャクヤを、いつの間にかそんな風に感じるようになっていた…。
母が強く勧めたので、ビャクヤは家で風呂に入って行く事になった。
せっかくなので、俺は一緒に風呂に入って背中を流す事にした。
「何だか悪いねぇ。お風呂までご馳走になっちゃって…」
申し訳なさそうに言うビャクヤの広い背中を流しながら、俺は苦笑いする。
「それを言ったら、飯も風呂もご馳走になった上に、ベッドまで借りてる俺はどうなるんだよ?」
「君は未成年だからね。甘えるくらいで良いのさ。僕は大人だから、好意を受けるにも節度っていうものがある」
妙に生真面目な返答に、俺は小さく吹き出す。
ビャクヤは大きい。骨太で、背も高く、幅もある。
いつもふさふさの長い毛は、今は湯を吸って張り付き、体のラインを浮き上がらせている。
発達して丸く張った肩や腕。背筋で盛り上がった背中。
いつもオーバーオールを着ているから判らなかったが、肩胛骨の下辺りから膝の辺りまでの毛は、薄いグレーに染まっていた。
胸と腹は白いが、グレーのエリアは背中側から脇腹まで続いて、腹の下に繋がっている。
ももは丸太のようにずんと太く、犬型の足もどっしり太くて大きい。
人狼になった俺の足はシャープだが、ビャクヤはこの足で力強く大地を蹴り、俺よりもずっと速く駆ける事が出来る。
首も太く、胸は分厚い。中年太りだと自嘲しているが、脂肪の下にみっちり筋肉がついた胴は、まるで樽みたいだ。
…そして何より…、股間の雄のシンボルもまたでかい…。
…太い…。いやぶっとい…。ごんぶとだ…。
これではいざオーケーが出ても、カワムラも大変だろう。…などと、気が付けば俺は妙な心配をしていた…。
俺も…でかさには…ちょっと自信があったんだけどな…。
「どうかしたのかい?急に黙り込んで?」
「え?いや…別に…」
俺は平静を装って、泡立てたスポンジでビャクヤの背を擦り続けた。
そして、考えた。…少し迷ったけれど、俺はさっき思った事を、ビャクヤに伝えてみる事にした。
「…あのさ、ビャクヤ…」
「うん?」
「俺、いつのまにかビャクヤの事、兄貴みたいに思ってた…」
ビャクヤは少し息を吸って、それからピタッと動かなくなった。…驚いてる…のか…?
「…俺…、一人っ子だったから、本当の兄弟がどういう物なのかは良く解らないけど…。ビャクヤみたいな兄貴が居れば良かっ
たのになって、今じゃ、そう思ってる…」
俺は無言のままのビャクヤに、苦笑しながら続けた。
「迷惑だよな?こんな問題ばかり起こすガキに、兄貴みたいに思われたって…」
ビャクヤは黙って首を左右に振ると、ぽつりと、小声で言った。
「迷惑なんかじゃないよ…。僕も…いつの間にかね…。君の事を…、弟のように感じていたから…」
意外な言葉に、今度は俺の手が止まった。
「…また一つ、昔話をしようか…」
ビャクヤはそう言うと、彼がまだ人間の姿になれていた頃…、まだ人間社会に紛れ込んで生きていた頃…、弟と過ごした遠
い日々の想い出を、俺に話して聞かせてくれた…。
風呂から上がった俺達を、母はビールを出して待っていた。
母があまり酒を飲まない我が家では、母が職場の同僚などから貰った、暑中見舞いやお歳暮などのビールが、半年から一年
に渡って消費されずに残ったりする。
なお、未成年の俺は一人だけコーラだ。
乾杯した後、ビールが好きなビャクヤは天井を仰ぐようにして、缶ビールを一気にあおった。
俺やビャクヤのライカンスロープとしての姿は、人間と違ってマズルが突き出ているせいで、缶やコップからチビチビと飲
み物を飲むのは結構手間だ。なので、こんな風に一気に口に流し込む方が、楽だし気分も良い。
「へぇ〜…、「地でぢ」ねぇ…。僕が山に隠っている間に、世の中は随分変わったなぁ…」
俺と母の説明を聞くと、ビャクヤはテレビを眺めながら感心したように呟いた。
「…携帯電話って、家に何台もある物なのか…。僕が知っている携帯電話はもっとゴテゴテしていたけれど…。しかもかなり
高かったし、屋内に入れば頻繁に圏外になっていたのに…」
「「えむでぃ」?カセットテープはもう使われていないのかい?ウォークマンもみんなこれを使うの?え?携帯電話で音楽が
聞ける?」
「「でぃーぶいでぃー」?レーザーディスクじゃなく?へぇ…、今は映画もこんなディスクに収められるのか…」
文明と距離を置いて暮らしているビャクヤにとっては、俺達が慣れ親しんでいるものも珍しいらしい。
物珍しそうな彼に、俺と母は面白がりながら色々な品を紹介した。
「たったの13年で、人間社会はここまで変わっていたんだねぇ…」
ビャクヤは母が持ってきたコードレスフォンを手に取り、しげしげと眺めながら、感心したようにうんうん頷いている。
「手ぶらで通話できる機能か…。便利かどうかは判らないけれど…、面白そうではあるね」
「あらやっぱりそう思う?最初は便利そうと思って買ったのだけれど、いざ使うときは普通に話してしまうのよねぇ。ほほほ」
すでに堅苦しい言葉遣いはやめ、二人はすっかり打ち解けた様子で会話を弾ませている。
そんな二人を見ながら、俺は自然に浮かんでくる笑みを、隠すことも無く浮かべ続けていた。
最初は会わせる事に抵抗があったけど、心配なんて無用だったな…。
土産にと、母は家中の缶ビールを全て段ボールに詰め、ビャクヤに持たせた。
今日飲んで少し減ったとはいえ、それでも6ダースはあったが、ビャクヤはそれを軽々と担ぎ、心底嬉しそうな笑みを浮か
べて、何度も礼を言った。
「気兼ねなく、またいつでもおいでなさいね、ビャクヤさん」
「まぁ、このナリですから頻繁にとは行きませんが、ご迷惑でさえなければ」
笑みを交わす母の横で、俺はビャクヤに声をかけた。
「ビャクヤ。俺、明日も行くよ。今度は、気を付けていくから…」
「うん。念のため、僕も途中まで迎えに出るようにしよう」
頷いたビャクヤは、軽く頭を下げた。
「長々と居座って迷惑かけちゃったけれど、これで失礼するよ。ご飯とお風呂、それからビールもご馳走様。今夜は…、とて
も楽しかった!」
「迷惑だなんてそんな…、私の方こそ楽しかったわ」
「いつも俺の方が迷惑かけてたんだ。少しでも埋め合わせになったなら嬉しいよ」
母と俺の言葉に笑みを返すと、ビャクヤはコートのフードを目深に被った。
「それじゃあお休み。ケイコさん、ヨルヒコ」
ビャクヤがドアを開けて出て行くと、母さんは俺の頭に手を置いた。
そして、すでに身長を追い抜いて久しい息子の顔を、微笑みながら見上げる。
「ごめんなさいね、ヨルヒコ…。いずれ話すつもりだったけれど、お前がもう人狼になっていた事に気付けなかったから…。
大変な思いをさせちゃったわね…」
「良いんだよ母さん…。俺はこうして無事で居る」
俺は母に笑って見せ、その細い手を取った。
「父さんの事、聞かせてくれないか?人狼だった、父さんの本当の顔を…」
少し驚いたように目を丸くした母に、俺は少し照れながら続けた。
「…知りたいんだ。人狼だった父さんが、どんな人だったのかさ…」
母は、目を細めて笑みを浮かべて頷いた。
その夜、俺達母子は、夜更けまで話をした。
母の口から語られた、人狼だった父の人物像…。
俺にとって、これまで遺影の顔でしかなかった父は、心の中で、一個人としてしっかりとイメージされるようになった…。
隠れ里に迷い込んだ人間の女性と恋に落ち、共に生きる為に仲間達と縁を切り、人間社会に溶け込んで暮らす事にした、少
し世間知らずで不器用な、真っ直ぐで一途な気性の、俺と同じ色の狼として…。