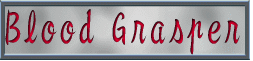
廃村の白夜
日本というこの島国の景観と文化は、私の心を潤してくれる。
エキゾチックかつ美しい植物達に、独自の発展を遂げた食文化。
そして、他国では殆ど見られない程稀有な、微妙な秩序を以て成り立つ獣達の群れ社会。
私が今立っているここにも、かつては獣の集落が存在していたはずだ。
杉の木が身を寄せ合うように茂った、ゆるく傾斜を描く山間。
そこには、木の板で組まれた小さな家屋が、周囲の杉の木と同じように、身を寄せ合うようにして建ち並んでいる。
いずれの家も、壁はひび割れあるいは崩れ、屋根(確かカヤブキというらしい)は破れて上に雑草が茂り、それを支える柱
は根本から傾き、長年の風雨に晒され、今にも崩れそうになっている。
遠く、列車の中からグラスで眺め、興味深い植物を見つけて足を運んだ山で、まさかこのような発見ができようとは…、い
やいや、思わぬ収穫だった。
集落跡には、もちろん痕跡など残されてはいない。表向きは。
しかし私には感じられる。一般人には判らない、微かに残ったその独特の気配が…。
視覚でも、嗅覚でも、五感と呼ばれる物では決して捉えられないその気配は、紛れもなく、人間ではない存在がここに残し
たものだ。
とりあえず、空の表情と風の香りを確認してみたが、天候は崩れそうにない。
せっかくなので、調査しながらここで一晩空かす事にしよう。
食料は…、まぁ、列車の旅で共をしてもらった菓子や干物類しか無いが、そうそう長居はしないので、問題あるまい。
滞在を決めた私は、集落の中を歩き回り、一晩の宿を探した。
風を防げるだけの、そして間違っても倒壊しないだけの強度を保っている小屋は、割とすぐに見つかった。
たった一つの荷物である大きめの旅行鞄を、さっそく屋内に運び込もうとしたその時、私はそれに気が付いた。
視線…。先程までは全く気配を感じなかったのだが、何者かが近くに潜んでいる。
…この感覚…、人間ではないようだ…。
気付かないふりをして、私は屋内に足を踏み入れた。
私を見ているソレが、何を考えているのかは判らないが、無用な衝突は避けるに越した事はない。
「さて、どうするべきか…?」
私は顔の下半分を覆う、たっぷりとした灰色の顎髭を撫でながら思案する。
とりあえずは気付かぬふりを決め込んで、様子を見るとしようか…。
やはりと言うべきか、一息ついた後に集落跡を調べ始めた私を、例の視線はずっと追ってきた。
まさかここの元住民という訳でもあるまいが…、はて、一体何者だろうか?
半日を小探検に費やし、日が傾く頃になると、私は観察者についていくつか知る事ができた。
一つめは、視線の主は、気配を絶つのが恐ろしく上手いという事。
私にこの特殊な感覚が無ければ、おそらく存在を感知する事はできなかっただろう。
二つめは、どうやら私への敵意は無いらしいという事。
警戒はしているだろうが、どうこうしようという意志があれば、隙だらけに振る舞っている私に何も仕掛けて来ないのはお
かしい。
三つ目は、どうやら私に興味を持っているらしいという事。
これは当然だ。でなければ半日もの間、飽きもせずに私を監視などしていないだろう。
…さて、向こうから何かして来るつもりは、今の所は無いようだ。
だが、何をして来る訳でなくとも、ただ黙って見られているというのは、なかなかに居心地が悪い。
相手に敵意が無いと踏んで、私は日が完全に落ちる前に、ある行動に出てみる事にした。
集落の中心となっている場所は、小さく開けた広場のようになっている。
そこには、おそらく住民が共同で使っていたのだろう井戸がある。
今もなお、澄んだ地下水が湧き出している井戸のへりに、私は片手に乗るほどの小さなクッキーの箱を置き、その場を離れた。
広場から離れる私の背に、視線は相変わらず注がれている。
しかし、ほんの微かにだが、動揺しているらしき気配が感じられた。
持って行けと言わんばかりに置かれた菓子の箱。
そして、何も言わずにその場を離れる老人。
私が、注がれている視線に既に気付いていた事を、監視者は知ったのだ。
傾いた小屋の脇を抜け、広場からは私の姿が見えなくなる辺りに差し掛かった時だった。その声が、私を呼び止めたのは。
「待って下さい」
というその声に、私は振り返らないまま足を止めた。
「気付いていたんですね?僕が見ていた事に」
思いのほか若い男の声は、私のずっと後ろ、広場の辺りから聞こえて来る。
壁際にでも身を隠しているのか、声は反響しながら私に届いた。
そこそこ距離があるにも関わらず、落ち着いて張りのあるその声は、たいして大きくもないのに、老いた私の耳朶にも一語
一語はっきりと届いた。
「そなたの縄張りとは知らずに踏み込んでしまった無礼、どうか赦されよ。私は通りすがりの旅行者だ。そなたの住み処を荒
らすつもりも、そなたと争うつもりもない」
私の弁解が聞き入れられたのか、振り向かぬままに確かめる術は無かったが、声の主に敵意が無いことは、今や明らかだ。
この間合いで相手が人間ならば、あちらにとって絶対的に有利。
にもかかわらず、隙だらけの私に対し、わざわざ声をかけて来たのが何よりの証。
「僕の縄張りという訳では無いんです。こっちも少々事情があって放浪している身でして…」
…ふむ…?事情は判らないが、どうやら私が思ったとおり、ここの元住人という訳ではないらしい。
「放浪の身、とな?」
興味を覚えた私の問いに、声は困ったような口調で続けた。
「ええ。仮の宿としてこの集落跡に身を寄せていたのですが、もしかしたら、貴方はここの正当な住人なのかと思いまして…」
なるほど、それで身を潜めて私の様子を窺っていたという訳か…。
「痕跡は残していないつもりでしたが…、どうやらバレてしまったようですね?」
「…いや、そなたの痕跡に気付いた訳ではない。そなたが監視していることには気付けたが、今話を聞くまで、この集落に身
を寄せていた事には気付かなかった」
己のうかつさをなじるべきか、それとも彼の痕跡の消し方を褒めるべきか、集落中を見て回ったにも関わらず、最近の物と
思われる痕跡は一つも見つけていない。
「でも、何か色々と調べていたように見えましたが…?」
訝しげな響きの混じる声に、私は極力軽い口調で応じた。
「ははは!あれはまた別の調べ物だ。ライカンスロープの集落跡を前にしたら、学者としての好奇心が抑えられなくなってな」
私の言葉で、ある程度こちらの正体に目星を付けたのだろう。
しばしの沈黙の後、その問いは静かに、私の背に投げかけられた。
「僕がライカンスロープである事にも、気付いていたんですね?」
背を向けたままでも判るように、私は大きく頷いた。
「私とそなたは偶然出会っただけ。どうこうしようとは思わぬし、余計な詮索もしない。この枯れ枝のような老いぼれ、襲お
うと思えばどうとでもできただろうに、そなたはそうはしなかった。その事から、話の分かる相手だろうと察し、一言挨拶し
てみようと思っただけだ」
背を向けたままの私の言葉に、声の主は微かに笑ったようだった。
「声をかけてみて正解でした。どうやら、久し振りに人と話ができそうだ」
土を踏み締める微かな音で、声の主が隠れていた壁を出て、私の見える位置に移動した事が察せられた。
許しが出たと考え、私は相手を刺激しないよう、ゆっくりと振り向いた。
こちらから見て広場の入り口を背に、クッキーの箱を片手に乗せて微笑んでいる声の主。
その姿を見た私は、あまりにも大柄なその体躯を目にして、一瞬熊かと勘違いした。
殆どボロ布と化したズボンで、申し訳程度に腰を覆っているだけの、ほぼ裸のライカンスロープ。
顔は犬…、縫いぐるみを思わせる、長い被毛に覆われたこの顔立ちは、オールドイングリッシュか。
全身を覆うのは白く長い毛。背の半ばから尻、膝上辺りまでが柔らかいグレーに染まったツートンカラー。
太り気味の体付きをしており、垂れた耳と、長い前髪の下で煌めく黒い瞳が、極めて大柄な体躯とは裏腹に、実に穏やかな
印象を私に与えた。
犬型のライカンスロープは数も多い。
私もこれまでに何度も見ているが…、しかし、これほど立派な体格をした個体にはそうそうお目にかかれない。
昔出会ったグレートピレニーズとセントバーナードの夫妻にも匹敵するその巨躯は、私が見てきた中で最大級のボリューム
だった。
…それに何より…。
「そなたは…、人狼混じりなのか?」
少しばかり驚きながら尋ねると、白犬は私よりもさらに驚いた様子で目を丸くした。
「わ、判るんですか!?お察しの通り、父親が人狼でしたが…」
人間の姿を取る事の出来る、人外の存在…。
彼らはライカンスロープと一括りに呼ばれてはいるものの、実際にはかなり細かく分類される。
半獣半人の形態となる彼ら本来の姿は、それこそ獣と同じだけの種類が存在すると考えて良い。
そのように数多くの種に細分化される彼らの中でも、とりわけ強力とされる数種のライカンスロープが存在する。
人狼は、その中でも代表格の種だ。
同族内でも群を抜いて高い驚異的な身体能力に、ライカンスロープの大きな特徴である、常識外れの修復能力を封じる力を
持っている。
もっとも、人狼は個体数が少ない希少な存在で、五十年近くハンターをやってきた私も、出会えた人狼はたったの四名だけだ。
そんな人狼と、犬属のライカンスロープとの間に子が生まれた場合、稀に、外見上は犬属でありながら、人狼の力を部分的
に受け継いだライカンスロープが生まれる事がある。これが人狼混じりだ。
種が近いせいなのか、狼と犬との間の子だけが人狼混じりとなる可能性があるらしい。人狼そのもの以上に希少だ。
そして、目の前に居るこの白犬も、そんな珍しいハーフブラッドの一人である事を、私の感覚は捉えていた。
白犬はしばらくの間、私をじっと見つめていたが、やがて何かに納得したように小さく頷いた。
「…そうか…、気配を絶った僕に気付く訳だ…。貴方は、パシーバーですね?」
今度は、少しどころでなく驚いた。
パシーバーとはつまり、私のように五感以外の感覚で、人外の存在の正体を看破できる者…、あるいはその感覚そのものを
指す言葉だ。
ライカンスロープの存在を知る組織内で使われている言葉なのだが、その存在と名称を知っているという事から、この白犬
も、それらの組織と何らかの関わりがあったという事が察せられる。
そういった組織の中に居たのか、それとも敵対していたのかまでは判らないが…。
「これは貴重な体験だ…。人間社会に紛れて生きていた僕からすれば、貴方達は天敵でしたから…。話をするどころか、うか
つに近付くこともできなかった。是非にも、色々と話を聞いてみたいものです」
警戒されるかとも思ったが、意外にも彼は興味深そうな様子を見せ、機嫌すら良さそうに私に笑いかけた。
自然な、あまりにも自然な身ごなしで、彼は私に歩み寄った。
「僕の名は白夜。貴方にも分かり易く言うなら、この国の言葉で、遙か北の地の日が沈まない夜を指します」
私は彼が差し出した大きな手を、信じられない物を見る気分で見下ろした。
相手に全く警戒を抱かせない、無防備で自然で開けっぴろげなその足運びに、元ハンターともあろう者が、身構える事もな
く目の前まで接近されてしまっていた…。
…老いたかな、私も…。
「私はホー…」
名乗りかけた私は、言葉を切って苦笑した。
もはや、長年使い慣れた偽名を名乗る必要は無いのだったな…。
私はもう、ハンターではないのだから…。
「パラケルススだ。よろしく、ビャクヤ」
しばし名乗る事もなかった本名を告げ、白い毛に覆われた大きな手を、私は軽く握り返した。
「AMLTAのハンター?」
私が元の所属を告げると、ビャクヤは驚いたように口をポカンと開けた。
夢中になって食べていたクッキーの欠片が口の端についており、なんとも子供っぽく見える。
「元、な。今は脱走し、追われる身だ」
ビャクヤと名乗ったこの若いライカンスロープは、実に物知りだった。
もしやと思って口にしてみれば、私の古巣である組織、通称アムリタの事も知っていた。
今、私は荷物を置いていた小屋の前で、どうやらツケモノメイキングに使われていたらしい樽を椅子代わりに、ビャクヤと
話し込んでいる。
私もそうだが、彼もまた他者との会話に餓えていたらしい。
この国に来てから見聞きした、他愛のないいくつかのニュースの話題にも、興味深そうに聞き入っていた。
他愛も無い話題だけでも、会話はいつまでも途切れそうに無かったが、ふと思い立った私が試しにその言葉を投げかけてみ
ると、予想通りにビャクヤは反応を示した。
「先程から思っていたのだが…。ビャクヤ、そなたは人間の組織と深く関わっていたのではないか?」
ビャクヤは少し逡巡していたが、やがてこくりと頷いた。
「訳あって離れなければならなくなりましたが…、半年前までは、人間社会に溶け込んで暮らす、大きなトライブで狩人を担っ
ていました。人間の組織やフリーのハンターとも、何度も戦っています」
なるほど、それでこの手の情報に精通しているのか…。
狩人とはつまり、彼らライカンスロープの共同体の中で見られる、一種の掃除屋だ。
外敵や多様なトラブルからトライブを護る守護者であり、敵対者を駆逐する殺し屋でもある。
狩人を担うライカンスロープは、その群の中において屈指の実力者であり、闘争に長けた個体だ。
彼の穏やかな振る舞いや口調からすれば少々意外だったが…、なるほど確かに、老いぼれとはいえ自分達の事について詳し
い、得体の知れない私を前にしても、無駄に警戒せず自然体で居られるのは、場数を踏んだ証と取れない事もない。
まして人狼混じりとなれば、その力は推して知るべしだ。
…それにしても、何故狩人を担っていた彼が、今は群を離れ、人里を離れたこのような山奥に…?
疑問を抱く私の視線に気付いたのか、ビャクヤは困ったように眉尻を下げ、頬を掻く。
「…人間の姿に、なれなくなってしまいまして…」
…なるほど。彼が何故、正体を現したままで私に接触して来たのかが判った。
最初は、私が逃走、あるいは危害を加えようと目論んだ際に対応し易いように、獣の形態を取っていたのだと思っていたが、
どうやら違うようだ。
獣化因子が機能障害を起こしているのか、それともその他の何かが原因なのか、ビャクヤはライカンスロープという生物の
最大の特徴の一つ、人間への形態変化ができなくなっているらしい。
「迷惑をかける事にもなりますし、それで仲間の元を離れ、人目を忍んで暮らし始めた訳です」
「…どれほど前から?」
「四ヶ月ほどですね。まぁ、そろそろ慣れて来ました」
「辛いかね?」
私の問いに、ビャクヤは少しの間、黙って考え込んだ後、
「…考えないようにしていますが、たぶん、辛いんだと思います」
そう応じて、少し寂しげに微笑んだ。…なんとも正直な物言いだ。
「…もしも、だが…」
私は白犬の目を見つめながら、一つ提案をしてみた。
「そなたがその機能不全を何とかしたいと思うのであれば…、そして、私を信用できるのならば、治療に手を貸しても良いの
だが…?」
ビャクヤは驚いたように目を大きく見開き、それから窺うように、じっと私の目を見つめてきた。
「…出来るんですか?そんな事が…」
「「出来る」とは言い切れぬ。が、やれるだけの事はしてみよう。その代わりと言っては何だが、そなたの力を見せて欲しい」
胡乱げに目を細めたビャクヤに、我ながら酔狂な事だと自嘲しつつ、私は懐から手帳を取り出して見せた。
その革表紙には、互いの尾を噛んだ、金色の二匹の蛇がもつれ合うエンブレムが刻印されている。
「こう見えても、私は学者の端くれでね」
ビャクヤは子供のように目をキラキラさせながら手帳を、そして私を見つめた。
「…金のウロボロス…!錬金の博士号をお持ちなんですね?」
知っているかもしれないとは思ったが、やはり彼は物知りだ…。
ビャクヤはその優れた嗅覚によって、私に敵意が無い事を確信していたらしく、喜んで申し出を受けた。
だが、私が考えていたほどに、彼の体に起こっている変化は甘いものではなかった。
彼は、人狼混じりであるのみならず、干渉否定能力の持ち主だった。
ビャクヤは干渉否定によって、自らの人としての姿を否定していたのだ。
薬に催眠療法、思いつく限りの様々な手段を試みたが、彼の肉体は人の姿に変わる力を取り戻す事がないまま、あっという
間に三ヶ月が過ぎた…。
「博士。出来ましたよ」
「では、このビーカーにゆっくり入れてくれ」
私が火にかけ、紫色の薬を沸騰させていたビーカーに、ビャクヤは自分が作った薄緑色の薬を慎重に混ぜてゆく。
無臭の蒸気がビーカーから立ち昇って部屋の中を満たし、私は満足して頷いた。
今、私とビャクヤは、二人で建てた丸太小屋で暮らしている。
私がこの山にやってきたきっかけ、列車の窓から遠目に見つけた希少植物「まよひざくら」を使い、偶然にも入り込んだ一
般人に発見される事のないよう、周囲に結界を張って。
生活用具については、あの集落から竈や鍋をそっくり失敬して利用させて貰ったり、椅子や机などは切り出した木を加工し
たりして、二人で組み上げた。
私は人狼混じりである彼の能力を調べ、彼は私から錬金の知識と技術を学んで過ごしている。
私にとって、追っ手の目を逃れる為にも、こうして身を隠していられる時間はありがたい。
ビャクヤは亡き父親から、錬金術の基礎を少し囓っていたらしい。
私が教える様々な知識や技術を、乾き切った砂地が雨を吸収するように、驚嘆すべきペースで身に付けてゆく。
私の力不足で、形態変化能力を取り戻すことはついぞ叶わなかったが、ビャクヤはもはや、その事は気にしていないようだ
った。
「色が…」
ビーカーを注意深く見つめていたビャクヤは、混じり合い、熱せられた薬が透き通ってゆく様子を目にして呟く。
濁っていた薬は、やがて無色透明の薬に変わる。
私が教えた通りの配分で、材料を正確に混ぜ合わせた事が、この結果からはっきりと分かる。
「それが消気水だ。もっとも、完全に気配を絶てるそなたには、あまり使い道は無いだろうがな」
ビャクヤは素晴らしい生徒だ。
これまでにも数人に手ほどきしてきたが、これほどの才覚に恵まれた者には、ついぞお目にかかれなかった。
…惜しむらくは、彼がその才をさして必要とせず、そして存分に活かす事のできない身であるという事…。
人狼そのものと同等の驚異的な身体能力に、呪いを弾く特性。
加えて、絶対的な作用を持つ干渉否定能力。
そして、教え手が嬉しくなるほどの才能。
何よりも、穏やかで優しく、賢明なその性質。
ビャクヤは正に、奇跡のような存在だった。
世を大きく動かすことが出来得るはずの彼が、このような田舎の山奥でくすぶっていなければならない…。
その事が、私には不憫でならなかった…。
出来上がった消気水を慎重な手つきで小瓶に収めると、ビャクヤは子供のように無邪気な、心底嬉しそうな笑みを見せた。
ビャクヤが身に付けているのは、私が下山して手に入れてきた生地で、実に器用な彼が作ったオーバーオールに、最も大き
いサイズを選んで手に入れてきたティーシャツ。
どことなくユーモラスないでたちだが、どうやらお気に入りになったらしく、同じデザインの衣類を何着も拵えている。
ビャクヤとの暮らしは、逃亡、そして追跡の生活に疲れていた私の心を癒してくれた。
…だが、いつまでも居る事はできない。じきに発たねばならないだろう…。
冬が過ぎ、春が訪れたなら、再び放浪と探求の身に戻ろうと思っている。
ビャクヤは寂しがるだろうが、私がこのままここに留まったところで彼が元に戻れる訳でもない。
出来うる限りの知識を授けたなら、私は一つ増えた捜し物を抱え、旅立つとしよう…。
「山を降りる!?」
思っていたとおり、ビャクヤはかなり驚いていた。
彼が作った絶品のクリームシチューをじっくりと味わいながら、私は頷く。
春がほど近い、雪解けの季節の事だ。
私はずっと温め続けて来た、再び旅に出ようという考えを、ついにビャクヤに伝えた。
「どうしてです博士!?追っ手の目を誤魔化す為にも、この山で過ごした方が…」
「追っ手が居るからこそなのだよ。ひとところに身を隠していた所で、逃げおおせられる相手でもない。入国からすでに半年
が経った。私がこの国に居る事は、そろそろ嗅ぎつけられるだろう。この地に留まり続ければ、そなたにも危険が及ぶ」
「構いません!」
垂れた前髪の下の瞳に、これまでに見せた事もない険しい光を宿して、ビャクヤは声を上げた。
「博士に害を為しに来る相手は、僕が一人残らず追い返します!指一本触れさせはしません!」
ビャクヤの言葉は本音だ。
彼の義理堅さを鑑みれば、この老いぼれ一人の為に、アムリタに…、国家に正面切って挑みかねない。
おそらくは、この猛々しく吠えるビャクヤもまた、彼の真の一面であるのだろう。
だが、彼の魂の根源とでも言うべき精神の根は、その身に宿す絶対的な力とは裏腹に、争いを好まない穏やかなものだとい
う事が、共に過ごしてきた私には判っている。
申し出に甘え、彼にそうまでさせる事は…、私にはできない…。
「ビャクヤ…、気持ちは嬉しい。…そなたと過ごす穏やかなる日々も捨て難いという本音も、実はあるがね…」
「なら…」
何か言いかけたビャクヤを制し、私は先を続けた。
「が、私のわがままを許してはくれまいか?あとどれほど生きられるかも判らぬ老いぼれだが、残る生涯を見聞と探求に費や
したいのだよ」
ビャクヤは口を横に引き結び、今にも泣き出しそうに顔を歪めた。
…赦せ、ビャクヤ…。
山中に独り身を潜め、息を殺して過ごす日々、さぞ辛く、寂しいものになるだろう…。
だが、そなたの体を元に戻す方法も、あるいは旅の中で見つけられるやもしれないのだ…。
ビャクヤは、私の意志を尊重してくれたらしく、小さく頷いたきり項垂れて、それ以上は何も言わなくなった。
この時のビャクヤの姿は、忘れられないものとなった。
…見上げるような巨体の白犬が、まるで捨てられた幼い仔犬のように寂しげに、心細そうに、肩を落として項垂れていた姿
は…。
風呂桶の中から窓の外の月を眺め、私はこの国で過ごした日々を振り返る。
思えば、この国にここまで長居する事になろうとは考えてもいなかった…。
あの日、列車の窓から「まよひざくら」を見つけたりしなければ、この山に踏み入る事も、あの集落跡を見つける事も、ビャ
クヤと出会う事も無かっただろう。
気まぐれな運命の女神が与えてくれた、実に面白い、実に素敵な巡り合わせだと思う。長生きはしてみる物だ…。
しばし物思いに耽っていると、木戸をトントンと叩き、ビャクヤがおずおずと話しかけてきた。
「博士、よければ背中を流したいのですが、構いませんか?」
いやに腰の低いビャクヤの態度に、私は軽い罪悪感を覚えた。
…寂しいのだ…、ビャクヤは…。
まだ彼は二十を幾らも過ぎない若者、こんな老いぼれでも、話し相手を失うとなれば、寂しいに決まっている…。
「…頼もうか…」
私が呟くように返事をすると、木戸を引き開け、全裸のビャクヤが浴室に入って来た。
惚れ惚れするような巨躯は、しかし肩を落として小さくなり、いつも笑みを絶やさなかった顔は、俯き加減で表情が暗い。
決して広くはない浴室で、椅子にかけた私の背に、ビャクヤはゆっくりと湯をかけ、丁寧に擦り始めた。
老いさらばえた枯れ枝のような私の体を、ビャクヤは労るようにゆっくり、丁寧に、優しく流す。
まるで、私の旅の無事を祈るように、いつにも増して入念に…。
「ビャクヤ…」
「…はい…」
明らかに元気のない声で返事をした彼に、私はゆっくりと、言葉を選んで話しかけた。
「方法が見つかったなら、私は必ずやここに戻ってこよう。だがもしも、私が戻る前にここを離れなければならなくなったな
ら…、そうだな「まよひざくら」の下に手紙を埋めておいてはくれまいか?何処に行けば、愛弟子の顔が見られるのか、この
老いぼれでも判るよう、できるだけ判りやすい手紙をな…」
「…はい。必ず…」
「そんな声を出すな。まるで死出の旅路にでもつくような気分になるぞ?」
冗談めかして言った私に、
「は、はい…!」
ビャクヤは慌てた様子で、下手くそな作り笑いを浮かべ、返事をした…。
「では、な」
住み慣れた小屋の前で、私の手を握りながら、ビャクヤは大きく頷いた。
「はい。博士、お元気で…」
「そんな顔をするな。笑って見送ってくれ」
片方の眉を上げ、少々おどけた表情でそう言うと、ビャクヤは泣きそうに顔を歪めた。
私は愛弟子の顔を見上げながら、そのぶ厚い胸をドンと、拳で叩く。
「方法が見つかっても、見つからなくとも、私は必ずまたそなたに会いに来よう。それまで達者でな、ビャクヤ…」
「はい…!」
泣くのを必死に堪えながら、ビャクヤは頷いた。
家庭を持った事は無かったが…、今や、私がビャクヤに抱くようになった気持ちは、あるいは孫に対してでも抱くような感
情なのかもしれない。
離れる寂しさと、残してゆく罪悪感を断ち切り、私は踵を返した。
振り返らず、真っ直ぐに歩み、つぼみを付け始めた二股の桜の間を潜ろうとしたその時、
「博士!」
背後から響いたその声に、私は思わず振り返った。
小屋の前に留まっていたビャクヤは、右の眉を上げ、左の口の端を吊り上げ、なんとも複雑な泣き笑いの顔で、私に言った。
「有り難う御座いました…。そして、気をつけて行ってらっしゃい…!」
「ああ。行ってくる…!」
私は笑みを浮かべて片手を上げ、そして桜の間を抜けた。
いつか、またこの桜の間を抜ける時…、元に戻す方法を手土産に帰ってきた私を、ビャクヤが笑顔で迎えてくれる事を願い
ながら…。