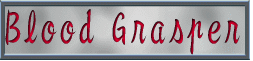
黒白の惜別
ユウの目覚めという朗報は、瞬く間に同士達の間に広まった。
ウーシンを保護して一足早く戻っていたヤチは当然病室に急行し、大きな弟を力一杯抱き締めた後、周りが引く程べたべた
しながら体の具合を確かめたりもした。
その間に撤収し、後始末の人員達と入れ替わりで帰ってきたフータイは、しかし手を放せる状況でもなかったため、我慢し
て一晩訪問を見送る事になる。
そしてヤチ達のトライブは、各方面への痕跡を残さない後始末の為、極めて多忙な数日を送り、大晦日がやってきた。
「…花火…」
痩せ細ったパンダの少年は、リクライニングベッドの上で身を起こしながら、顔の半面を窓から注ぐ煌びやかな光で染めて
いた。
「ああ。あれが本物の花火だ」
ベッドの脇に座る姉は、弟の手を取りながらうんうん頷く。
年越しのカウントダウンに次いで立て続けに上がる花火を、ウーシンは目を細めて微笑しながら眺めている。
「綺麗だ…」
「綺麗だろう?凄いなぁ、あんなに大きいぞ」
殊更に明るい口調で応じたヘイシンは、視線を窓と弟から外し、首を巡らせて背後を見遣る。
ドアとベッドの間に置かれた大テーブルにつき、てきぱきと飲み物を用意し、クラッカーにチーズやベーコンなどをトッピ
ングしている大柄な虎は、ジャイアントパンダの視線には気付かぬまま、大きな白熊にトレイを渡していた。
その部屋は病室ではない。
タマモが所有するホテルの一つ、花火が見られるスポットとしても人気の物件の最上階。個人的な客人を持てなすための、
一般には貸し出していないVIPルームであった。
現在この部屋には数名のライカンスロープが集まって、年越しの絶景を楽しんでおり、バーキーパーのフータイはここで出
張営業中。
師からトレイを受け取った白熊は、窓際の姉弟に歩み寄ると、ニコニコしながらそれを差し出す。
「はいウーシン君。イチゴミルク。クラッカーは好みが判らないから、フータイさんが色々用意してくれたよ」
ユウの口から出たのは、師匠仕込みの流暢な広東語。
「有り難う、兄ちゃん」
痩せ細った顔に嬉しそうな笑みを浮かべてトレイを受け取ると、ウーシンはストローを口に含む。
変わったヤツだ。そうヘイシンは思う。
半殺しの目に遭わせた者の弟に屈託無く接するだけでなく、本人にまで普通に接して来る。まるで何もなかったかのように。
「ヘイシンさんも飲み物どうですか?大概の物はありますよ」
そう言いながらユウが向けた視線の先には、慣れた手付きでリズミカルにシェイカーを振るい、カクテルを拵えて山猫に振
る舞っているフータイの姿。
その動作と黒服に腰エプロンという格好がやけに似合っているのが、ヘイシンには信じられない。自分に黒星をつけた武芸
者がバーキーパーをしているというのは、何ともちぐはぐに思えた。
信じられないと言えば、ここ数日間の自分達の扱いも信じられない。
ハンイーから先払いで代金が支払われたと聞いているが、ウーシンは延命治療に加えて何一つ不自由のない生活を保障され
ている。
報復措置によって拷問の末に殺されても仕方がないはずのヘイシンも、今のところは処分保留で、ウーシンの傍に付き添っ
ていられる。
これがウーシン存命中の限定措置だとは、フータイから聞かされている。
保って三ヶ月。残された時間がそれほどまでに少ないウーシンは、せめて肉親に見送られるべき。そんな配慮からの措置で
あった。
ウーシンが逝った後はどうなろうと構わない。元々そう考えているヘイシンは、弟の死後、自分に下されるであろう処分を
恐れていない。
このトライブの頭の古馴染みである組織の者を、少なくとも十人以上殺した。このトライブの面目を守り、相手側との関係
を保つ為にも、実行犯である自分はそれなりの死に方をさせられる事になるだろうと確信している。
それでも彼女は感謝している。ハンイーの頼みを聞いてくれた人狼に…、仇討ちに力添えしてくれた虎人に…。
「殺されかけたくせに、ユウはああだ」
カウンター代わりのテーブルの脇でザクロココアを啜りながら、ヨルヒコが仏頂面で呟いた。
「アレは元来憎み憎まれが得意な性格でもない」
フータイが応じると、若き人狼は「まぁアイツには確かにそういうトコあるけどさぁ…」と顔を顰める。
「ヤチもどういう訳か肩入れしてるし。…そういえば今日は見ないな?」
「ヤチは今日、雌狐に同行して件の親分の所へ行っている。それと、あいつは懐が広い訳ではないが、気に入った相手には寛
容だ。あの姉弟の事、遺言に従って可能な限り守ってやるつもりなのだろう」
ハンイーという名の男がどんな事を語ったのかは、銀狼のかいつまんだ話からしか知らない。だがヤチの心を動かし、味方
に付けられるだけの器だったのだろうと、フータイは思う。
ヘイシンの態度からは窺えないが、彼女程の強者が己と弟の身を預けていた事からも、信頼されていたらしいと察しは付く。
ヤチが気に入り、遺言を聞き届けてやりたくなるような人間…。
興味はあったが、もはや言葉を交わす事は叶わない。それがいささか残念にも感じられた。
「そう言うフータイさんだって、ウーシンはともかくあの大女の事まで、まんざら嫌いでもなさそうじゃないか?」
不機嫌そうな顔のまま、ヨルヒコは口を尖らせる。
「他人と思えないような境遇ではある。そのせいだ」
否定するかと思ったのだが、割と素直に師が認めてしまったため、ヨルヒコは二の句が次げなくなった。
彼自身はヘイシンの事が嫌いである。義弟が殺されかけ、自分も死にかけた。ユウがきさくな態度を取っているせいで大き
な声では言わないが、ヘイシンに処分が下されないばかりか、彼女が客人待遇されている事に不満を持っている。
「そう言うお前も、ウーシンには随分と骨を折ってやっているようだが…?」
珍しくからかうような色を目に浮かべた師に、ヨルヒコは顔を顰めて見せた。
「だってウーシンは関係ないから…。あの子はあの子、姉は姉だ」
「その割り切り方を突き詰めて行くと、ユウのような境地に達するのだろうな」
「…へ?」
目を丸くして素っ頓狂な声を漏らしたヨルヒコは、しかしすぐさま表情を険しくした。
ユウに促されたヘイシンが、テーブルに歩み寄って来たせいで。
図々しくも飲み物を貰いに来たのか?そんな事を考えたヨルヒコは、ヘイシンにじろっと見られ、少し首を縮める。
このジャイアントパンダの事は気に入らないが、腕っ節で敵わないのは重々判っている。
「…な、なんだよ…」
先程までの威勢がなくなったヨルヒコを、笑いを噛み殺して見つめるフータイ。そんな虎人へ、ヘイシンは鼻をひくつかせ
ながら向き直った。
「何か飲むか?」
フータイの言葉に頷き、ヘイシンは再びヨルヒコを見遣る。
「そこの狼が飲んでるヤツ、くれるか?」
それを聞いたヨルヒコが意外そうに目を大きくした。
一瞬胡乱げな顔をしたフータイは、しかし何も言わずにパックを開けて鍋に注ぎ、小型コンロの火にかける。
やがてカップに入ってあてがわれた熱いザクロココアを見下ろし、しばし匂いを嗅いだ後、ヘイシンは一口啜り、動きを止
めた。
「口に合わないなら無理をするな」
ヨルヒコ御用達のザクロココアは市販の飲料なのだが、独特の甘みと苦みとえぐみのせいで激しく評価が割れ、十人に一人
は病みつきになるが、十人に九人は一度飲んだらもう結構という扱いである。
受け付けない派かと思って声をかけたフータイに、ヘイシンはしばしあってから首を横に振った。
「…悪く…ない…」
そう呟いたヘイシンは涙を零しかけ、目尻をそっと指で拭う。
その寂しげな顔に、口の端に浮かんだ微かな笑みに、ヨルヒコは毒気を抜かれて見入った。
(そうか…。これがお前の好きだった味なのか、ハンイー…)
小さなカップを大きな両手ですっぽりと覆い、フータイに会釈したヘイシンは弟の所へ戻ってゆく。
その、少し丸められた肉付きの良い大きな背中を見送りながら、ヨルヒコはぬるくなってきたザクロココアをぐいっと飲み
干し、仕方がないなぁとでも言いたそうにため息をついた。
「急に静かになったな?」
師の言葉に小さくかぶりを振り、若き人狼は苦々しげに呟いた。
「…ザクロココアが好きなヤツに、悪人は居ないから…」
木箱の蓋が除けられると、和服の老人は珍しい物でも見たように目を大きくした。
「ほほう。コレが…」
「はい。件の殺し屋でございます」
ヤチが開けた木箱の中へ視線を向け、タマモが頷く。
一抱え程の桐箱に収まっているのは、豹の生首であった。
声も出せないまま、レパードは心の中で喚く。
違う!俺じゃない!と。
ヘイシンに破壊され、死ぬ間際にヨルヒコにとどめを刺され、カースオブウルブスによって死にきれなくなったレパードは、
そのまま頭部だけを回収された。
何故そんな事をしたのかというと、理由は当然ある。
ハンイーの意を汲み、遺言を叶えてやりたくなったヤチは、しかしこの状況ではヘイシンがその命をもって落とし前をつけ
なければならなくなる事も判っていた。
今回の件はトライブ内だけで終わらせられる物ではない。タマモの古馴染みであり、ヤチも何かと世話になっている名の知
れた極道の大親分も、傘下の人員を殺されているのである。
だからこそ、ヤチは一計を案じた。
あの事件から一夜が明けた朝、ヤチはヨルヒコに回収させたレパードの生首を持参し、ホテル地下にある小さな和室でタマ
モに謁見した。
そしてハンイーから託されたカードを渡し、自分の希望を述べたのである。
「…つまり、大親分さんに嘘をつけというのね?ヤチ君」
タマモは当然いい顔をしなかった。彼女にしてみればいずれ婿に迎えるはずのユウを殺されかけている。平静を装う外見ほ
ど、胸中は穏やかではない。
そのユウの、実の兄と言っても過言でないヤチからの予想外の提案は、彼女を大層驚かせた。
「どうしてあの女を庇おうとするの?」
「あの女のためじゃない。幼くして死の刻印を受けたその弟のためだ。…そして、ヤツの兄のような男の願いを、できれば聞
いてやりたい…」
畳に正座し、土下座して、ヤチは先を続ける。
「タマモさんには不義な真似をさせてしまうと判っている。だが、聞いてくれ…」
レパードを全ての殺しの犯人という事にし、親分に納得してもらう。それが、ヤチの立てた計画であった。
タマモが嫌がる事は承知していたので、手土産として口実に使うレパードの首と、ハンイーから預かったカードを差し出し
ている。だが…。
「あのねヤチ君…。親分さんは同志ではないものの、私から見れば大切なひとなのよ…」
「判っている。亡くなった旦那さんと五分の杯を交わした仲だと、ビャクヤから以前聞いた」
生前を知らず、写真でしか見た事が無いが、恰幅の良いタマモの夫は、自分とビャクヤの父とも親友であったと聞いている。
自分の父がタマモのトライブに参加したのもその繋がりからだという事も…。
夫の親友はタマモにとっても盟友。いわば自分から見たフータイのような相手に嘘をつけと言うのだから、ヤチにも葛藤は
あった。
「義に欠ける事は承知している。だがそこを曲げて、どうか…!」
平伏するヤチを困り顔で見下ろしていたタマモは、音も無く開いた横の襖を見遣る。
一瞬遅れて気配に気付いたヤチは、タマモ同様に横を見遣り、訝しげに眉根を寄せた。
「フータイ?」
無言で上がり込むなりどっかと腰を下ろし、あぐらをかいたフータイは、しばし何か考えている様子であったが、やがて心
を決めたように顎を引き、深々と頭を下げる。
「何の真似かしら?」
言葉少ない虎人の行為に困惑したタマモに、フータイは頭を下げたまま切り出した。
「これまで食客という扱いだったが、そろそろ身を落ち着けるべきかもしれんと考えた。差し支えなければ、正式にこのトラ
イブの一員に加えて欲しい」
この申し出に、タマモは仰天した。
ほぼ字伏ファミリーの一員となっているフータイだが、過去の行為へのけじめとしてトライブに正式参加はしていない。
タマモなどは同志として迎える事を望み、打診もしているのだが、頑なに拒み続けていたのである。
雌であるタマモを頭として頂く事に抵抗を感じている事もあり、正式に下につく事を固辞してきたフータイが、自ら配下と
なる事を切り出した…。
その事が、タマモにある確信を抱かせた。このタイミングで急にそんな事を言い出したフータイは、間違いなく代わりの何
かを求めているという確信を…。
「…交換条件として、あのパンダを殺すなと言いたいのかしら?」
「どう取って貰っても構わん」
否定しなかったフータイの頭を見下ろしたまま、タマモはため息をつく。
さらに正面ではヤチが再び土下座している。国内屈指の強者であろう二人の雄の平伏で、タマモは目のやり場に困った。
「…判ったわ…、善処しましょう…」
一応は嘘で通してみるが、もし親分が納得しなかったら改めてヘイシンの命を差し出す…。そういう条件をつけて、タマモ
は首を縦に振った。
撃ち合わせた通りに嘘の説明をするタマモの話に、時折相づちを打ちながら静かに耳を傾けた大親分は、しかしヤチの心配
をよそに、疑う様子も見せなかった。
「話は判った。今回も苦労をかけてしまったねタマモちゃん」
タマモをちゃん付けで呼べる唯一人の存在である大親分は、レパードの首は処分して良いと告げた上で、礼の話に移る。
(どうやら上手く行ったようだ…)
やがて話も終わり、ほっとしながらタマモと共に席を立ったヤチは、
「ああ、そういえばヤチ君よ」
呼び止められ、少し身を固くしながら足を止めた。
「聞けばユウ君も酷い目に遭わされたそうじゃないか。相当じゃなぁ、其奴」
「ええ、まぁ…」
歯切れ悪く応じたヤチは、抱えた箱に親分の視線が注がれていて落ち着かない。
もしや疑いを抱かれたのか?そう心配になり始めたヤチは、
「良い牛肉がある。土産に持たせるよう言っておくでな、たんと食わしてやんなさい。君と同じで大食らいだからなぁ、ユウ
君は」
そう続けられ、再びほっとした。
「気をつけるのよヤチ君。私の旦那は、親分さんに美味しい物をたっぷり食べさせられてまん丸くなっていたんだから」
コロコロと笑うタマモに、緊張が解けたヤチは笑い返す。
「大丈夫だ。その点については、ユウは既に手遅れだから」
最後の一発となる花火が上がり、溶けるように夜空に消えると、ヘイシンは弟の顔を見遣った。
「どうだった?」
「うん。綺麗だった」
心なしか以前より元気になったようにも見えるウーシンは、大きく頷いて笑みを浮かべる。
ウーシンは普段ならホテルシルバーフォックスの地下で大人しくしているのだが、今日は特別という事でこの部屋に連れて
来られた。
パンダが珍しいのか、診察や食事でウーシンが移動する度、会う者全てが構って来る。
最初こそウーシンの体に障るのではと心配していたヘイシンだったが、しかし弟が目に見えて明るくなり、はっきり受け答
えするようになり、大層驚いていた。
まるで、関わり合う事で元気を分けて貰っているかのように…。
それもそのはずで、今ではすっかり調子が良くなったユウが、頻繁にウーシンに接触してはその希有な能力で己の活力を分
け与えていたのである。
しかし、動けるだけの元気を彼がくれているという事に、姉弟は気付いていない。
「再来週にも新春花火大会があるんだよ?」
「本当に?見たいなぁ」
ユウに話しかけられて顔を輝かせている弟を眺めながら、ヘイシンは思う。
もしかしたら自分は、長年守り続けてきたつもりになって、その実、ウーシンを閉じ込め続けて来ただけだったのではない
かと…。
知らなかったとはいえ、治らぬ病に蝕まれたウーシンに必要だったのは、その短い時間を共有できる、他者との関わり合い
だったのではないかと…。
「ヘイシン」
不意に名を呼ばれ、物思いに耽っていたヘイシンは我に返る。
虎人がドアの前に立ち、ついてこい、と顎をしゃくっていた。
腰を上げてベッドから離れたヘイシンは、入れ替わりにベッドに寄った若い狼がややたどたどしい広東語でウーシンに話し
かける様子を横目に、フータイに続いて部屋を出る。
ドアを閉め、廊下に出て二人きりになると、フータイは左右を見回してから口を開いた。
「たった今連絡があった。お前の処遇が決まったそうだ」
死刑宣告。そう覚悟して頷いたヘイシンに、虎人は厳つい顎を動かして告げる。
「ウーシンの看病が必要な間は、タマモ御前の食客として協力し続ける事。狩人に任される類の危険な仕事も申しつけられる
だろう。覚悟しておけ」
ウーシンの世話をして貰えるのだから、その程度は何でもない。短く頷いたヘイシンは、
「以上だ」
フータイがそこで話を打ち切りにかかったので、拍子抜けして目を見開く。
「待て。以上?以上って事はないだろう?その後のあたしの処分はまだ決まってないのか?」
「今伝えたのがお前の処分だ」
「だからその後だ。ウーシンの看病が必要無くなったら…」
ヘイシンの言葉が終わらぬ内に踵を返したフータイは、ドアノブ掴みながら口を開く。
「その後は好きにさせるとの事だ。後を追うなり、故郷に帰って墓を作ってやるなり、勝手にすればいい」
つっけんどんにそう言うと、フータイは思い出したように振り返り、付け加えた。
「言っておくが、妙な気は起こすなよ?ウーシンはこちらの手の中にある。もしも妙な真似をしたら…」
剣呑な光を瞳に瞬かせた虎の前で、ヘイシンは唾を飲み込み、
「晩飯後、ウーシンに出るデザートが安物になる」
そんな言葉を受け、口をぽかんと開けた。
一瞬遅れてからかわれたと気付いたヘイシンは、鼻面に皺を寄せつつ何か気の利いた事でも言い返そうとしたが、思いつく
前にフータイがさっさと部屋に戻ってしまい、一人ぽつんと廊下に取り残された。
「…結局出るんじゃないか、デザート…」
居なくなってしばらくしてからややズレた事を呟き、ヘイシンは俯いた。
お咎め無し。そう言っても良い処分である。
何故こんな事になったのかと考えた彼女は、ハンイーが息を引き取る前に口にしていた言葉を思い出した。
「…ここの連中…、ハンイーの頼みを聞いてくれたのか…?あいつの遺志を汲んで…」
馬鹿じゃないか?そう思った。
敵であるハンイーの言葉を聞き入れ、敵である自分を赦し、敵である自分の弟を守ってくれる…。これほどの馬鹿は見た事
が無かった。
「…ありがとう…」
ハンイーへの礼なのか、フータイへの言葉なのか、それとも他の誰かへ言いたかったのか…。俯いたまま礼の言葉を呟き、
ヘイシンは誓う。
気の良い馬鹿達への恩返しと償いのために、また拳を振るう事を。
フータイが言った危険な仕事を申しつけられるという事についても、願ったり叶ったりであった。闘う以外に能がない自分
にはこれ以上ないほど向いた仕事だと、自信を持って言える。
死を免れたからなのか、それとも償いとして仕事を与えられると聞いて気が楽になったからなのか、ヘイシンの目には以前
とは違う輝きが宿っていた。
時間まで精一杯生きる弟…。彼を守ってくれるトライブの為に働くのは正当な事に思えた。
ウーシンが眠りにつくその日まで傍にいて、皆には全力で恩返しをし続ける。
新たな決意を胸に、ヘイシンはドアノブに手をかけた。
ヘイシンの素性はトライブ内に知れ渡っている。
タマモが彼女に与えた処分を知らされても快く思っていない者が多かったため、しばらくは針の筵であった。
だが、タマモから依頼される件をお目付役の狩人達と共にこなしてゆく、寡黙でぶっきらぼうだが、働き者で弟思いのジャ
イアントパンダの姿は、トライブの同志達との間に横たわった確執を、徐々にだが、着実に溶かしていった。
被害にあった本人であるユウや、その家族が、わだかまり無く彼女に接している姿も、同志達に受け入れられる大きな要因
となっていたのは言うまでもない。
そして、事件から二ヶ月が経ち、暦は二月の末となる。
「ただいま、ウーシン」
一見すると病室とは思えない、派手さは無いが高級そうな家具が取りそろえられた部屋に足を踏み入れ、仕事を終えて戻っ
たジャイアントパンダはベッド上の弟に声をかける。
そして、その傍らで椅子に腰掛けている若者達の顔を順番に見回した。
「また来てたのか、お前ら…」
呆れているような、しかしまんざら悪い気もしていないような口調で、ヘイシンは呟く。
「お帰りなさい姉ちゃん」
「お邪魔してます。ヘイシンさん」
「お疲れ」
弟の返事に続き、広東語の挨拶が二つ飛んでくる。
ウーシンのベッド脇に居るのは、白い熊と銀の狼。
それぞれが携帯ゲーム機を手にしており、同じ物がウーシンの手にも握られている事を見て取ると、ジャイアントパンダは
胡乱げに眉根を寄せた。
「それ、どうしたんだウーシン?」
「虎のおじちゃんがくれた」
笑顔を見せて応じるウーシンは、新品のゲーム機を翳して見せた。
「フータイ師父が?」
意外そうなヘイシンに、ユウが頷く。
「お昼過ぎにふらっと来て置いて行ったんです。あの通りぶっきらぼうに、僕らが使ってるのと同じ物を…。きっと、一緒に
遊べるようにって」
「興味無さそうだったのに、見てるもんだよなぁ…。ちゃんと間違えないで同じソフトをセットで買って来てるし」
ユウに続いて呟いたヨルヒコは、画面を凝視しながらボタンを操作し、日本語が読めないウーシンにあれこれ説明していた。
「…高いんじゃないのか?そのマシーン…」
警戒でもしているかのように硬い呟きを漏らしたヘイシンの、マシーンという呼び方が可笑しくて、ユウは微笑む。
「まぁ良いじゃないですか。フータイさんの好意なんですから」
「それに、同居人以外には金の使い道があんま無いひとだからなぁ…」
ヨルヒコの言葉に、ヘイシンの耳がピククッと過度に反応した。
「…フータイ師父は、誰かと同居してるのか?」
軽く動揺しているヘイシンは、のしのしとベッドに歩み寄ると、椅子にどっかと腰を下ろす。
「ああ、可愛いのとな」
ゲーム機の画面から目を離さずに応じたヨルヒコを、ヘイシンはまじまじと見つめた。
「可愛い!?…いや、あれほどの男、考えてみりゃあ周りが放っておかないだろう…。奥さんが居たって不思議じゃないか…」
ぶつぶつと呟くヘイシンが落ち着かなげに身じろぎしているのを見て、ユウは太い首を捻った。
「奥さんじゃないですよ?」
む?と首を傾げたヘイシンは、次いでハッと目を見開く。
「恋人と同棲中なのかっ!?」
違う。と言いかけたユウに先んじて、ヨルヒコは「まぁ、確かに恋人って言えるかなぁ」と、半ば上の空で返事をした。
「…そうか…。恋人と暮らしてるのか…」
どことなく元気が無くなったヘイシンの様子が気になったが、ユウはヨルヒコに急かされてゲーム画面に目を戻す。
「気になるならさぁ、行ってくりゃ良いじゃん?フータイさんのヤサ、場所は知ってるだろ?ほら、ウーシンがプレゼント貰っ
たお礼も言わなきゃいけないだろ?」
ゲームに集中しているヨルヒコが、面倒くさそうにしながらもそう言うと、ヘイシンはしばし迷った後、
「姉ちゃん、おじちゃんにお礼言いに行くの?お菓子とか持って?」
ウーシンにそう問われると、自分を納得させるようにブツブツと呟く。
「そ、そうだな…。お礼ぐらいは言わないと…だよな…。ケーキとか持って…」
慌ただしく支度を整えたヘイシンが、「すぐ帰ってきちゃダメだよ姉ちゃん」とのウーシンの言葉で部屋から送り出される
と、ユウは気になっているようにしばしドアを見つめる。
「ヘイシンさん…、勘違いしちゃったんじゃないかな…?」
「何で?どんな?」
相変わらずゲームに意識が向いているヨルヒコがカタカタとボタンを連打していると、
「ヘイシンさんはきっと、ヨル兄さんの説明を…、女の人と同棲しているとか、そういう風に取ったと思います…」
「は!?」
素っ頓狂な声を上げたヨルヒコが顔を上げると、ユウは困り顔になった。
「だって…、考えてみたらさっきは、同居してるのは豆柴だなんて、一言もいってなかったし…」
「いや…。え?いやでも…、え?何?俺ミスった?」
「ミスったー!」
可笑しそうにウーシンが声を上げると、ヨルヒコは画面に目を戻して「あー!」と叫んだ。
「一人で二死とか勘弁して下さい兄さん…。初めて遊ぶウーシンが頑張ってるのに…」
「だ、だって速いんだよこの兎!デブいのに!…うー…!ごめん…」
良いところを見せ損ねまくっているヨルヒコが肩に力を入れ直してゲーム機を覗き込むと、ウーシンはぽつりと言った。
「姉ちゃん。おじちゃんの事が気になってるんだ」
ん?と揃って顔を見たユウとヨルヒコに、ウーシンはゲーム機を操作しながら続ける。
「好きなんだよ。おじちゃんの事」
「すすす好きっ!?」
「フータイさんを?」
ヨルヒコは声を上ずらせ、ユウは少し驚いたように目を大きくして、それぞれ口々に聞き返すと、ウーシンは顔を上げない
まま頷く。
「判るよ。ぼく弟だから」
ウーシンの声は静かで淡々としており。ユウとヨルヒコは顔を見合わせた。もしかしたらこの子はヤキモチをやいているの
か?とも思って。
だが、違っていたと、すぐに思い知る。
「ぼくが死んでも、他に誰か好きな人が居たら、姉ちゃんは生きて行けるよね?」
咄嗟には言葉が出なかったユウが、何と答えるべきか迷っていると、
「そういう事、ヘイシンの前では絶対に言っちゃ駄目だからな?」
ヨルヒコが少し厳しい口調でそう言い、ウーシンは素直に頷く。
「そうだな…。死にたくないってだけじゃ、生きてく理由に足りないヤツも居るからな…。ヘイシンもそういうタイプかもし
れない。ずっとウーシンの為に生きて来た。だから、ウーシンが居なくなったら、生きる支えが無くなっちゃうかもだしな…」
どこか冷めた、しかし突き放す風でもない口調で、ヨルヒコは呟く。
ユウは不思議な気分になった。
時々だが、ヨルヒコはこんな風に一歩引いたように、客観的に、冷めた調子で分析を口にする。
そしてそんな時のヨルヒコの印象は、彼らの義兄であるヤチに極めて似通っているように感じられる。
これが人狼という種特有の物なのか、それともヤチの影響で変わりつつあるのか、ユウには判断がつかない。
だが確信している事もある。
それは、自分は恐らくヤチやヨルヒコのようにはなれないだろうという事…。
自分達の内でどちらか一人だけが狩人になれるとしたら、それはきっとヨルヒコの方だろうとも思う。
それは腕前とは別の問題である。狩人としての資質において、精神的にも物の考え方でも、ヨルヒコの方が自分より上だと
認識している。
最も歳の近い義兄を少し遠くに感じながら、ユウはウーシンに視線を向けた。
心なしか疲れているようにも感じられ、眠そうに見える。
「ウーシン。これが終わったら少し休もうか?おやつ食べて、昼寝しようね」
優しく微笑むユウに、新しい遊び道具を得たばかりのウーシンは、物足りなさから少し不満の色を覗かせたが、しかし結局
首を縦に振った。夕食後にまた一緒にゲームするという約束を取り付けて。
そんなユウを視界の隅で窺いながら、ヨルヒコもまた思う。
自分はきっと、ビャクヤやユウのようにはなれないだろう、と。
ユウは狩人に向いていないほど優しい。だが、その包み込むような柔らかさと暖かさで皆を安心させ、リラックスさせられ
る素質は、努力や鍛錬で何とかなるような物には思えない。
ビャクヤのように、弱者を守るだけでなく心から安堵させられるような者には、きっと自分はなれない。だがユウならきっ
と彼に近い男になれる。そんな予感がある。
いずれショウコが次の玉藻御前となったら、ユウはその夫として、今は空席となっている補佐官的な立場につく。そうなれ
ば当然狩人などできないのだが、そのポジションの方がユウに向いているような気もした。
(俺は矛だけど、ユウは盾だ。適材適所って言葉もあるしな…)
やがてゲームを終わらせ、おやつも終えた後、慈愛に満ちた大きな手でウーシンの体を支えてやり、倒したリクライニング
ベッドに寝かせると、ユウは腰を上げた。
「夜にまた来るからね」
「きちんと寝るんだぞ?」
ヨルヒコもそう告げてユウに倣い立ち上がると、ウーシンは掛け布団の下から手を出し、その銀の手を握った。
「あの…。お願いがあるんだけど…」
「ん?何だ?」
腰を折って顔を近づけたヨルヒコを真っ直ぐ見つめ、ウーシンは落ちかける瞼を必死に上げ、眠気に抗いながら言う。
「ぼくが死んだ後も、お姉ちゃんをここに居させてあげてくれる?」
「馬鹿言うなよ。そういう話は無しって言ってるだろう?」
「お願いだから、真面目に聞いて」
いつになく強い口調でウーシンが言うと、ヨルヒコは少し間を開けてから「聞こう」と頷いた。
ヤチを思わせる落ち着き払ったその態度と、ウーシンが言いたい事が気になって、ユウが不安そうな視線を向ける。ウーシ
ンはひょっとして、自分達とこの話がしたいから姉をフータイの所へ行かせたのではないかと、急に思えて来た。
姉を除けば、今この少年と最も頻繁に言葉を交わし、親しくしているのは、他でもないユウとヨルヒコなのだから。
ヘイシンと彼らトライブの間にある取り決めや、ハンイーが死んだ事、そしてウーシン自身の余命については、少年には伏
せられている。
だが、おっとりしているように見えるウーシンは、実は勘が良い事を、ユウ達は察していた。
おそらくは知らないふりをしているだけで、この少年は気付いているのでは?ユウは時折そう思っている。
「お姉ちゃん、ぼくの病気を治すために役目を捨てて飛び出してきたから、もう村には帰れないんだ。だから…、他に行く所
がないから…、このまま、皆の仲間にしてあげてくれない?」
懇願する少年の目を真っ直ぐに見返し、ヨルヒコは口を開く。
「確約はできない」
その、事務的ともいえる淡々とした口調が、ユウに不安を与えた。
嘘でも良いから、せめてウーシンの言う事には色よい返事をしてやって欲しかった。
ユウが見かねて口を開こうとしたその時、一瞬早く、「だけど…」とヨルヒコは続ける。
「他でもない友達の頼みだからな。俺達の兄貴に掛け合ってみる」
安堵した様子でウーシンが表情を緩めると、ヨルヒコはその手を布団の中に戻してやった。
よほど我慢していたのだろう、すぐに寝息を立て始めたウーシンを残し、二人は静かに部屋を出る。
そしてシルバーフォックスの地下通路を並んで歩みながら、トーンを落とした声で囁き交わした。
「あと一ヶ月程度か…。あっと言う間だよな、三ヶ月なんて…」
「この小康状態がいつまで続くか判りませんけど…」
ユウは言葉を切り、目を伏せた。
「僕の「力の譲渡」で渡す活力の受け入れ量が、日に日に減っています…。たぶんもうすぐ全く受け付けなくなる…」
ウーシンがまだある程度の元気を保っていられるのは、ユウが触れて生命力を分け与え続けているからである。そうでなけ
れば衰弱はもっと進行しており、動く気力も残っていないはずであった。
それでも、ユウの力では根本的な解決にはならない。
食べ物を殆ど吸収できないウーシンの肉体は、物理的に質量を減らし、疲弊してゆく。一時的に活力を得ても延命には至ら
ないのである。
「強い子ですよね…」
「だよな…」
ふっと笑みを浮かべ、ヨルヒコは頭の後ろで腕を組んだ。
「俺さ、自分の寿命が残り三ヶ月とか知ったら、あんな風に笑ってられる自信無いよ」
「僕もです。きっと取り乱すと思う…。僕も、ヤチ兄さん達も…。その点、ウーシンもヘイシンさんも強いですよ…」
「…ヘイシンの事はいまいち好きになれないけど…、ウーシンの姉貴なんだ、ヤチやフータイさんに頼んでみるか…。あ、そ
うだユウ」
何か思い出したように声を高くし、ヨルヒコは足を止める。
つられて立ち止まったユウが顔を向けると、ヨルヒコは義弟の突き出た腹に軽くボディブローを入れ、ぼよんと揺らした。
「お前さ、ショウコさんとタマモさんのご機嫌とって、ヘイシンの事お願いしてみろよ。な?未来のナンバー2!」
「またすぐそう言うんですから…」
打たれた腹を隠すように手で防ぎながら、ユウは顔を顰めていた。
「おかえり、姉ちゃん」
静かに室内に入ってドアを閉めたヘイシンは、寝ているとばかり思っていた弟の声を背中で聞き、振り返った。
「起こしたか?ごめんなウーシン」
歩み寄った姉に優しく頭を撫でられ、ウーシンはくすぐったそうに目を細める。
「おじちゃんの家、どうだったの?」
「秘密基地みたいだった。あと、可愛い犬が居た。こんな小さいのが」
釣った魚のサイズでも示すようにして、ヘイシンが両手で大きさを表現すると、ウーシンは可笑しそうに笑う。
「しかし…、あの狼小僧め、よくも騙してくれたな…!」
ヨルヒコにその気はなかったのだが、結果的に勘違いさせられてしまったヘイシンは不機嫌そうに唸る。
相性があまり良くないのか、深くはない溝がなかなか埋まらない両者であった。
気を取り直してベッド脇の椅子に腰掛け、帰りに買ってきた焼きプリンを弟に食べさせてやりながら、ヘイシンは思う。
先程までのようにユウやヨルヒコが訪ねて来てくれるおかげで、ウーシンは毎日を楽しく過ごしている。
ショウコや赤ん坊狼を伴ったヨウコも頻繁に顔を見せ、パンダが珍しいのか、それとも気遣っているのか、様々な者が土産
を手に部屋を訪れる。
言葉の壁は、広東語が理解できる青年達のおかげで障害になっていない。
彼女自身は償いとしてそれなりに危険な仕事も任されるが、穏やかな日々だと思う。
「姉ちゃん」
「…ん?」
束の間物思いに耽っていたヘイシンは、弟に呼びかけられてその顔を見遣る。
「姉ちゃん、ここの人達の事、好き?」
「…まぁ…な…」
歯切れ悪く応じたヘイシンに、ウーシンはにこやかに笑いかけた。
「ぼくも好き!ずっとずっと、ここに居たいね!?」
「そうだな…」
ヘイシンは弟の頭を撫でてやりながら、目を細めた。
ウーシンにとって彼らは良き友人以外の何者でもない。自分と違って何のしがらみも無く付き合える弟が、少し羨ましく感
じられた。
「ぼくの病気が治っても、ずっとここに居るの?」
本心を隠したウーシンの問いに、腕組みをして「う〜ん…」と顔を顰めたジャイアントパンダは、
「お前がそんなに気に入ってるんなら、頼んでみるか」
弟を励ますつもりでそう頷いた。
「お姉ちゃんもだよ?ずっとここに居てよね!ヨルヒコ兄さんとか、ユウ兄さんとも、おじちゃんとも仲良くして…」
「おい、あたしもか?」
「当たり前でしょ?」
ウーシンが口を尖らせると、「仕方ないなぁ」と苦笑いし、ヘイシンは頷いた。
この時の会話が、腰を落ち着ける居場所を与えたいという弟の願いから出たものだった事に彼女が気付くのは、ウーシンが
発作の苦痛を抑える薬を投与され始め、一日の殆どを眠って過ごすようになってからの事であった。
それから一ヶ月と少し後、春一番が吹いた日差しの強い日の夕刻に、ウーシンは逝った。
顔を見に来た字伏一家と小一時間ほど談笑し、トウヤを抱いてあやした、僅か数時間後の事である。
疲れて眠り、そのまま静かに鼓動と息を止め、姉に看取られながら眠って逝ったウーシンの顔は、苦痛の影は全く浮かばず、
穏やかな、ここ数ヶ月の寝顔と同じ顔であった。
「…よく頑張ったな…、ウーシン…」
ホテル付きの医師が死亡を確認した後、ヘイシンは弟の頭を撫でてやった。
激痛が伴う発作を何度も起こしながら、一度も泣き言を口にしなかった強い弟が誇らしかった。
「今は…、ゆっくり休め…」
ヘイシンが呟くと、ドアが勢い良く開く。
報せを受けたライカンスロープや同志の人間達が慌ただしく訪れる中、ヘイシンはそっとベッドから離れ、訪ねてきた中の
一人、大柄な虎の前に立った。
今日はバーを開けるつもりだったのだろう。仕事用の黒服に腰エプロン姿のままやって来たフータイに、ヘイシンは深々と
頭を下げる。
「おかげで、静かに眠った…。感謝している…」
無言のまま頷きもせず、ベッドの上のウーシンに目を遣ったフータイは、
「お前の弟は立派な雄だ。病に泣き言一つ言わぬほど強い、見上げた漢だ。誇って良い」
口を真一文字に引き締め、漏れそうになる嗚咽を堪えてヘイシンは頷く。
「…行け。ウーシンには、見せたくないのだろう」
フータイの言葉を受け、ヘイシンは足早に部屋を出た。そして後ろ手にドアを閉めると、
「う…、うぅ…!うぅううううっ…!」
天井を見上げ、肩を震わせ、喉を鳴らし始めた。
「うわあああああああああああああああああああああああああああああああああああぁぁぁぁぁぁっ!!!」
程なく堪えきれなくなり、滂沱となった涙で頬を濡らし、ヘイシンは泣き出した。辺りを憚る事なく大声を上げて。
せめてウーシンには泣き顔は見せまい。そう決めて堪えていた涙は、いつまでもいつまでも、枯れる事無く流れ続けた…。
ヤチやユウ達と入れ替わりでたまたま訪れていたヨルヒコは、報せを聞いて駆けつけ、棒立ちのまま天を仰いで慟哭するヘ
イシンの姿を目にし、
「ああ…、そうか…」
ウーシンとはもう二度と話せないのだと実感し、気が抜けたような表情で立ち尽くした。
関係者のみが参列する葬儀が密かに行われ、ウーシンは火の洗礼を受けて旅立った。
そしてその遺骨は今、年末の作戦終了後に回収され、荼毘にふされ、ヘイシンが大切に保管していたハンイーの遺骨と共に、
彼女が肩にかけた大きなスポーツバッグに収められている。
ホテルシルバーフォックスの地下駐車場。
着替えを含めた僅かな持ち物と二人の遺骨だけを荷物に、ヘイシンは見送りに来たトライブの面々を見回している。
これから彼女はトガワが運転するワゴンで送られ、タマモの知り合いが所有する大陸行きの貨物船に乗り込み、日本を去る。
二人の遺骨をそれぞれの故郷へ戻してやるための帰国である。
古里の皆は温かく迎えてくれるだろうが、ヘイシンはあそこで暮らすつもりはない。
一度は狩人の役目を放棄して飛び出した身…、再びあの地で暮らす事は、他の誰でもなく彼女自身が認められなかった。
それでも、ウーシンは両親と同じ墓に葬ってやりたい。
そして、何処に親族が居るかも判らないハンイーについても、何とか手掛かりを得て、故郷に帰してやるつもりでいる。
ろくに当てもなく、調べながらの困難な旅になるが、諦める気は毛頭無い。
「世話になった」
深々と頭を垂れたヘイシンに、広東語をユウに通訳されたタマモは首を横に振る。
「相応の働きはして貰ったもの…」
場の雰囲気から何か感じているのか、ヨウコに抱かれたトウヤが不思議そうな顔で「へーちん、へーちん」と繰り返しなが
ら、ヘイシンに向かって短い手を伸ばす。
「ヘイシンお姉ちゃんはお出かけするんですよ、トウヤ」
息子をあやすヨウコの隣で、ユウが名残惜しそうに口を開いた。
「道中お気を付けて、ヘイシンさん…」
「そうよ。女の一人旅なんだから」
ショウコが追従すると、ヨルヒコが鼻を鳴らした。
「気を付けるたって、この大女をどうこうできるヤツが世界に何人居るんだよ?」
「一理ある。が、そういう事を言っている内はモテないのではないかな?ヨルヒコ」
フォウが考え込みながら真顔でそう言うと、若き人狼は言葉に詰まった。
「忘れ物は無いな?船に乗ったら途中で気付いても取りに戻れないぞ?」
「心配性だなぁ兄さん、子供じゃないんですから…」
ヤチに苦笑いを向けたユウの隣で、ソウスケが「こいつたまにオカンみたいな事言うよなぁ」と茶化し、「いや、割と頻繁
に言うぞ?」とクラマルが訂正する。
身を寄せていた三ヶ月、ヘイシンが骨身を惜しまず働いた事もあり、今ではトライブの同志達は仲間として見るようになっ
ていた。
相変わらずヨルヒコとはウマが合わないが、険悪というほど深刻ではなく、ユウ曰く「仲良くケンカする仲」との事である。
別れが済むのをワゴンの脇で待っていたドライバーの青年は、やがて腕時計を確認すると、「ヘイシンさん。そろそろ時間
です」と、控えめに声をかけた。
振り返って頷いたヘイシンは、一同の顔を順に見遣り、それから深々とお辞儀した。
「ありかト、みな」
たどたどしく口を動かしたヘイシンの口から出たのは、この三ヶ月で少しだけ覚えた、日本語での礼の言葉であった。
後部座席に乗り込み、手を振る皆に会釈したヘイシンは、ワゴンが走り出すと、隣に座る大男に広東語で話しかけた。
「必ず戻る。まだ恩を返し終わっていない」
護送役を買って出たフータイは、小さく鼻を鳴らした。
それは、呆れているようでもあり、面白がっているようでもあり、そしてほんのちょっとだけ嬉しそうでもある…、そんな
微妙な仕草であった。
「鎖を解かれ、ようやく手に入れた自由。勝手気ままに生きて行けば良い物を…」
「あたしとウーシンの為に…」
フータイの言葉を遮り、ヘイシンは口を開く。
「あんたはそれまでの主義を曲げて、玉藻御前の正式な配下になったって聞いた。あたし達の命を助ける交換条件で…」
それを聞いたフータイは渋い顔をする。
ユウか、ヨルヒコか、それともヤチか…、告げるつもりも無かった事を、誰かが口を滑らせて教えてしまったのだろうと察
しがついた。
「この恩は忘れない。必ず返す」
前を向いたまま頑なに繰り返すヘイシンに、同じく前を向いたままフータイは応じる。
「…酔狂な事だ…」
「惚れている?フータイに?」
「ウーシンはそう言ってたよ」
素っ頓狂な声を上げたヤチに、ヨルヒコは頷く。
駐車場から地下通路に戻り、固まって歩く一同に、軽いざわめきが広がった。
「もしかして、フータイさんも気付いてて、しかもまんざらでも無いんでしょうか?」
特に必要も無いだろう護送役をわざわざ買って出た大男の行動を改めて訝り、ヨウコはトウヤをあやしながら首を捻る。
「どうかな。ただ不憫に思っての事だと思うが…」
「そうね…、その配慮と思い遣りが、ヘイシンの気持ちを刺激しているという事はあり得ますよ」
マスタングが唸ると、シマウマが追従した。
「辛い時だからこそ、ちょっと優しくされるとコロッといくってか?」
山猫が誰にともなく訊ねると、周囲から一斉に『あるある』と声が上がる。
「単純に、自分を負かした相手だからってのもあるかもだけど?初黒星だったらしいし」
「それもあり得ますよね。ヘイシンさん、腕に自信があるから」
「ところで、フータイさんはデカ女の気持ちに気付いてると思う?」
「…ああいうひとだから、たぶん気付いて無いんじゃないかと…」
ヨルヒコとユウがそんな言葉を交わす横で、ヤチは面白がっているように口元を緩めていた。
「生涯独身。…なんてかっこつけていたが…、いつまで保つかなフータイ?」
帰郷と、ハンイーの故郷を探す旅を終えたヘイシンが再びこの街を訪れるのは、半年ほど後の事になる。
その時、殺し屋を廃業し、正式に仲間としてトライブに迎え入れられた彼女が、程なくフータイに続く五人目の狩人となり、
生涯通して恩返しに勤しみ続けるようになろうとは、まだ誰も想像していなかった。