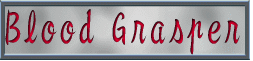
淡雪の白夜
梅雨明け宣言が出されてから一週間が経った。
山の緑はここ数日の間に一気に色濃くなって、とても生き生きしている。
生命力に満ち溢れた木々の中、あたしは額の汗を拭いながら、道とも呼べないような、通い慣れた山道を登っている。
まだ朝も早い時間帯なのに、もうかなり暑い…。
最近は暑い日が多くなって来ているけれど、今日は何℃まで上がるんだろう?
行く手に二股に分かれた木が見えた頃には、長い事歩いたあたしは、すっかり汗だくになっていた。
タオルで顔を拭いながら、馴染みの木の後ろに回り込んで、間を通り抜けてから振り返る。
何度も繰り返した、訪問する時の決まり事。
振り返ったあたしの視界に、それまでは何処にも見えなかった丸太小屋の姿が飛び込んで来る。
手すりのついたウッドテラスに囲まれ、上には煙突が生えた、童話に出てくるような小屋。
…それは、ほんの数ヶ月前まで、あたしの最愛の人が住んでいた小屋だ…。
たくさんの想い出が詰まったこの小屋に、彼はもう、居ない…。
いつものように居間とテラスの掃除をした後、あたしは棚から出した自分のマグカップを洗い、リビングの机に置いた。
そしてミニクーラーに入れて来たコンビニのおにぎりと、2リットルのペットボトルを取り出し、冷えた麦茶を注ぐ。
ウッドチェアに腰掛け、背もたれに体を預けながら、冷たい麦茶を喉に流し込むと、少し汗が引いてくる。
椅子にテーブル、戸棚に箪笥、ベッドすら、それどころかこの小屋までも、全てが元の住人の手作り。
凝り性だった彼が作った家具の数々はどれも、店で売っているものと比べても遜色ないレベルの、立派な出来映えだ。
彼が仲間達と一緒にここを出て行ってから、三ヶ月以上が過ぎた。
あたしは今でも、毎週欠かさず小屋を訪れて、掃除をしている。
ここは、あたしにとって大切な場所…。
心安らぐ、穏やかな時間を過ごせた場所…。
両親の離婚に際し、追い詰められた幼いあたしを受け入れてくれた場所…。
そして、その後のあたしに前向きさを与えてくれた、大切な恩人の住んでいた場所…。
ここを離れ、忘れる事は、あたしにはもうできないだろう。
だからいつまでも、未練がましく通い続けている。
通って、掃除して、いつも綺麗に保っている。
まるで、彼の帰りを待つように。
…どんなに待っても、彼が帰って来る事は、もうないのに…。
首に吊している木彫りのフクロウを弄りながら、ここで過ごした幸せな時間を反芻していると、突然ギシッと、ドアが音を
立てた。
ハッとして顔を上げたあたしは、椅子を倒しながら立ち上がってドアに駆け寄り、押し開ける。
期待を込めて庭を見回したけど、そこにはやっぱり誰も居ない。何もない。
木々の間を抜けてきた少し涼しい風が、あたしが勢い良く開けたドアを、ゆっくりと揺らした。
…小屋のドアが大きく軋んだり、風を受けた窓がガタっと音を立てる度…、彼が帰ってきたのかと勘違いする…。
そして…、期待を胸に外を見ては、肩を落とす…。その繰り返しだ…。
…彼は仲間の所へ戻ったんだ…。もう、ここには帰って来ない…。
あたし以外に訪れる相手も無い山小屋で、変わらない日々を過ごすより、仲間と暮らす方が、もちろん幸せだ…。
…そう、判っているのに…。
ドアを閉めたあたしは、また椅子に腰を下ろした。
少し出てきた風が、あたしをからかうように、何度も小屋のあちこちで音を立てた…。
昼食を終えたあたしは、最近いつもそうしているように、ぼんやりと、何もせずにリビングに居座り続けた。
幼い頃に彼から貰った、フクロウのペンダントを弄りながら…。
ふと携帯を取り出して時間を見てみれば、午後三時を回っていた。
今年、都会の大学へ進学した同級生から届いたメールを読み返す。
同級生や彼が関わっているはずの、ニュースを賑わせている一連の事件は、一応は終息したように見える。
でも、彼はまだ、あちらには着いていないらしい。
部外秘という事になるんだろう。普通の人間のあたしには、その同級生も詳しい内情は教えてはくれない。
それでも、彼があっちに着けば、きっと教えてくれるはずだ。
そうしたら、たまには電話で話せるかもしれない…。
また、並んで手を繋ぎたい…。
あの優しい声が聞きたい…。
そして顔が見たい…。
…彼に…、…会いたい…。
ため息をついて、何度も頭に浮かべた、どうしようもない事を考える。
…どうして、あたしは人間なんだろう?
…どうして、あたしは彼らと違うんだろう?
あたしも彼らの仲間だったなら、一緒に行く事も、許して貰えたかもしれないのに…。
どんなに考えても仕方がない事なのに、彼がここを去って以来、あたしは何度も何度も、繰り返しその事を考えてしまう…。
小屋の中の一室のドアを開け、中を見回す。
大きなベッドと箪笥がある、綺麗に片付いたその部屋は、彼の寝室だ。
ダブルベッドよりも大きな、手作りの寝台に歩み寄って、あたしは綺麗に整えてあるシーツの上に倒れ込んだ。
…彼の…匂い…。
鼻孔に入り込んだその匂いが、彼の事を鮮明に思い出させる。
長い前髪がかかった、キラキラと光を照り返す優しい瞳。
ふさふさと全身を覆った、良い匂いがする真っ白い毛。
抱き付くと安心できる、柔らかくてフカフカの体。
深みのある、穏やかで落ち着いた声。
…愛してる…。
会えなくなってしまった今でも、あたしはまだ彼の事を愛している。
彼への恋心は、あたしの胸の奥深くまで、まるで返しの付いた釣り針のように、しっかりと食い込んでいる。
無理に引き抜けば、ズタズタになってしまいそうな程に…。
これから先の生涯、彼を忘れる事はきっと無い。
彼以上に誰かを好きになる事も、たぶん無い。
ベッドに染みついた優しい匂いに包まれて、あたしは柔らかなシーツに顔を埋めたまま、涙を零した。
寂しくて…。哀しくて…。…会いたくて…。
顔を上げると、窓の外は暗くなりかけていた。
いつの間にか眠ってしまっていたあたしは、ベッドに手をついて体を起こし、立ち上がった。
頬にこびりついた、乾いた涙の跡をぐいっと手の甲で拭う。
…ちょっと遅くなった…。そろそろ夕食の支度をしなくちゃ…。
今日は元から小屋に泊まって行くつもりだったから、夕飯の材料も持って来ている。
リビングのランプと竈に火を入れ、野菜炒めとコンソメスープを作る。
コンビニで買った食パンとそれらが、今夜と明日の朝のご飯だ。
すっかりクセがついて、調理の際にも、食べ物を買う際にも、彼が嫌いなタマネギには過分に注意するようになってしまった。
今日のメニューにも、タマネギは一切入らない。
椅子にかけて、テーブルに並べた夕食を一人で黙々と食べていると、「ホウ」と、小屋の外で声がした。
窓に寄って外を見ると、ウッドテラスの手すりに、一羽のフクロウが行儀良くとまっているのが見えた。
あたしは野菜炒めに使ったベーコンの余り数枚を、これも彼の手作りの木の皿に入れ、ドアから外に出る。
顔見知りのフクロウは、あたしが近寄っても逃げる事無く、催促するように「ホッホウ」と鳴いた。
そのすぐ脇、平らな手すりの上に皿を置くと、フクロウはせっせとベーコンをついばみ始めた。
その様子を間近で眺めていたあたしは、気が付いたら、首に下げた木彫りのフクロウ親子を、無意識に弄っていた。
…これは、小さい頃からのあたしの癖だ。
このフクロウは、昔、彼がここでこのネックレスを彫ってくれた時、モデルになったフクロウとは別のフクロウだ。
彼が言うにはその子供という事だけれど、今では所帯持ちらしい。
この子は別に飼われていた訳じゃない。でも、野鳥でありながら、彼とあたしには気を許してくれている。
…この子も…、あたしと同じだ…。
彼が居なくなった後も、この小屋を訪れるのをやめようとしない…。
「彼はもう、帰ってこないのよ?あんた判ってるの?」
そう問い掛けると、フクロウは顔を上げ、あたしを見ながら首を捻った。
しきりに首を左右に捻るその様子は、幼い子供が「なんで?」「どうして?」と、不思議がっている様子にも似ていて、見
ていたら、涙が出そうになった…。
零れそうになる涙を誤魔化して、あたしは空を見上げた。
いくつかの細長い雲が浮かぶ夜空に、涙で滲んだ丸い月が光っていた。
彼が去って行ったあの日と、良く似た月が…。
三ヶ月も前の、あの日の夜…。
あたしと彼は、小屋からそう離れていない、いつも水汲みにやって来る小さな沢の傍に居た。
やっと春が訪れ、少し前までの身を切るような厳しさが消えた、ゆるやかな風に髪をなぶらせながら、あたしは横倒しになっ
た巨木に腰掛けていた。
あたしの隣には、黄色いティーシャツにオーバーオールを身に付けた大男が、並んで腰を下ろしている。
いつも同じ服装をしている彼の顔は、あたし達とはかなり違う。
前に少し突き出た鼻と顎。長い前髪と垂れた耳。白く、ふさふさした毛に覆われた大きな体。
その顔は犬、オールドイングリッシュシープドッグに良く似ている。
字伏白夜(あざふせびゃくや)。それが彼の名前。
彼は人間じゃない。ずっと昔から、人間の中に紛れ込んで生きてきた、人間以外の種族。
けれど、あたしにとっては、そんな事は些細な事だ。
穏やかで優しくて素敵なビャクヤを、あたしは心の底から、この世の誰よりも愛している。
「…そろそろ、行くよ…」
ぽつりと呟いた彼の言葉に、あたしは努力して頷いた。
止める事はできない。ビャクヤには、やらなくちゃいけない事がある。
仲間達を助ける為に、そして、あたしのクラスメートの力になる為に…。
これから危険の中に身を投じるはずの彼は、「どうして?」と、訊きたくなる程に穏やかだった。
でも、その穏やかさは、いつもの穏やかさとはほんの少し違っている。
例えば、澄んだ泉の水面が、そこに映る天気によって色を変えるように…。
いつもの、晴れた空を映した水面のような彼の穏やかさは、曇り空を映した水面の静かさになっていた。
ゆっくりと立ち上がったビャクヤは、座ったままのあたしの頭に手を伸ばす。
「…さよなら。アサヒちゃん…」
少し掠れた声と、寂しそうな微笑み…。
頭にその大きな手が触れる寸前に、あたしは思い出した。
大きな手を払い除けて立ち上がり、あたしはビャクヤから数歩遠ざかる。
驚いたような顔をしているビャクヤの顔を見上げ、あたしは首を横に振った。
「あたしの記憶を、消すつもりなんでしょう?」
ビャクヤは一度息を吸った後、口を一文字に引き結んだ。
『ビャクヤはきっと、カワムラの記憶を消そうとする。それが、カワムラにとって幸せな事だって、思ってるはずだ』
…危なかった…!イミナからの手紙で注意されていなければ、きっとそこまで頭が回らなかったわ…。
ビャクヤはその不思議な力で、人の記憶を消す事すらできる。
その事をあたしよりも詳しく知っていた同級生は、ビャクヤは別れの前にあたしの記憶を消していくつもりだと、残していっ
た手紙の中で警告してくれていた。
「…きっと…、そうするのが一番良いんだ…」
ビャクヤは静かに呟いた。前髪の奥で光る目に、寂しげな光を湛えながら…。
「僕の事も、この山での事も、全部忘れて普通の生活に戻る事が…、一番…」
「普通って何よ!?」
叫ぶように発したあたしの問いに、言葉を遮られたビャクヤは口を閉ざす。
「あたしにとっての普通は、ビャクヤが居る生活よ…!」
言葉を叩きつけるあたしを、ビャクヤは無言のまま、静かに見つめる。
「ビャクヤとの想い出が消えたら、あたしはもう、あたしじゃないっ!」
「…アサヒちゃん…」
「初めて会った時、ビャクヤが居たから、あたしは両親の離婚を乗り越えられた…」
話しながらも涙がこみ上げて来て、視界が滲んだ。
「ビャクヤが居たから、この町を離れて、友達も居ない所へ引っ越しても、なんとか頑張れた…!」
溢れた涙が、頬を伝っていった。
「ビャクヤが居たから、勝気で自信に満ちた、強い自分を装って来られた!」
顎の先から、涙が胸に落ちていった。
「ビャクヤとの想い出が無くなったら、あたしは…!」
言葉に詰まって、それ以上何も言えなくなってしまった。
俯いて、喉の奥からこみ上げてくる嗚咽を押し殺すだけで精一杯のあたしに、
「…ごめん…」
ビャクヤの声が、静かに届いた。
ゆっくりと歩み寄ったビャクヤの顔を、あたしは見上げる。
「もう、記憶を消そうなんて考えないよ。…ごめん…」
その「ごめん」はきっと、あたしの意見を考えなかった事への「ごめん」…。
そして、辛い別れを経験させてしまう事への「ごめん」…。
傍で見つめあうあたし達の間に、ふわりと、白い物が舞い降りた。
三月も末のこの時期、それほど寒くもないのに淡雪を降らせ始めた空を、あたしとビャクヤは見上げる。
雲も殆ど出ていない、丸い月が浮かぶ夜空から、ふわり、ふわりと、音も無く雪が舞い降りる。
雪のように真っ白なビャクヤの旅立ちに相応しい、空からの贈り物…。
音も無くフワフワ舞い降りる淡雪は、あたしの目にはそう映った…。
しばらく無言で空を見上げた後、あたし達は顔を下ろして、再び見つめ合った。
体に、地面に触れれば、雪は影のような薄い染みを残して消えてしまう。
そんな儚くも綺麗な雪が舞い降り続ける中、静かに持ち上げられたビャクヤの大きな手が、あたしの頭にポンと乗せられた。
温かくて大きな白い手が、あたしの頭をゆっくりと、優しく撫でる。
「…元気でね…、アサヒちゃん…」
一度は押さえ込んだ涙が、また、堰を切ったように溢れ出した。
あたしは喉の奥から嗚咽を漏らしながら、ビャクヤの太り気味の大きな体にしがみついた。
柔らかくて、温かくて、優しい感触…。
二度と触れる事ができなくなるんだと考えたら、ひび割れて、バラバラに砕けてしまいそうに、心が痛んだ。
柔らかなお腹に顔を埋め、オーバーオールを涙で濡らすあたしを、ビャクヤはそっと、優しく抱き締めてくれた。
震えていたのはあたしだろうか?それとも、背中に回された逞しい腕の方だったんだろうか?今でも、良く判らない…。
「ビャクヤ…!」
身長差があるあたしは、ビャクヤのお腹、鳩尾辺りに顔を埋めながら、震える声で告げた。
「あたし…、ずっと…、ずっと忘れない…!いつまでだって、ビャクヤの事、覚えてる…!」
ビャクヤが小さく頷いたのが、見なくとも気配で分かった。
「僕も、ずっと…忘れないよ…」
頭上から投げかけられる月の光が、重なり合ったあたしたちの影を、くっきりと地面に張り付けていた。
あたしが漏らす嗚咽が止まるまで、しばらくそのまま抱き締めていてくれたビャクヤは、やがて、ゆっくりと腕を放した。
顔を上げたあたしの目をじっと見つめながら、ビャクヤは一歩後退して身を離し、泣き笑いの表情で、別れの言葉を口にした。
「今までありがとう…、アサヒちゃん…」
あたしは…、
「行かないで!」
喉を突いて出かかったその言葉を、無理矢理飲み込んだ。
…その言葉が、あたしとビャクヤを苦しめるだけだと、解っていたから…。
「あたしの…方こそ…、ありがとう…」
そしてあたしは、精一杯頑張って、笑みを浮かべた。
「…元気でね、ビャクヤ!」
頑張ってはみたけれど、きっとこの時のあたしは、上手く笑えてはいなかっただろう。
そんなあたしに、ビャクヤはほんの少しだけ哀しそうな表情を向けた後、ニッと、口の両端を吊り上げて、目を瞑るように
細めて笑った。
「…それじゃあね」
呟きと同時に背を向けると、ビャクヤはゆっくりと歩き出した。
フワフワ、フワフワと舞い降りる、淡雪の薄いカーテンの向こうへ遠ざかる、大きな背中…。
まるで、足かせでも付けられているように重い足取りで、ゆっくり、ゆっくり遠ざかって行く、最愛の人…。
降り続ける淡雪の中、木立の中に消えて行くその背中を、あたしはじっと見つめて、無言で見送った。
ビャクヤの姿が見えなくなった後も、あたしは淡雪に濡れながら、ずっと、その場に佇んでいた。
一人ぼっちになって寂しそうな影を、足下に連れたまま…。
食事が終わったフクロウが「ホウ」と鳴き、あたしは回想を中断した。
フクロウは挨拶するような一鳴きを残して、音も立てずに飛び立つ。
一人残されたあたしは、フクロウが飛び去った夜空と、そこに浮かんでいる丸い月をしばらく見上げた後、小屋の中に引き
返した。
そしてお風呂で体を流し、パジャマに着替え、ここ数ヶ月、週末の度に繰り返してきたように、小屋中のランプを消して回る。
それから、あたしが通うようになってからの数年間、あたし専用にして貰っていた寝室に入り、最後のランプを消す。
以前ビャクヤが作ってくれた、これも専用のベッドに横になったあたしは、窓越しに夜空を眺めた。
…今日の月は大きくて綺麗…。
ビャクヤも、どこかでこの月を見上げているのかな…。
元気にしてる?寂しくない?時々は、あたしの事も思い出してくれてる?
そして今日も、夢の中でビャクヤに会える事を願いながら、あたしは目を閉じる…。
…おやすみ…、ビャクヤ…。