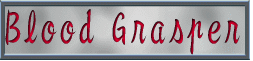
あたしの白夜(前編)
「おはよう!ビャクヤ!」
勢い良くドアを開けたあたしを、かまどの所で朝食を作っていた白犬が振り返った。
「おはよう。アサヒちゃん」
穏やかに微笑んだ、大きくてフワフワなビャクヤは、フライパンを振って野菜と肉の炒め物を宙に躍らせた。
「朝ごはん、まだかい?」
「うん」
あたしが来るのを待ち構えていたようなタイミングで、料理を終えたビャクヤは、お手製の木皿に盛り付けを始めた。
「最近はずいぶん暖かくなって来たねぇ。もう雪も見納めかな?」
「そうねぇ。あたしは嬉しいな。雪が降ると、登って来るだけで大変だから」
「雪が積ったら無理に来なくて良いんだからね?あんなのはもうこりごりだよ」
埋もれて動けなくなったあたしが、大声で助けを求めた時の事を引き合いに出して、ビャクヤは苦笑いした。
あの時、物凄い遠くから声を聞きつけて駆け付けてくれたビャクヤは、腰まで雪に埋まった状態で手を伸ばし、引っ張り出
してくれるようにせがんだあたしを見て、心底ほっとしたような顔をしていたっけ…。
「今日、イミナは?」
「来ないよ」
「あら珍しい…。それにしても、いつになったら、あたしとビャクヤのラブラブ生活が戻るのよ…」
頬を膨らませたあたしは、はたと気が付いた。
イミナは東京に行ったじゃない?もうここに通って来る事は…。
気付いた、いや、気付いてしまった途端、周囲の景色がぼやけた。
苦笑いを浮かべたままのビャクヤが、机が、椅子が、すぅっと透き通って、小屋も消えて、真っ暗になる。
…そう。気付いちゃったから、終わっちゃったんだ…、あの頃の回想のような夢が…。
月明かりが差し込む寝室で、あたしは薄く目を開けた。
ログハウスの天井を見上げているあたしの目の横を、耳に向かって涙が滑り落ちていった。
夢でいいから会いたい。
いつもそう思って目を閉じるのに、夢から醒めてみれば、眠る前よりも切ない気持ちになっている…。
あたしは目を擦りながら身を起こし、ベッドから降りた。
…喉、渇いちゃったな…。
寝室を出て、小屋のリビングへ向かったあたしは、保冷容器に納まった麦茶を、カップに注いでちょっとだけ飲んだ。
「…ふぅ…」
ため息をつき、何気なくドアに目を遣ったあたしは、小さな、でも確かな物音を耳にして、息を止めた。
ウッドテラスの床と、何かが擦れる音…!?
あたしはドアに駆け寄って、勢い良く開ける。
ウッドテラスに置かれた長椅子の脇、闇の中で、月光を照り返して光る目…。
勢い良く開けられたドアに驚いたのか、あたしを見つめて固まっていたタヌキは、我に返ると、木の床を引っかきながら大
慌てで駆け出し、手すりの隙間から庭に飛び降りて、闇の中に逃げ込んで行った。
期待は、やっぱり空振りだった…。
あたしは静かにドアを閉めて、小屋の中に戻り、目尻から零れた涙を拭う。
…ビャクヤが居なくなってからというもの、あたしは、事有る毎に泣いてばかりだ…。
勝気で強気なあたしは、一体何処に行ってしまったんだろう…?
微かな物音を耳にして、まどろみかけていたあたしは薄く目を開く。
寝室のドアが、軋んだのかしら…?
風の音かとは思ったけれど、念のために起き上がる。
もしかしたら、さっきドアを開けた時、閉め忘れたのかも?
小屋は寝室や浴室、倉庫以外はドアで区切られていない。リビングも通路も、歩きぬけの出入り口になっている。
だから、小屋の入り口のドアが開いていると、中に風が入って、あちこちが軋み音を立てたりする。
何よりも、虫が入り込むと嫌だ。
小、中学校時代、この町を離れている間に、いつのまにか苦手になっていた虫にも、この小屋に通うようになってからは随
分慣れた。
…けれど、脚が無駄に多い手合いは未だにダメ…!
無断侵入したムカデを素手で摘み上げ、あまつさえソレを手の平に乗せて、丁寧に退出願うビャクヤのような芸当は、あた
しには一生かかってもできそうにない。
食べる為以外には、なるべく生き物を殺さないというのが、彼のポリシーだった。
何故か蚊に刺されないビャクヤには、害虫を殺すという発想も無かったんだろうか?
寝室を出たあたしは、窓から入る月明かりを頼りにリビングに向かった。
短い通路を曲がり、リビングに一歩踏み入れたあたしの目に、うっすらとした月光を受ける影が映った。
窓から入り込んだ青白い光が照らす、入り口から少し入った所に佇む、大きな影。
それが、ゆっくりとあたしに向かって動いた。
「…あ…」
あたしは、思わず声を漏らしていた。
頭では信じられなかった。でも、心は確信していた。
姿は良く見えなかった。けれど、それが誰なのか、はっきりと判った。
輪郭しか見えなくとも、身じろぎした動きが、息遣いのリズムが、馴染んだそれらが誰なのかを教えてくれる。
「…ただいま、アサヒちゃん…」
影が発した優しい、穏やかな、耳慣れた声が、あたしの耳をくすぐった。
「びゃ…く…!」
あたしは、声を詰まらせて、愛しいひとの影に飛びついた。
暗闇の中でも、彼の目にはあたしの姿がきちんと見えているんだろう。
太くてたくましい腕が、そっとあたしを抱き寄せて、胸の中に抱き締めてくれた。
柔らかくて温かい、大きな体…。
汗をかいているのか、いつもとは違って濃い体臭がする…。
「ただいま…。アサヒちゃん…」
少し震える穏やかな声が、そう繰り返した。
「おか…えりっ…、ビャ…ク…!」
込み上げる嗚咽を押し殺そうとして失敗したあたしは、しゃくりあげてしまって、言葉を最後まで続けられなかった。
「う…、あっ…!うあぁぁぁあっ!うあぁぁぁああああああんっ!」
一度声に出してしまったら、抑えが利かなくなった。
「あっ、会いたかっ…た…!会いたかった…!会いたかった!ビャクヤぁあああああっ!」
泣きじゃくるあたしを、太い腕は強く抱き締めてくれた。
「…僕も…だよ…!」
ギュッと抱き締める、何よりも確かなその感触に身を委ねたあたしの耳に、ビャクヤはそっと囁いた。
「…待たせてごめん…。でも、僕はもう、何処にも行かないから…」
しがみついたまま離れないあたしを、ビャクヤはいつまでも、いつまでも、抱き締めてくれていた。
再びランプに火が灯された、夜更けのリビング。
くたびれた様子のビャクヤが、椅子に腰を下ろしている。
半分あぐらをかくように右足が横に寝かされていて、あたしはその足の上に座り、後ろからビャクヤに抱きかかえられる形
になっている。
一昼夜、休まずに駆け続け、大急ぎでここに戻って来てくれたらしい。
その事も嬉しかったが、何よりも嬉しかったのは、ビャクヤがあたしを抱き締めてくれている事。
いつもはあたしが抱き付いても、照れたような、困っているような顔で頬を掻いていたビャクヤが、今は自分からあたしを
抱き寄せてくれている。
「…ヨルヒコがね、あっちの皆にお願いしてくれたらしいんだ…」
汗と埃で汚れたビャクヤは、太い右腕であたしの体をしっかりと抱きながら口を開いた。
「僕には、こっちに大切な人が出来てしまった。だから、できれば今まで通りに暮らさせてくれないか?ってね…、あっちの
トップに直訴してくれたんだ…」
…イミナが…、そんな風に…?
あたしは驚きのあまり、気の利いた返事もできないまま、ビャクヤの言葉を聞いた。
「十数年ぶりに弟と会った…。ヨルヒコと会っていた彼から、その話を聞かされた…。弟もね、好きにして良いんだって、言っ
てくれた…」
イミナとは今でも連絡を取り合ってる。でも、あたしはその事を聞いていなかった。
たぶん、内情に関わる事だから話せなかったし、メールにも記せなかったんだろう。
励ますような、元気付けるようなあいつの電話やメールに、時には腹が立つこともあった。
あたしの気も知らないで、気軽に、楽観的に励ますな。
そんな風に、八つ当たり気味に考えたりした事もあった…。
今、はっきりと判った。
伝えるわけにいかなかったけれど、せめてビャクヤが帰るまで、少しでも元気でいられるように、あいつは気を遣ってくれ
ていたんだ…。
…ごめん、イミナ…。そしてありがとう…。
…あんたにももうちょっと、優しくしてあげれば良かったな…。
「…そういう訳でね、僕はこれからも、ここで暮らせる事になった」
しばらくの沈黙の後、ビャクヤは軽く咳払いして、しんみりしていた声の調子を、少し明るくして続けた。
「要請があれば協力する事にはなるけれど、それ以外は今まで通り、ここで自由気ままに過ごしていける」
ビャクヤはキュッとあたしを抱き締め直すと、顎をあたしの肩に乗せるようにして、耳元で囁いた。
「…そう…。今まで通りに…、これからも、君と…」
あたしは手を上げて、そっとビャクヤの頬に触れ、さすった。
手の平に湿った感触があって、ビャクヤもまた、泣いていた事が判った。
きっと、あたしを後ろ向きに抱き締めているのは、涙を見られるのが恥ずかしかったから…。
嬉しくて溢れ出た涙は止まらないのに、言葉は全く出て来なかった…。
あたしが持って来ていた麦茶をボトル一本、一気に飲み干して一息ついた後、
「…今更だけど、僕…、匂うよね?…ご、ごめんね?臭かった?」
ビャクヤは腕を持ち上げてフンフン匂いを嗅いだ後、あたしを見て、困ったように眉根を寄せた。
「そんな事無いわよ?」
だって、ずっと嗅ぎたかった、大好きなビャクヤの匂いだもん…。
「あ。お風呂に入る?一度湧かしたわよ?…もうだいぶ温くなっちゃったと思うけど…」
「それでも良いよ。有り難いなぁ…、ここ数日水すら浴びていなかったから、とにかく体を流したかったんだ」
あたしの言葉を聞いて嬉しそうに言ったビャクヤは、あちこち破れたオーバーオール、その肩ベルトの止め具をパチンと片
方外した。
「もう遅いし、休んでいてよ。僕も体を流したらすぐに寝るから」
抱き締めていた腕を放して、あたしを床に降ろして立ち上がるビャクヤ。
「起きたら、改めてゆっくり話をしよう。また、これまでと同じように、のんびりと過ごせるんだから…」
微笑みながらそう言って、浴室に向かおうとしたビャクヤの背中に、
「ま、待って…」
あたしは、後ろからしがみついた。
「だ、大丈夫だよアサヒちゃん!何処にも行ったりしないから…」
オーバーオールをしっかりと掴まれ、困ったような、驚いたような顔で振り向いたビャクヤの顔を、あたしはじっと見上げる。
「あの…、一緒に…」
これまでにも、一緒に入浴しようと何度も誘った。というか誘惑した。…全て失敗したけれど…。
でも、今回のあたしの欲求は、これまでにないくらいに強い。
二度と帰って来ないと思っていたビャクヤが、帰って来てくれた。
二度と会えないと思っていたビャクヤと、こうしてまた会えた。
嬉しさ。そして、もしかしたらこれも、あたしの願望が見せている夢なんじゃないかという不安。
それらがごちゃ混ぜになって、あたしの体を突き動かした。
目を離してしまったら、ビャクヤは居なくなってしまうんじゃないだろうか?
漠然とした、でも強い不安と、くっついていたいという抑え難い欲求…。
そんなあたしの心情を察したのか、ビャクヤはしばらく黙り込んだ後、あたしの頭にポンと手を乗せて、少し恥ずかしそう
に眉尻を下げながら頷いた。
たぶん今回も断られるんだろうと、半ば諦めてもいたあたしは、まず驚いて固まった。
「本当!?」
紅潮した顔を綻ばせて尋ねたあたしに、ビャクヤは長い前髪に太い指を突っ込んで、額の辺りをコリコリと掻きながら、小
さく頷いて見せた。
「…これまで…、散々…断って来たしね…」
浴室の床に敷いたすのこの上に、直接お尻を降ろして座ったビャクヤ。
その大きな背中に温くなった湯をかけたあたしは、たっぷりとボディシャンプーを塗って泡立てた。
いつもフサフサのたっぷりとした白い毛は、今は湯を吸ってぺたっと寝ている。
一緒にお風呂に入るのは、初めて会ったあの時…、あたしが幼稚園だった頃以来だ。
恥ずかしいのか、ビャクヤは体を硬くしていた。
これまではあまり見る機会が無かったけれど、ビャクヤの体は、完全に真っ白な訳じゃない。
普段はオーバーオールを着ているから判らないけれど、肩胛骨の下辺りから膝の辺りまでの毛は、薄い灰色になってる。
本物のオールドイングリッシュみたいな、しかもくっきり白抜けのツートンカラー…。
胸とお腹は白いけれど、肩甲骨よりちょっと下側からが灰色で、それは脇腹まで続き、丸く出っ張ったお腹の下へと繋がっ
て行く。
急に体積が減ってしまったようにも見えるのは、きっと濡れた毛が寝ているだけじゃなく、ビャクヤが体を縮めているから。
埃なんかで汚れて、黒ずんでいた部分も、丁寧に擦っていたらすぐに綺麗になった。
危険な事をしてきたはずだけれど、傷なんかは見えない。
もっとも、ビャクヤの体は私達と違って凄く丈夫だし、怪我をしてもすぐに塞がってしまうから、傷を負ったとしてももう
治ってしまっていて、私には解らなくなっているだけなのかもしれない。
「…ビャクヤ…」
「…う、うんっ?」
声をかけると、ビャクヤはビクッとして首を巡らせた。…声が裏返ってる…。
「また、少しの間離れて、判ったの…。二度と会えないんだって思って、はっきり思い知ったの…」
戸惑っているようなビャクヤの目から、視線を逸らさないように必死になって、あたしは続けた。
「…ビャクヤはいつも、もっと社会を見ろって、きちんと経験を積んで、色々な人を見て、それから決めろって言うけれど…。
あたし…、あたし、ね…」
もじもじと、ビャクヤの濡れた背中を擦りながら、あたしはからからになった喉を鳴らして、唾を飲み込んだ。
「あたしは…、後悔なんて絶対にしない…。これから先、どんな人に巡り会っても、どんな事を体験しても、あたしは…」
ビャクヤの目から顔を隠すように、あたしは俯いて、大きな声で叫んだ。
「あたしは、世界中の何よりも!誰よりも!ビャクヤが好きなのっ!」
あたしが振り絞った言葉は、浴室に反響して、耳元でわんわんと鳴った。
声の反響が治まると、急に静かになって、耳が痛くなるような静寂が浴室に満ちた。
高鳴ってるあたし自身の鼓動が、どこか遠くで鳴っているように、でもはっきりと感じられる。
それ以上の言葉を続けられなくなったあたしは、その嫌に長い沈黙の中、身じろぎ一つせず、俯いたまま、息を殺して待った。
…ビャクヤの、答えを…。
実際には一分と経ってない…。いや、もっと短かくて、数秒だったのかもしれない…。
やけに長く感じられた沈黙のあと、あたしは、俯いたままビャクヤの声を聞いた。
「…僕も、君ほど好きになった相手には、生まれてこの方、巡り会った事は無かったよ…」
静かで穏やかな、でも、はっきりとした声が、あたしの耳に届いた。
恐る恐る顔を上げると、首を巡らせたさっきの姿勢のまま、照れ笑いしているビャクヤの顔が目に飛び込んできた。
「…もう一度だけ、聞いても良い?本当に…、僕なんかで良いの?」
あたしは、大きく一度頷く事で、ビャクヤの問い掛けに答えた。
「…ありがとう…。アサヒちゃん…」
ビャクヤは、目を瞑るように細めて微笑んだ。
目尻に少し光って見えたのは、跳ねた湯の飛沫だろうか?それとも、涙だろうか?
どっちなのかは判らなかったけど、あたしはそっと、ビャクヤの背中に抱き付いた。
今までならやんわりと身を離していたビャクヤは、顔を前に向けて少し身じろぎしただけで、抱き付いたままにさせてくれた。
激しくなっているあたしの鼓動と、彼の背中に押し当てた乳房に感じられるビャクヤの鼓動が、溶けて一つになって行くよ
うな気がした。
十分に温もりを堪能した後、あたしは身を離しながら囁いた。
「ビャクヤ…。愛してる…」
「…僕も…、愛してるよ、アサヒちゃん…」
背中を向けたままで応じたビャクヤの背中を、あたしは指でつつく。
「こっち、向いてよ…」
「ん…、んん〜…」
ビャクヤは少し躊躇った後、すのこの上に手をついて、体を180度回転させた。
…初めて見る、一糸纏わないビャクヤの裸…。
逞しく太い腕に、丸く盛り上がった肩。
マフラーのように豊かだった首元の毛は、今は濡れて寝ている。
筋肉と脂肪で丸く出た、ちょっと垂れ気味の胸のラインがはっきりと判る。
軽く叩くと「ポンッ」と良い音がするお腹は、ポッコリ丸々と突き出ている。
…その下…、あぐらをかいている太い脚の間に…、薄い灰色の毛の中に…、男のシンボルがあった…。
生で見るのは、ビャクヤが二人目だ…。
一人目はお父さん。まだ子供の頃、一緒にお風呂に入っていた頃は何度も見た。
けれど、何と言うか…、ビャクヤのはその…、体に比例してなのか、…お、大きい…!
長い灰色の毛に半分埋もれているけれど、太さははっきりと判る。
ビャクヤのおちんちんの先、湯で濡れた亀頭とかいう部分が、濃い桃色に光っていた。
まん丸で濃いピンク色のそれは、心配していたほどグロテスクには感じなかった。むしろ、可愛くて愛おしい…。
比較対象をあまり知らないけれど、たぶんビャクヤのは特別大きいんだろう。
世の男共の股間全てにこんなモノがぶら下がっていたら、服の上からでもシルエットが判ってしまうはず…。
「あ、あんまりまじまじ見ないでくれるかなあ…」
困ったように顔を歪ませて言ったビャクヤに、
「びゃ、ビャクヤこそ…」
あたしは顔を真っ赤にしながらそう返す。
あたしがビャクヤの裸を見つめていたように、ビャクヤの視線もあたしの体を撫で回していた。
スタイルにはそこそこ自信がある。
胸は同級生と比べても結構大きい方だし、お腹はきちんとくびれている。
いつもヒップラインを強調するきつめの下着を身につけていたおかげで、お尻もキュッと上がっている。
いつか、ビャクヤにじっくり見られても恥ずかしくないように、常に気を配ってきたスタイル…。
…でも、今はとにかく、恥ずかしい…。
じっと見られる羞恥に耐えかねて、あたしは膝立ちのまま一歩進んで、ビャクヤに寄った。
そして、同じ高さにある顔を近付ける。
あたしが求めているモノに気付いたんだろう、ビャクヤは一度目を大きくしてから、ごくん、と大きな音を立てて唾を飲み
込んだ。
あたし達はそろそろと顔を近付け、そして、唇を重ねた。
頬やおでこへの不意打ちはこれまでに何度かやった。そのうち何度かは唇も奪えた。
けれど、ビャクヤも唇を重ねてきてくれるのは、これが初めての事…。
重ねた唇を割って、ビャクヤの舌があたしの口の中に滑り込んだ。
「…んっ…!」
ビャクヤは、予想外に積極的だった。
激しく口の中を舐め回す、ビャクヤの長い舌が、頬の内側を撫で、歯茎を先で擦り、あたしの舌に絡み付く。
初めて経験する、舌を絡めるディープキス…。
身も心もとろけてしまいそうな心地良さは、きっとキスの快楽だけがもたらしたものじゃない。
何年もの間、想い焦がれてきて、やっと受け入れて貰えた嬉しさ…。
二度と会えないと思っていたビャクヤが、こうして帰ってきてくれた喜び…。
それらがきっと、胸の中でトロトロとたゆたう、安らぎと興奮が混じり合ったこの気持ちを生み出している…。
望んでいた、でも想像していた以上に激しいディープキスに、あたしは息を荒げながらビャクヤの首に腕を回して、必死に
なってしがみつく。
ビャクヤはそんなあたしに応えるように、脇の下から背中側に逞しい腕を回して、しっかりと、優しく抱き締めてくれた。
ビャクヤの広い胸にあたしの乳房が押し付けられる。
お互いに弾力をもった胸が、ひしゃげて潰れ、密着している。
荒い息遣いと鼓動をお互いの胸を通して感じながら、あたしたちは貪るように唇を吸いあった。
やがて、長い、長い口付けの後、あたしたちは唇を離す。
あたしとビャクヤの唇の間で、唾液が糸になって、アーチを描いて、やがて、切れて落ちていった。
間近で見る、恥ずかしそうなビャクヤの顔は、まるであたしと同年代の男の子のように初々しく見えた。
きっと、純情さと身持ちの堅さでは、ビャクヤは正に天然記念物級だ。
あたし達はお互いの顔を見つめ合い、照れ笑いを浮かべた。
…ビャクヤの笑顔は幸せそうに見えて…、あたしはとても、嬉しかった…。
キスを交わしながら抱き締め合ったあたし達は、まだぴったりと体をくっつけている。
あぐらをかいた太い脚の上に座る格好で、あたしはビャクヤの胸にしなだれかかった。
頬をすり寄せたビャクヤの胸から、温もりと鼓動が伝わって来る…。
目を閉じたあたしの頭を、ビャクヤはそっと撫でてくれた。
しばらくの間、言葉もなく身を寄せ合った後、あたしはビャクヤの顔を至近距離で見上げた。
「ねぇ…、ビャクヤ…」
「うん…?」
あたしは異様に熱く感じる息を漏らしながら、潤んだ瞳で、愛しい男の瞳を見つめる。
「…抱いて、くれる…?」
初めて経験した、激しく長いディープキスでかなり興奮したせいなのか、あたしの秘所はもう、自ら湿り始めていた。
驚くかとも思っていたけれど、ビャクヤは穏やかな表情を変えず、あたしの瞳をじっと覗き込んだ。
そして、少しの間をあけた後、ゆっくりと顎を引いて頷いてくれた。
ちょっとだけ恥ずかしそうに、目を細めながら…。
「…嬉しい…!」
再び胸に顔を埋めたあたしは、頬ずりしながらビャクヤの首を撫でた。
「…その前に…」
ビャクヤは少し困ったように呟いて、あたしは顔を上げる。
「…しっかり体を洗っていかないと…。…そのぉ…、まともな入浴は、実のところ三ヶ月ぶりだから…」
恥ずかしそうな微苦笑を浮かべたビャクヤに、あたしは微笑みながら頷いた。
「うん!あたしが隅々まで綺麗にしてあげるわ!」
期待混じりの予感はあった。
帰ってきてくれたビャクヤが、今までとは違って、自分からあたしを抱き締めてくれたから。
あたしがずっと差し出し続けてきた想いを、やっとビャクヤは受け取ってくれた…。
お風呂から上がったあたし達は、リビングで冷えた麦茶を飲んだ。
お互いに言葉は無い。
いつもならあたしがあれこれ話題を出して、ビャクヤがそれに応じて色々な答えや反応を返してくれる。
夜更けまで語り合っても、ぜんぜん飽きる事のない、言葉のキャッチボール。
でも、今夜に限っては、それがほとんど無い。
今のあたし達は、ボールを投げ合ったりはしない。
ボールを直接手渡せる程、ピッタリとくっついているから。
あたしはマグカップから顔を上げ、向かいに座ったビャクヤを見る。
微笑みかけてくれたビャクヤは、トランクス一枚のラフスタイル。
これまでなら、そう簡単には見せてくれなかった、くつろぎきった格好だ。
あたしの方は、今はまたパジャマを着ている。
すぐに脱ぐんだから、わざわざ着るのも面倒だったけれど…、
「夏とは言っても、山の夜、ましてこの丸太小屋じゃあ冷える。体を冷やして風邪でもひかれたら困るよ」
と、ビャクヤに気遣われ、一度はパジャマ姿に戻る事にした。
あたしが麦茶を飲み終えると、ビャクヤは立ち上がり、カップ二つを流し台に運んだ。
トランクス一丁の白犬が丁寧にマグカップを洗っている後ろ姿は、こんなにも大きな体をしているのに、なんだかとても可
愛らしかった。
あたしはそっと立ち上がり、ビャクヤに歩み寄って、背中にぺたっとくっついた。
ビャクヤは手を休めないまま、小さく「ふふっ」と笑う。
「いつかはね、こういう日が来れば良いなって、実は心の底で思っていた」
ビャクヤの声はいつもと変わらず穏やかだったけれど、少し嬉しそうで、恥ずかしそうで、困っているようですらあった。
「それはいつから?」
尋ねたあたしに、ビャクヤはまた小さく笑う。なんだか少し楽しそうに。
「予約をした頃からかな?まぁ、その頃はちょっとそんな事を思うくらいで、それほど本気で考えてもなかったんだけれどね。
アサヒちゃんはきっと、僕なんかよりもずっと良い男を見つけると思っていたから」
「あ、ひどぉい!あたしはずっと本気だったのに!」
あたしは怒ったふりをして、ビャクヤの背中に軽く頭突きする。
「はは、ごめんごめん。…いつかはここを離れなければならなくなるかもしれない…。そうも思っていたから、本気にならな
いように必死だったよ」
ビャクヤの言葉が耳に届いて少ししてから、あたしはそこに込められた意味に気付いて、嬉しくなった。
…本気にならないように…必死だった…。
ビャクヤも、あたしの事をちゃんと…想ってくれていたんだ…。
やがて来るかもしれない別れに備えて、その気持ちを押さえ込んでいたんだ…。
「ねぇ、ビャクヤ」
「うん?」
洗い物が終わったにもかかわらず、背中に抱き付かれたまま、じっとしているビャクヤに、あたしはちょっと意地悪な質問
をしてみた。
「ビャクヤも、寝室でオナニー、してたんでしょ?」
予想通り、ビャクヤは小さく息を飲んでピクンっと硬直した。
あたしは当然知っていた。
掃除を手伝ったりしてるんだから、時折出現していた、妙な匂いがする丸めたティッシュの存在に気付かない訳がない。
「するときは…、あたしの事を考えたりとか、してくれてた?」
あたしの問い掛けに、たっぷり二十秒は間を空けてから、ビャクヤは頷いた。
あたしは、ビャクヤの太い体に回した手に力を込め、ぎゅっと、強く抱き付く。
「…嬉しい…!」
ビャクヤがあたしになびかないのは、そもそも好みじゃないから?以前、何度かそう思った事もある。
でも違っていた。あたしを束縛しないようにと気遣って、自分の気持ちを抑えていただけなんだ…。
「ねぇ、ビャクヤ…。そろそろ…」
あたしはふかふかの背中に頬ずりして、ビャクヤに催促した。
ビャクヤがゴクリと、大きな音を立てて唾を飲み込んだのが、背中越しに判った。
「あ、アサヒ…ちゃん…。今の内に、一つ言っておきたいんだけど…」
ビャクヤは、何故か体をギチギチに硬くして呟いた。
「うん。何?」
「…え、えぇと…、いや、やっぱり良い…。あ、いや、良くない。黙ってるのは良くないな、うん…」
ビャクヤはブツブツと呟いた後、首を捻ってあたしを見下ろした。
「あ、あのね?アサヒちゃん…」
「うん?」
「実は僕…、その…」
ビャクヤは眉を八の字にして、ぼそぼそっと言った。
「…僕…、本番の経験…まだ無いんだ…」
………。
「ひ、ひくよねっ!?こ、ここ、こんな歳になって…、ど、童貞だなんて!?」
ビャクヤはオドオドと、あたしの顔色を窺った。
こんなに動揺してるビャクヤ、料理にタマネギを混ぜたあの一件を除けば、初めて見る…。
「あ〜、いや〜、もしかしたら、そうかも?くらいには思ってたから…」
何を今更?あたしにすればそんな感じだけど、ビャクヤはかなりビックリしている。
「え?な、何で!?」
「だってビャクヤ、モテないって自分で言ってたでしょ?」
「う!?う、うん、そうだけど…」
「おまけに十数年間、山の中で一人暮らしじゃない?」
「え?それも、そう、だけど…」
「だから、もしかしたら…ぐらいには」
ビャクヤはしばらく黙り込んだ後、
「…はは…。勇気を振り絞って、打ち明けたのになぁ…」
と、安心したような、そしてちょっと情けないような、微妙な半笑いで呟いた。
ビャクヤは、今までに私が見た事の無い、とても…、とっても可愛い顔をしていた…。